アライグマが家に来る理由は?【食料と隠れ場所を求めて】誘因を断つ5つの効果的な対策法を紹介

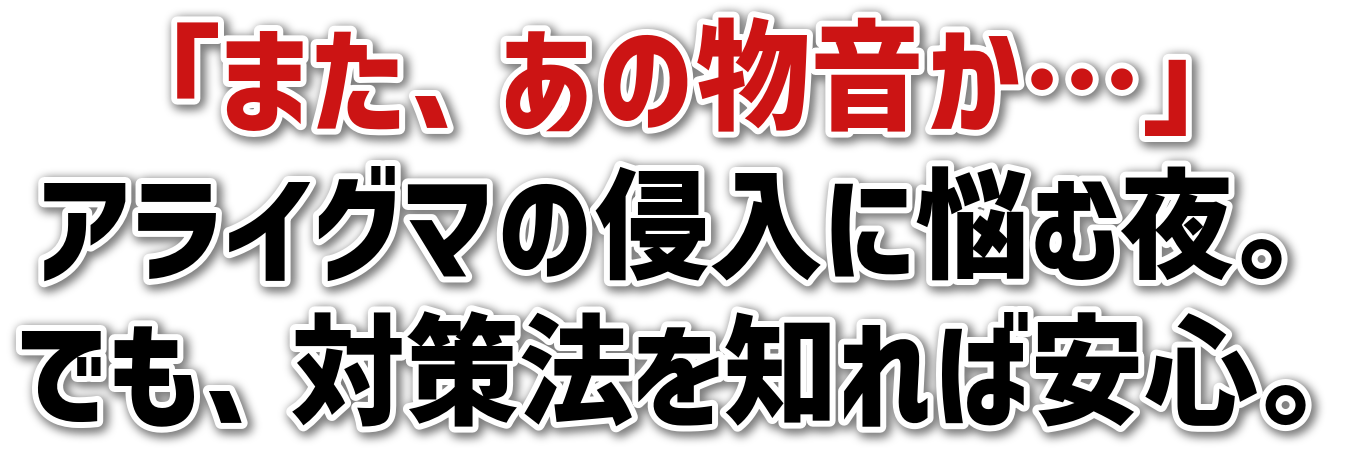
【この記事に書かれてあること】
アライグマが家に来る理由、気になりませんか?- アライグマが家に来る主な理由は2つ
- 果物や生ゴミが食料源として狙われやすい
- 屋根裏や物置が隠れ家として好まれる
- 春から秋にかけて被害が増加する傾向
- 家屋の構造や築年数によって侵入リスクが変わる
- 隙間封鎖や臭いを使った効果的な対策法がある
実は、この可愛らしい外見の動物、私たちの家を格好の食事処や隠れ家と見なしているんです。
果物や生ゴミを求めてやってきて、屋根裏や物置に住み着いてしまうことも。
しかも、春から秋にかけては特に要注意。
家の構造によっては、知らぬ間に「アライグマウェルカム」な環境になっているかもしれません。
でも大丈夫。
この記事では、アライグマが家に来る理由を詳しく解説し、効果的な対策方法もご紹介します。
さあ、アライグマとの知恵比べ、始めましょう!
【もくじ】
アライグマが家に来る理由とは?食料と隠れ場所が鍵

アライグマの好物は「果物」と「生ゴミ」!庭と台所に注意
アライグマが家に来る最大の理由は、食べ物を求めているからです。特に果物と生ゴミに目がないんです。
「おや?庭のリンゴが勝手に消えてる…」なんて経験はありませんか?
実はこれ、アライグマの仕業かもしれません。
アライグマは甘いものが大好き。
果物の中でも特に甘いリンゴやブドウ、イチゴなどを好んで食べます。
でも、アライグマの食欲はそれだけじゃありません。
台所から出る生ゴミも、彼らにとっては魅力的な食事なんです。
「え?生ゴミを食べるの?」と思うかもしれませんが、アライグマにとっては立派なごちそう。
魚の残りや野菜くず、果物の皮など、人間が捨てるものも彼らの口に合うんです。
そのため、アライグマ対策として以下の点に注意が必要です。
- 果樹園や菜園には柵を設置する
- 熟した果物はすぐに収穫する
- 生ゴミは密閉容器に入れる
- ゴミ出しは収集日の朝に行う
- コンポストは蓋付きのものを使用する
食べ物がなければ、アライグマも別の場所を探すようになるでしょう。
家の周りをアライグマにとって「美味しくない場所」にするのが、対策の第一歩なんです。
屋根裏や物置が狙われる!暗くて暖かい場所を好むワケ
アライグマが家に来るもう一つの大きな理由は、隠れ場所を探しているからです。特に屋根裏や物置が狙われやすいんです。
なぜアライグマはこんな場所を好むのでしょうか?
それは、彼らの生態と深く関係しています。
アライグマは本来、森林に住む動物。
木の洞や岩の隙間などを住処にしています。
そのため、人間の家の中でも似たような環境を探すんです。
「じゃあ、うちの屋根裏は大丈夫かな…」と心配になってきませんか?
実は、アライグマが好む隠れ場所には、いくつかの特徴があるんです。
- 暗くて静かな場所
- 暖かくて乾燥している場所
- 人目につきにくい場所
- 出入りが自由な場所
- 子育てに適した安全な場所
特に春から夏にかけては、子育ての時期。
安全で快適な場所を必死で探しています。
対策としては、家の周りをこまめにチェックすることが大切です。
小さな穴や隙間も見逃さないようにしましょう。
アライグマは直径10センチほどの穴があれば、そこから侵入できてしまうんです。
「え!そんな小さな穴から入れるの?」と驚くかもしれません。
でも、アライグマの体は意外と柔らかくて、細い隙間もすいすい通り抜けられるんです。
ですから、見つけた穴はすぐにふさぐことが重要。
金網や板で塞いで、侵入を防ぎましょう。
こうして隠れ場所をなくすことで、アライグマは別の場所を探すようになります。
家をアライグマにとって「住みにくい場所」にするのが、効果的な対策なんです。
春から秋が要注意!季節によって変化するアライグマの行動
アライグマの行動は季節によって大きく変わります。特に春から秋にかけては要注意。
この時期、アライグマは最も活発に活動するんです。
「え?冬は大丈夫なの?」と思うかもしれません。
実は、アライグマは完全な冬眠はしません。
活動は減りますが、暖かい日には外出することもあるんです。
では、季節ごとのアライグマの行動を見てみましょう。
- 春:繁殖期。
食べ物を求めて活発に動き回ります。 - 夏:子育ての季節。
食べ物と安全な隠れ場所を必死で探します。 - 秋:冬に備えて食べ物を貯める時期。
果物や野菜が豊富なこの時期、庭や畑への被害が増えます。 - 冬:活動は減少しますが、完全に休眠するわけではありません。
暖かい隠れ場所を探して、家に侵入することも。
実は、夏から秋にかけてが最も要注意なんです。
なぜなら、この時期は食べ物が豊富で、アライグマの活動も最も活発になるから。
特に、果物が熟す時期は要注意です。
対策としては、季節に応じた対応が効果的。
例えば、夏から秋にかけては果樹園や菜園の管理を徹底し、熟した果物はすぐに収穫しましょう。
また、冬に向けては家の隙間をしっかり塞ぎ、暖かい隠れ場所を作らないことが大切です。
「でも、毎日対策するのは大変…」と思うかもしれません。
確かに手間はかかりますが、アライグマによる被害を防ぐためには必要なんです。
季節の変化を意識しながら、こまめな対策を心がけましょう。
そうすれば、年間を通じてアライグマを寄せ付けない環境が作れるはずです。
餌付けはNG!アライグマを寄せ付けない3つの対策
アライグマを寄せ付けないためには、餌付けは絶対にNGです。意図せず餌付けしてしまっているケースも多いんです。
では、どうすればいいのでしょうか?
まず、アライグマを寄せ付けない3つの重要な対策をご紹介します。
- 食べ物を置かない:庭に果物や野菜くずを放置しないこと。
ペットのエサも戸外に置きっぱなしにしないようにしましょう。 - ゴミの管理を徹底する:生ゴミは密閉容器に入れ、収集日まで戸外に出さないこと。
コンポストは蓋付きのものを使いましょう。 - 家の周りを整理整頓する:アライグマが隠れられそうな場所(木材の山や放置された箱など)を片付けましょう。
でも、これらの対策は驚くほど効果があるんです。
アライグマは頭がよく、一度食べ物があった場所を覚えています。
「ここにはおいしいものがある」と学習すると、何度も訪れるようになってしまうんです。
だから、最初から餌付けしないことが大切なんです。
さらに、アライグマを寄せ付けない環境作りのコツをいくつか紹介します。
- 庭の果樹には網をかける
- 夜間はペットを室内に入れる
- 屋外の水場(池や水鉢)を減らす
- 明るい照明を設置する
- 動物が嫌う香り(ペパーミントなど)を利用する
「面倒くさそう…」と思うかもしれませんが、一度習慣になれば、それほど大変ではありません。
アライグマとの共存は難しいかもしれません。
でも、私たちの生活を守るためには必要な対策なんです。
「アライグマさん、ごめんね。でも、ここには来ないでね」という気持ちで、粘り強く対策を続けていきましょう。
アライグマの侵入経路と家屋構造の関係性

屋根vs壁!アライグマが侵入しやすい場所はどっち?
アライグマが侵入しやすい場所は、圧倒的に屋根です。壁よりも屋根の方が、侵入口が多いんです。
「えっ、屋根からも入ってくるの?」と驚く方も多いかもしれません。
でも、アライグマは驚くほど器用な動物なんです。
木登りが得意で、垂直な壁でもすいすい登っていけます。
屋根の隙間から侵入するアライグマの特徴は、以下の通りです。
- 屋根瓦のすき間を利用する
- 破損した軒下から侵入する
- 雨どいを伝って屋根に上る
- 屋根裏換気口から侵入する
- ドーマーウィンドウの隙間を狙う
なぜなら、壁は基本的に隙間が少なく、アライグマが入り込みにくいからです。
でも、古い家屋や木造住宅の場合は要注意。
経年劣化で壁に隙間ができやすく、そこから侵入される可能性があります。
「うちは大丈夫かな?」と心配になってきませんか?
実は、アライグマは直径わずか10センチの穴があれば侵入できるんです。
屋根や壁のちょっとした隙間も、アライグマにとっては立派な侵入口になっちゃうんです。
対策としては、定期的に屋根や壁をチェックし、小さな隙間も見逃さないことが大切です。
特に屋根まわりの点検は重要。
雨どいや軒下、換気口などをしっかりチェックしましょう。
隙間を見つけたら、すぐに修理するのが一番の予防法です。
アライグマに「いらっしゃいませ」と言わないためにも、家のメンテナンスをこまめに行いましょう。
換気口と煙突に要注意!意外な侵入口と対策方法
アライグマの意外な侵入口として、換気口と煙突があります。これらは家の中と外をつなぐ経路なので、アライグマにとっては格好の侵入ルートなんです。
「まさか、そんな小さな穴から入ってくるの?」と思うかもしれません。
でも、アライグマは驚くほど柔軟な体を持っているんです。
直径10センチほどの穴があれば、体を縮めてスルスルっと入り込んでしまいます。
換気口と煙突からのアライグマ侵入の特徴は、こんな感じです。
- 屋根や壁の換気口を格子ごと外して侵入
- 煙突の上部から滑り降りて家の中へ
- 換気扇のカバーを外して台所に侵入
- 浴室の換気口から天井裏へ忍び込む
- トイレの換気口を利用して侵入
しっかりとした金網や格子を取り付けることです。
「でも、換気ができなくなっちゃわない?」って心配する必要はありません。
通気性を確保しながら、アライグマの侵入を防ぐ特殊な網や格子がたくさん市販されているんです。
対策の具体例をいくつか挙げてみましょう。
- 換気口に強固な金網を取り付ける
- 煙突の上部に金属製のキャップを設置
- 換気扇に取り外しにくいカバーを使用
- 浴室やトイレの換気口に細かい網を付ける
家のあちこちにある「アライグマへの招待状」を、しっかりと封印しちゃいましょう。
こまめなチェックと適切な対策で、アライグマに「ごめんなさい、ここは入れません」とお断りできるはずです。
古い家屋vs新築!アライグマ被害リスクの差は歴然
アライグマ被害のリスク、実は古い家屋と新築では大きな差があるんです。結論から言うと、古い家屋の方がずっと危険です。
「えっ、そんなに違うの?」って思いますよね。
でも、その通りなんです。
古い家屋は、アライグマにとって魅力的な侵入ポイントがいっぱい。
一方、新築は比較的安全なんです。
では、古い家屋と新築の違いを詳しく見ていきましょう。
- 古い家屋の特徴
- 経年劣化による隙間や穴が多い
- 屋根や壁の材質が劣化している
- 換気口や煙突の防護が不十分
- 雨どいや軒下が傷んでいる
- 新築の特徴
- 建材や構造が最新で隙間が少ない
- 換気システムが改良されている
- 屋根や壁の素材が丈夫
- 害獣対策を考慮した設計
あちこちに隙間があって、アライグマにとっては天国のような環境なんです。
一方、新築は「お断りします」の看板を掲げているようなもの。
アライグマが侵入できる隙間がほとんどないんです。
ただし、新築だからといって油断は禁物。
時間が経てば経つほど、家にも隙間ができてきます。
「うちは新築だから大丈夫」なんて思っていると、ある日突然アライグマに「こんにちは」って言われちゃうかも。
対策としては、古い家屋であれば大規模な修繕を検討するのがベスト。
新築の場合も、定期的なメンテナンスを怠らないことが大切です。
例えば、こんな対策がおすすめです。
- 年に1回は屋根や壁の点検を行う
- 小さな穴や隙間を見つけたらすぐに修理
- 換気口や煙突に頑丈な防護ネットを設置
- 雨どいや軒下の定期的な清掃と補修
家のメンテナンス、面倒くさいと思うかもしれません。
でも、アライグマとの同居生活を避けるためには、必要不可欠なんですよ。
木造と鉄筋の比較!アライグマに強い家の特徴とは
アライグマに強い家って、どんな家でしょうか?実は、木造と鉄筋コンクリート造では、アライグマへの耐性に大きな違いがあるんです。
結論から言うと、鉄筋コンクリート造の方がアライグマに強いんです。
木造住宅は、アライグマにとって侵入しやすい構造になっていることが多いんです。
「えっ、そんなに違うの?」って思いますよね。
でも、その通りなんです。
木造と鉄筋の違いを、詳しく見ていきましょう。
- 木造住宅の特徴
- 建材が柔らかく、アライグマが爪で傷つけやすい
- 経年劣化で隙間ができやすい
- 屋根裏や壁の中に空間があり、住処になりやすい
- 木の香りがアライグマを引き寄せる可能性がある
- 鉄筋コンクリート造の特徴
- 建材が硬く、アライグマが傷つけにくい
- 隙間ができにくい構造
- 壁の中に空間がなく、住処になりにくい
- コンクリートの無機質な臭いはアライグマを引き寄せにくい
柔らかい木材は、アライグマの鋭い爪や歯で簡単に傷つけられてしまいます。
一方、鉄筋コンクリート造は「立ち入り禁止」の看板を掲げているようなもの。
硬いコンクリートは、アライグマにとって難攻不落の城塞のようなものなんです。
ただし、鉄筋コンクリート造だからといって、完全に安全というわけではありません。
換気口や窓など、弱点になる部分はあるんです。
では、どんな対策が効果的でしょうか?
木造住宅の場合は、こんな対策がおすすめです。
- 外壁を硬い材質でコーティング
- 屋根裏や壁の隙間をしっかり埋める
- 定期的に家全体の点検を行う
- 木材の防腐・防虫処理を行う
こんな対策を心がけましょう。
- 換気口や窓に頑丈な防護ネットを設置
- ベランダや屋上の排水口をチェック
- 外壁のひび割れを定期的に補修
- 樹木が建物に接触しないよう剪定
アライグマに「ここは入れません」とはっきり伝えられる家作りを心がけましょう。
家のタイプに合わせた対策で、アライグマとの意外な遭遇を防ぎましょう。
二階建てvs平屋!アライグマが好む家屋構造の秘密
アライグマが好む家屋構造、実は二階建てと平屋では大きな違いがあるんです。結論から言うと、二階建ての方がアライグマに狙われやすいんです。
「えっ、そうなの?」って驚く方も多いかもしれません。
でも、アライグマの習性を考えると、納得できる理由があるんです。
では、二階建てと平屋の違いを詳しく見ていきましょう。
- 二階建ての特徴
- 屋根裏空間が広く、隠れ家に最適
- 高い位置に侵入口があり、安全
- 複雑な構造で、人目につきにくい
- 雨どいが長く、登りやすい
- 平屋の特徴
- 屋根裏空間が狭い
- 地上から近く、侵入リスクは高い
- 構造がシンプルで、隠れにくい
- 雨どいが短く、登りにくい
広い屋根裏は最高の隠れ家になりますし、高い位置にあるので安全感もあります。
まるで、アライグマに「ようこそ、素敵な住処へ」と言っているようなものです。
一方、平屋は「ちょっと物足りないな」という感じ。
屋根裏が狭いので、アライグマにとっては窮屈です。
また、地上から近いので、人間に見つかるリスクも高くなります。
ただし、平屋だからといって安心はできません。
地上に近いぶん、侵入口が見つけやすいというデメリットもあるんです。
では、どんな対策が効果的でしょうか?
二階建ての場合は、こんな対策がおすすめです。
- 屋根裏への侵入口をしっかり塞ぐ
- 雨どいにトゲトゲした板を取り付けて登りにくくする
- 屋根や壁の隙間を定期的にチェックし修理
- 二階の窓やベランダに防護ネットを設置
- 地面近くの侵入口をしっかりふさぐ
- 換気口や排水口に頑丈な格子を設置
- 庭の木や物置を家から離して設置
- 外壁を定期的に点検し、小さな穴も見逃さない
「うちは大丈夫」なんて油断は禁物。
アライグマは意外と頭がいい動物なので、ちょっとした隙を見逃しません。
家の構造に合わせた適切な対策を行い、アライグマに「ここは住処には向いていないよ」とはっきり伝えましょう。
こまめなチェックと適切な対策で、アライグマとの思わぬ同居生活を避けることができるはずです。
家族の安全と快適な暮らしのために、アライグマ対策、侮れませんよ。
アライグマ撃退!効果的な対策と予防法

隙間封鎖が最強!直径10cm以下の穴をふさぐ技
アライグマの侵入を防ぐ最強の方法は、隙間封鎖です。特に直径10センチ以下の穴をしっかりふさぐことが大切です。
「え?そんな小さな穴からアライグマが入れるの?」と驚く方も多いでしょう。
でも、アライグマは意外と体が柔らかくて、小さな隙間でもスルスルっと入り込んでしまうんです。
では、どうやって隙間を封鎖すればいいのでしょうか?
具体的な方法をいくつか紹介しますね。
- 金属製のメッシュを使う(網目は6ミリ以下がおすすめ)
- コーキング剤で小さな隙間を埋める
- 木材や金属板で大きな穴をふさぐ
- 換気口には特殊な格子カバーを取り付ける
- 煙突にはキャップを設置する
屋根の軒下や壁との接合部、そして家の基礎と地面の間の隙間は、アライグマのお気に入りの侵入口なんです。
「でも、全部の隙間を見つけるのは大変そう…」と思いますよね。
確かに一人で全てをチェックするのは難しいかもしれません。
そこで、こんな方法はいかがでしょうか?
- 家族や友人と協力して、外壁を一周チェック
- 夜に外から明かりを当てて、内側から光が漏れる場所を探す
- 雨の日に家の周りを歩いて、水がしみ込む場所をチェック
隙間封鎖は地道な作業ですが、アライグマ対策の基本中の基本。
「ここは入れません」とアライグマに強くアピールする、最も効果的な方法なんです。
少し面倒くさいかもしれませんが、家族の安全と快適な暮らしのために、ぜひ頑張ってみてくださいね。
光と音でビックリ!アライグマを怖がらせる裏技
アライグマを撃退する効果的な方法として、光と音を使った対策があります。これらはアライグマをビックリさせて、寄せ付けない環境を作るんです。
「え?そんな簡単なことでアライグマが来なくなるの?」と思うかもしれません。
でも、アライグマは意外と臆病な動物。
突然の光や音に弱いんです。
では、具体的にどんな方法があるのか見ていきましょう。
- 光を使った対策
- 動きを感知して点灯する強力な照明を設置
- ソーラー式の点滅ライトを庭に置く
- 反射板や鏡を使って光を反射させる
- 音を使った対策
- 超音波発生装置を設置(人間には聞こえない音でアライグマを追い払う)
- 風鈴やチャイムを多数取り付ける
- ラジオを低音量で夜中につけっぱなしにする
例えば、動きを感知するライトと超音波発生装置を同時に作動させれば、アライグマは「ギョッ」となって逃げ出すかもしれません。
ただし、注意点もあります。
近所迷惑にならないよう、音量や光の強さには気をつけましょう。
また、アライグマは賢い動物なので、同じ刺激に慣れてしまう可能性もあります。
定期的に設置場所や方法を変えると、効果が持続しやすくなりますよ。
「でも、そんなの面倒くさそう...」と思う方もいるかもしれません。
確かに手間はかかりますが、アライグマの被害を防ぐためには効果的な方法なんです。
家族の安全と快適な暮らしのために、ちょっとした工夫を重ねていきましょう。
光と音を使ったアライグマ対策、まるで楽しいイタズラのようですね。
アライグマに「ここは居心地が悪いよ」とアピールして、自然と遠ざかってもらう。
そんな穏やかな方法で、アライグマとの共存を目指してみてはいかがでしょうか。
臭いで撃退!アンモニアや柑橘系の香りが効果的
アライグマを撃退する意外な方法として、臭いを使った対策があります。特にアンモニアや柑橘系の香りが効果的なんです。
「えっ、臭いだけでアライグマが来なくなるの?」と驚く方も多いでしょう。
でも、アライグマは鼻が敏感。
嫌いな臭いがする場所には近づきたがらないんです。
では、具体的にどんな臭いがアライグマ撃退に効果があるのか、見ていきましょう。
- アンモニア臭:尿の臭いと勘違いさせる
- 柑橘系の香り:レモンやオレンジの皮の香りが苦手
- 唐辛子の辛み成分:鼻や目を刺激して不快に
- ペパーミントオイル:強烈な清涼感がアライグマを寄せ付けない
- ニンニク:強烈な臭いがアライグマを遠ざける
- アンモニア臭のある尿素肥料を庭に撒く
- レモンやオレンジの皮を侵入しそうな場所に置く
- 唐辛子パウダーを水で薄めて、スプレーで散布
- ペパーミントオイルを染み込ませた布を置く
- ニンニクをすりおろして水で薄め、庭に撒く
強すぎる臭いは人間にも不快ですし、ペットにも影響があるかもしれません。
また、雨が降ると効果が薄れてしまうので、定期的な補充が必要になります。
「でも、家の周りが臭くなっちゃわない?」と心配する方もいるでしょう。
確かにその通りです。
でも、アライグマ被害を防ぐためには効果的な方法なんです。
使用する量や場所を工夫すれば、人間にとってはそれほど気にならない程度に調整できますよ。
臭いを使ったアライグマ対策、まるで魔法使いの秘薬のようですね。
アライグマに「ここは居心地が悪いよ」と臭いでアピール。
そんな穏やかな方法で、アライグマとの距離を保ってみてはいかがでしょうか。
家族の安全と快適な暮らしのために、ちょっとした工夫を重ねていきましょう。
電気柵でガード!庭や畑を守る最終手段
アライグマ対策の最終手段として、電気柵の設置があります。特に庭や畑を守るのに効果的です。
「えっ、電気柵?ちょっと大げさじゃない?」と思う方もいるでしょう。
でも、アライグマの被害が深刻な場合、これが最も確実な方法なんです。
電気柵のメリットは、以下の通りです。
- 高い抑止力:アライグマが一度触れると、二度と近づかなくなる
- 広範囲の保護:庭全体や畑を囲むことができる
- 長期的な効果:一度設置すれば、長期間効果が持続
- 他の動物対策にも:アライグマ以外の野生動物も寄せ付けない
- 電圧の調整:人やペットに危険がないよう、適切な電圧に設定
- 設置場所の選択:子供が触れない高さや場所に設置
- 定期的な点検:故障や漏電がないか、こまめにチェック
- 近隣への配慮:設置前に近所の方に説明し、理解を得る
- 法律の確認:地域によっては設置に規制がある場合も
確かに専門的な知識が必要ですが、最近は家庭用の簡易タイプも販売されています。
取り付けも比較的簡単で、自分で設置できるものもありますよ。
電気柵の代わりに、高さ1.5メートル以上のしっかりした金網フェンスを設置するのも効果的です。
アライグマは器用に登るので、上部を内側に折り曲げるとさらに効果が上がります。
電気柵やフェンスの設置は、ちょっと大がかりな対策に感じるかもしれません。
でも、アライグマの被害に悩まされ続けるよりは、一度しっかり対策を取った方が長期的には楽になりますよ。
「うちの庭は、アライグマお断り!」そんな強い意志を示す電気柵。
アライグマとの境界線をはっきり引いて、快適な生活を取り戻しましょう。
家族の安全と大切な庭を守るために、思い切った対策を検討してみてはいかがでしょうか。
餌場撲滅作戦!ゴミ箱や果樹の管理方法
アライグマ対策の基本中の基本、それが餌場の撲滅です。特にゴミ箱や果樹の管理が重要になります。
「え?ゴミ箱や果樹が関係あるの?」と思う方もいるでしょう。
実は、これらはアライグマにとって格好の食事処なんです。
アライグマが寄ってくる原因を断つことが、最も効果的な対策なんですよ。
では、具体的な管理方法を見ていきましょう。
- ゴミ箱の管理
- 頑丈な蓋付きのゴミ箱を使用する
- ゴミ出しは収集日の朝に行う
- 生ゴミは新聞紙で包んでから捨てる
- ゴミ箱の周りを清潔に保つ
- 果樹の管理
- 熟した果物はすぐに収穫する
- 落果はこまめに拾い集める
- ネットや金網で果樹を覆う
- 果樹の周りに忌避剤を撒く
ただし、注意点もあります。
例えば、ゴミ箱を縛りつけたり重しを乗せたりしても、器用なアライグマなら開けてしまうことがあります。
また、果樹のネットも、隙間があればアライグマは侵入してしまいます。
「でも、そんなに完璧にやるの大変そう...」と思う方もいるでしょう。
確かに手間はかかりますが、アライグマ被害を防ぐためには非常に効果的な方法なんです。
こんな工夫もおすすめです。
- ゴミ箱を倉庫や車庫の中に置く
- コンポストを使う場合は、蓋付きの密閉型を選ぶ
- ペットのエサは屋内で与え、食べ残しはすぐに片付ける
- バードフィーダーは夜間は室内に取り込む
- 果樹の剪定を適切に行い、アライグマが登りにくくする
少し面倒に感じるかもしれませんが、これらの対策を続けることで、アライグマの訪問を徐々に減らすことができます。
「うちの庭は、アライグマにとって美味しくない場所」そんな評判を広めて、アライグマとの平和な共存を目指しましょう。
家族の安全と快適な生活のために、日々の小さな努力を重ねていくことが大切です。
餌場撲滅作戦、みんなで協力して頑張りましょう!