アライグマが好む環境とは?【水辺から100m以内】生息地の特徴を知って被害を未然に防ぐ方法

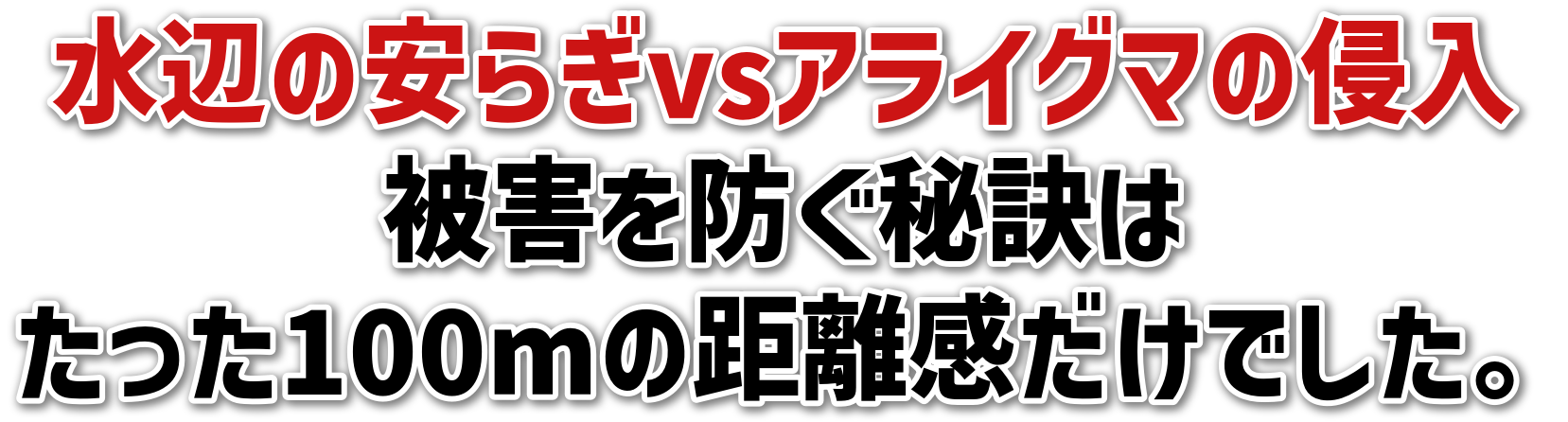
【この記事に書かれてあること】
アライグマが水辺を好む理由、知っていますか?- アライグマは水辺から100m以内の環境を好む
- 水辺環境は食料と隠れ場所を提供する
- 都市部でも人工的な水場に誘引される
- アライグマの行動パターンを理解することが対策の鍵
- 環境操作によるアライグマ対策が効果的
実は、水辺から100メートル以内の環境が彼らにとって理想的な生息地なんです。
「えっ、うちの近くに川があるけど大丈夫?」なんて心配になりますよね。
でも安心してください。
アライグマの生態を理解すれば、効果的な対策が立てられるんです。
この記事では、アライグマが好む環境の秘密を解き明かし、その特徴を逆手に取った5つの対策法をご紹介します。
「アライグマよ、さようなら!」と言える日も、そう遠くありませんよ。
【もくじ】
アライグマが好む環境の特徴とは?水辺との関係に注目

水辺から100m以内が「最適な生息地」になる理由
アライグマにとって、水辺から100m以内の環境は理想的な生息地なんです。なぜでしょうか?
それは、この範囲内に彼らの生存に必要な全てが揃っているからです。
まず、水辺は飲み水の確保に欠かせません。
「喉が渇いたな〜」と思ったときにすぐに水が飲めるのは、アライグマにとって大きな魅力です。
でも、それだけじゃありません。
水辺には豊富な食料も集まります。
魚やカエル、水生昆虫など、アライグマの大好物がたくさん!
「今日の晩ごはんは何にしようかな〜」と、毎日豪華な食事を楽しめるんです。
さらに、水辺周辺には木々や茂みが生い茂っていることが多く、これらは絶好の隠れ家になります。
「危険が迫ってきた!」というときにさっと身を隠せる場所があるのは、アライグマの安全を守る上で重要なポイントなんです。
- 飲み水の確保が容易
- 豊富な食料源(魚、カエル、水生昆虫など)
- 隠れ家となる木々や茂みの存在
- 繁殖に適した環境(水辺の樹洞など)
- 移動経路としての水路の利用
だからこそ、彼らはこの範囲に執着し、繰り返し出没するようになるというわけです。
アライグマが水辺を好む「3つの本能的欲求」とは
アライグマが水辺を好むのは、彼らの持つ3つの本能的欲求が深く関わっているんです。これらの欲求を理解すると、なぜアライグマが水辺に執着するのかがよくわかります。
1つ目は「食欲」です。
アライグマは雑食性で、水辺には彼らの大好物がたくさん!
「今日は魚にしようかな、それともカエルにしようかな」なんて、まるでバイキング料理を楽しむかのように、多様な食材を手に入れられるんです。
2つ目は「安全欲求」。
水辺の環境は、彼らにとって最高の隠れ家になります。
「危険が迫ってきた!」というときに、さっと水に飛び込んだり、茂みに身を隠したりできるので、安心感があるんです。
3つ目は「清潔欲求」。
意外かもしれませんが、アライグマはとてもきれい好き。
「手を洗わなきゃ」と、食事の前後に必ず水辺で手を洗う習性があるんです。
- 食欲:多様な食材が豊富に存在
- 安全欲求:危険から身を守る隠れ家
- 清潔欲求:手を洗う習性を満たせる
「食べて、隠れて、きれいになれる」という、アライグマにとっての理想的な環境が水辺なんです。
だからこそ、彼らは水辺から離れられないんですね。
この本能的な欲求を理解することで、アライグマの行動パターンを予測し、効果的な対策を立てることができるんです。
水辺以外でも「人工的な水場」に誘引される!
アライグマは自然の水辺だけでなく、人工的な水場にもグイグイ引き寄せられちゃうんです。これが都市部でアライグマが増える大きな理由の一つなんです。
例えば、庭の噴水や池。
「わーい、プライベートプール見つけた!」なんて、アライグマは大喜び。
人間が景観のために作った水場が、彼らにとっては格好の遊び場になっちゃうんです。
また、ペットの水飲み場も要注意。
「いただきま〜す」と、アライグマは遠慮なく飲んじゃいます。
これは衛生面でも問題があるので気をつけましょう。
さらに、意外なところでは雨どいや排水溝。
「ここなら安全に水が飲めるぞ」と、アライグマは考えるんです。
特に、雨上がりの後は要注意です。
- 庭の噴水や池:遊び場兼飲み場に
- ペットの水飲み場:簡単に水が手に入る
- 雨どいや排水溝:安全に水が飲める場所
- スプリンクラー:水遊びの絶好の機会
- バードバス:小鳥の水浴び場が飲み場に
「え?こんなところにまで?」と驚くかもしれませんが、アライグマにとっては全て貴重な水源なんです。
だからこそ、自然の水辺から離れた都市部でも、アライグマが増えてしまうんです。
この習性を理解して、不要な水場を減らすことが、アライグマ対策の第一歩になるというわけです。
水辺環境と「食料の豊富さ」の密接な関係性
水辺環境とアライグマの食料は、切っても切れない関係なんです。「水辺=食べ放題ビュッフェ」と考えると、わかりやすいでしょう。
まず、水辺には魚やカエルがたくさん!
「今日の晩ごはんはお魚にしよう」なんて、アライグマは毎日新鮮な食材を手に入れられるんです。
特に、浅い水辺は彼らにとって絶好の漁場。
手先が器用なアライグマは、まるでプロの釣り師のように魚を捕まえちゃいます。
また、水辺周辺には昆虫もいっぱい。
「甘くておいしそう〜」と、アライグマは虫たちも見逃しません。
特に、水生昆虫は栄養価が高くて大好物なんです。
さらに、水辺の植物も重要な食料源。
「今日のサラダはこれにしよう」なんて、水草や水辺に生える果実を食べることもあります。
- 魚類:主要なタンパク源
- 両生類:カエルやサンショウウオが好物
- 水生昆虫:栄養価の高いおやつ
- 水辺の植物:果実や葉を食べる
- 小動物:水を飲みに来る小動物も狙う
「食べ物がたくさんあるところに住もう」というのは、動物として当然の選択ですよね。
だからこそ、水辺環境を管理することが、アライグマの食料源を断つ重要な対策になるんです。
例えば、池の周りを整備したり、果実の落下を防いだりするだけでも、アライグマを寄せ付けにくくなるんですよ。
水辺近くの家屋は要注意!「侵入リスク」が高まる
水辺の近くに建つ家屋は、アライグマにとって格好のねぐらになっちゃうんです。「水も食べ物も近いし、ここに住もう!」なんて、アライグマは考えるんです。
まず、屋根裏や軒下が狙われやすいんです。
「ここなら雨風しのげるぞ」と、アライグマは人間の家を自分の城のように使っちゃいます。
特に、古い家屋や手入れが行き届いていない建物は要注意。
小さな隙間からスルスルと侵入してきちゃうんです。
また、デッキや縁側も侵入口になりやすいんです。
「ここから家の中に入れそう」なんて、アライグマは探検心をくすぐられちゃうんです。
特に、夜になると活発に活動するので、寝静まった家を狙ってくることも。
さらに、庭に置いてある物置やガレージも侵入されやすいんです。
「ここなら人目につかないぞ」と、繁殖の場所として使われることもあるんです。
- 屋根裏・軒下:雨風をしのげる安全な場所
- デッキ・縁側:家屋内部への足がかり
- 物置・ガレージ:隠れ家や繁殖場所に
- 基礎部分の隙間:地下からの侵入口に
- 換気口・煙突:思わぬ侵入経路に
「え?うちの家がホテル?」なんて思うかもしれませんが、アライグマにとってはそうなんです。
だからこそ、水辺近くの家屋は特に注意が必要。
建物の点検や補修を定期的に行い、侵入できそうな場所をふさぐことが大切です。
アライグマに「ここは住めないな」と思わせることが、効果的な対策になるというわけです。
アライグマを引き寄せる環境要因と対策法

自然環境vs都市環境「アライグマの選好性」を比較
アライグマは、本来自然環境を好みますが、都市環境にも驚くほど適応力を発揮します。まるで「どっちも大好き!」と言わんばかりの姿勢なんです。
自然環境では、アライグマは本来の姿を存分に発揮します。
「今日はどの木に登ろうかな」なんて、木登りを楽しんだり、「川でエビでも取ろうかな」と水辺で食事を探したり。
自然の中では、彼らの野生の本能がフル活動するんです。
一方、都市環境。
ここでアライグマは驚くべき適応力を見せます。
「人間様の残したごちそう、いただきます!」なんて、ゴミ箱をあさったり、「この屋根裏、なかなかいい部屋じゃん」と家屋に侵入したり。
人間社会のすきまを縫って生活しているんです。
- 自然環境での特徴:
- 多様な食料源(果実、小動物など)
- 豊富な隠れ場所(樹洞、茂みなど)
- 人間との接触が少ない
- 都市環境での特徴:
- 人工的な食料源(ゴミ、ペットフードなど)
- 人工的な隠れ場所(屋根裏、物置など)
- 人間との接触が多い
「こっちの環境がダメなら、あっちで暮らせばいいじゃん」という柔軟な発想で、どんな場所でも生き抜く術を身につけているんです。
でも、これが私たち人間にとっては頭の痛い問題。
「どこにでもいる!」という状況は、アライグマ被害の拡大につながっちゃうんです。
だからこそ、自然環境と都市環境、両方での対策が必要になるというわけです。
食料の豊富さvs隠れ場所「アライグマの優先順位」
アライグマにとって、食料と隠れ場所はどっちが大事?実は、この二つは「おいしい食事」と「安全な寝床」のように、どちらも欠かせない要素なんです。
まず、食料の豊富さ。
アライグマにとって、「お腹いっぱい食べられる場所」は天国同然です。
「今日は果物、明日は魚、明後日は昆虫かな」なんて、バラエティ豊かな食事を楽しめる環境を彼らは大好きなんです。
一方、隠れ場所の存在。
「危険が迫ってきた!」というときに、さっと身を隠せる場所があるのは、アライグマの安全を守る上で超重要なポイントです。
では、どっちを優先するの?
実は、状況によって変わるんです。
- 食料優先の場合:
- 子育て中で栄養が必要なとき
- 冬に向けて体重を増やしたいとき
- 新しい環境に来たばかりのとき
- 隠れ場所優先の場合:
- 天敵が多い地域にいるとき
- 人間との接触が多い都市部にいるとき
- 出産や子育ての時期が近いとき
「今日はお腹が空いてるから、ちょっと危険でも食べ物がある場所に行こう」とか、「最近人間をよく見かけるから、安全な隠れ家を探そう」とか。
この賢い判断力が、アライグマの生存戦略なんです。
でも、これが私たち人間にとっては厄介な問題。
食料も隠れ場所も与えないように気をつけないと、アライグマにとっての「理想郷」を作ってしまうことになるんです。
だから、両方の要素を考慮した総合的な対策が必要になるというわけですね。
人間活動との距離「警戒心vs適応力」の関係
アライグマと人間の関係って、まるで「いい距離感」を探る恋人同士みたい。警戒しながらも、どんどん近づいてくるんです。
アライグマの警戒心は、本来かなり強いんです。
「人間が来た!逃げろー!」なんて、昔は人間を見るだけで一目散に逃げ出していました。
でも、そんなアライグマが今や都市部にも進出してきているんです。
これって、いったいどういうこと?
実は、アライグマの適応力がすごいんです。
「人間がいても、おいしいものがあるなら行っちゃおうかな」なんて、徐々に人間への警戒心を緩めていくんです。
特に、都市部で生まれ育ったアライグマは、人間の存在を当たり前のものとして受け入れちゃっているんです。
この警戒心と適応力のバランス、実は場所や状況によってコロコロ変わるんです。
- 警戒心が強くなる状況:
- 突然の大きな音や動き
- 直接的な人間との接触
- 新しい環境に入ったとき
- 適応力が発揮される状況:
- 食べ物が豊富にある場所
- 安全な隠れ場所がある環境
- 人間の活動パターンに慣れたとき
最初は警戒心満々だったアライグマも、「あれ?人間って怖くないかも」と徐々に適応していくんです。
これが私たち人間にとっては、やっかいな問題になっちゃうんです。
「最初は寄ってこなかったのに、最近庭に来るようになった」なんて経験、ありませんか?
だからこそ、アライグマ対策は継続的に行う必要があるんです。
一時的な対策だけじゃなく、「人間の近くは危険だぞ」というメッセージを常に発信し続けることが大切。
そうすることで、アライグマの警戒心を維持させ、人間との適切な距離を保つことができるんです。
夜行性と人間活動の時間帯「活動時間のズレ」に注目
アライグマと人間の生活リズム、まるで昼と夜のように正反対なんです。このズレが、アライグマ対策のカギを握っているんですよ。
アライグマは夜行性。
「みんな寝静まった?よーし、活動開始!」なんて、日が沈むとソワソワし始めます。
一方、私たち人間はどうでしょう?
「おやすみなさーい」と、ちょうどその時間帯にベッドに向かいますよね。
この生活リズムのズレ、アライグマにとっては都合が良いんです。
「人間がいないうちに、ゴミ箱あさりに行こうっと」「静かな夜中に、屋根裏探検しちゃおう」なんて考えているんです。
では、具体的にどんなズレがあるのか、見てみましょう。
- 人間の活動時間帯:
- 朝:6時頃から活動開始
- 日中:仕事や学校で外出
- 夕方:帰宅し、家事や食事
- 夜:22時頃から就寝準備
- アライグマの活動時間帯:
- 夕方:19時頃から活動開始
- 深夜:最も活発に行動
- 明け方:4時頃まで活動
- 日中:休息・睡眠
「人間がいない時間を狙ってくるんだな」と理解すれば、その時間帯に焦点を当てた対策が立てられます。
例えば、「夜間にセンサーライトを設置する」「深夜でも作動する騒音装置を用意する」なんて方法があります。
これらは、人間の生活には影響を与えずに、アライグマの活動を邪魔することができるんです。
また、「朝一番に庭をチェックする習慣をつける」のも良いでしょう。
アライグマの痕跡をいち早く見つけることで、被害を最小限に抑えられるんです。
このように、活動時間のズレを理解し、それを利用した対策を講じることが、効果的なアライグマ対策につながるんです。
「夜の隙を与えない」。
それが、アライグマとの上手な付き合い方なんですね。
季節による行動変化「繁殖期vs越冬準備期」の違い
アライグマの行動、実は季節によってガラッと変わるんです。まるで「春は恋する乙女、秋は倹約家」のような、極端な変化を見せるんですよ。
春から夏にかけては、アライグマの繁殖期。
「素敵な相手を見つけなくちゃ」「子育ての準備をしなきゃ」と、彼らの活動が活発になります。
一方、秋から冬にかけては越冬準備期。
「冬を乗り越えるために、たくさん食べなきゃ」と、食べ物探しに必死になるんです。
この季節による行動変化、アライグマ対策にとって重要なポイントなんです。
どんな違いがあるのか、詳しく見てみましょう。
- 繁殖期(春〜夏)の特徴:
- 行動範囲が広がる
- 食事量が増える(特に栄養価の高い食べ物を狙う)
- 安全な巣作りの場所を探す
- 夜間の鳴き声が増える
- 越冬準備期(秋〜冬)の特徴:
- 食事量が更に増える(脂肪を蓄積するため)
- 暖かい隠れ場所を探す
- 活動時間が若干短くなる
- 群れでの行動が増える
例えば、繁殖期には「家屋の点検を徹底する」のが効果的。
屋根裏や物置など、巣作りに適した場所をしっかりチェックし、侵入を防ぐんです。
「ここは赤ちゃんを育てる場所には向かないな」と思わせることが大切です。
一方、越冬準備期には「食べ物の管理を徹底する」のがポイント。
ゴミの保管方法を見直したり、落ち葉や熟した果実を早めに片付けたりするんです。
「この庭では冬を越せそうにないな」と思わせることが効果的なんです。
このように、アライグマの季節による行動変化を理解し、それに合わせた対策を講じることで、年間を通じて効果的なアライグマ対策が可能になるんです。
「春夏秋冬、それぞれの季節にあった対策を」。
それが、アライグマとの賢い付き合い方なんですね。
アライグマ対策!好む環境を逆手に取る5つの方法

水辺から100m以内の範囲に「反射板設置」で威嚇
アライグマの大好きな水辺エリアを、光で守る作戦です。反射板を使って、アライグマを驚かせちゃいましょう!
アライグマは夜行性。
暗闇で活動するのが得意なんです。
でも、突然の光には弱いんです。
「うわっ、まぶしい!」って感じで、びっくりしちゃうんですね。
そこで登場するのが反射板。
これを水辺から100メートル以内の範囲に設置します。
「どこに置けばいいの?」って思いますよね。
木の枝や柵、建物の壁など、アライグマの通り道になりそうな場所がおすすめです。
反射板の効果を最大限に引き出すコツは、動きをつけること。
風で揺れる仕掛けを作ったり、回転する台に乗せたりすると、光の反射がより不規則になります。
「キラキラ、ピカピカ」とランダムに光が動くので、アライグマはますます警戒しちゃうんです。
- 反射板の設置場所:
- 木の枝(アライグマの通り道)
- 柵や塀の上(侵入経路)
- 建物の壁(家屋への接近を防ぐ)
- 効果を高める工夫:
- 風で揺れる仕掛けを作る
- 回転する台に乗せる
- 複数の反射板を組み合わせる
自然の光を利用するので、電気代もかからないし、環境にも優しいんです。
「エコでお財布にも優しい」なんて、一石二鳥ですよね。
ただし、反射板だけに頼りすぎないでくださいね。
アライグマは賢いので、慣れてしまう可能性もあります。
他の対策と組み合わせて使うのがおすすめです。
そうすれば、「この場所は危険だぞ」とアライグマに強く印象づけられるんです。
庭に「唐辛子スプレー」散布!嗅覚を刺激して撃退
アライグマの鋭い嗅覚を逆手に取る作戦です。唐辛子スプレーで、アライグマに「ここは危険だぞ」とメッセージを送りましょう!
アライグマって、鼻がとっても敏感なんです。
「おいしそうな匂いがする!」って遠くからでも感じ取れる反面、刺激的な匂いには敏感なんですね。
特に、辛い匂いは大の苦手。
そこで活躍するのが、唐辛子スプレーです。
「えっ、料理用の唐辛子でいいの?」なんて思うかもしれませんが、実はちょっと違うんです。
アライグマ対策用の特殊な唐辛子スプレーを使うんですよ。
このスプレーを庭のあちこちに散布します。
特に、アライグマが侵入しそうな場所を重点的に。
例えば、塀の周り、庭木の根元、家の周囲なんかがおすすめです。
「シュッシュッ」と散布するだけで、アライグマにとっては「立入禁止ゾーン」の出来上がりです。
- 唐辛子スプレーの散布場所:
- 塀や柵の周辺(侵入経路を遮断)
- 庭木の根元(隠れ場所を封じる)
- 家の周囲(接近を防ぐ)
- ゴミ置き場(食料源へのアクセスを阻止)
- 効果を持続させるコツ:
- 定期的に再散布する(雨で流れるため)
- 濃度を徐々に上げる(慣れを防ぐ)
- 他の香りと組み合わせる(単調さを避ける)
でも、アライグマにとっては強力な「立ち入り禁止サイン」になるんです。
「人にも環境にも優しい」なんて、素敵じゃないですか?
ただし、雨が降ると効果が薄れちゃうので、定期的な再散布が必要です。
「面倒くさいなぁ」って思うかもしれませんが、それだけアライグマ対策に効果があるってことなんです。
根気強く続けることで、アライグマに「この場所は居心地が悪い」と覚えてもらうんです。
そうすれば、だんだん寄ってこなくなりますよ。
家屋周辺に「動物の尿の臭い」でなわばり侵入を防止
アライグマの縄張り意識を刺激して、侵入を防ぐ作戦です。動物の尿の臭いを利用して、「ここは他の動物の縄張りだぞ」とアライグマに思わせちゃいましょう!
アライグマって、縄張り意識が強いんです。
「ここは俺の場所だ!」って感じで、自分の縄張りには他のアライグマを寄せ付けません。
でも、逆に言えば、他の動物の縄張りには入りたがらないんです。
そこで活躍するのが、動物の尿の臭いがするスプレーです。
「えっ、本物の尿を使うの?」なんて心配しなくても大丈夫。
化学的に合成された、安全な製品があるんです。
このスプレーを家屋の周りに吹きかけます。
特に、アライグマが侵入しそうな場所を重点的に。
例えば、庭の入り口、家の周囲、ゴミ置き場なんかがおすすめです。
「シュッシュッ」と散布するだけで、アライグマにとっては「他の動物の縄張り」になっちゃうんです。
- 尿の臭いスプレーの散布場所:
- 庭の入り口(侵入を初期段階で防ぐ)
- 家の周囲(建物への接近を阻止)
- ゴミ置き場(食料源へのアクセスを遮断)
- 花壇や菜園の周り(作物を守る)
- 効果を高めるコツ:
- 定期的に場所を変えて散布(慣れを防ぐ)
- 雨後は必ず再散布(雨で流れるため)
- 複数の動物の臭いを組み合わせる(より自然な状況を演出)
薬品で害を与えるわけじゃないので、環境にも優しいんです。
「自然の法則を味方につける」なんて、なんだかかっこいいですよね。
ただし、人間にも臭いが分かるので、散布する場所には注意が必要です。
家の中や人がよく通る場所は避けた方がいいでしょう。
また、雨で流れちゃうので、定期的な再散布も忘れずに。
「ちょっと手間はかかるけど、効果は抜群」。
そんな感じの対策方法なんです。
庭に「風車」設置!動きと音でアライグマを寄せ付けない
アライグマの警戒心を刺激する、動きと音の作戦です。庭に風車を設置して、アライグマに「ここは危険だぞ」とメッセージを送りましょう!
アライグマって、意外と臆病なんです。
特に、予測できない動きや音には敏感。
「何だか怖そう...」って感じで、近づきたがらないんですね。
そこで活躍するのが風車。
ただの装飾品じゃありません。
アライグマ対策の強い味方なんです。
風で回る羽根が作る不規則な動きと、「カラカラ」という音。
これがアライグマにとっては大きな脅威になるんです。
風車は庭のあちこちに設置します。
特に、アライグマが侵入しそうな場所を重点的に。
例えば、塀の上、庭の入り口、家の周囲なんかがおすすめです。
「クルクル、カラカラ」と風車が回るたびに、アライグマは「ここは危険だぞ」と感じるんです。
- 風車の効果的な設置場所:
- 塀や柵の上(侵入経路を遮断)
- 庭の入り口(初期段階で侵入を防ぐ)
- 家の周囲(建物への接近を阻止)
- 菜園や果樹の近く(作物を守る)
- 効果を高めるコツ:
- 大小様々な風車を組み合わせる(変化をつける)
- 反射板付きの風車を選ぶ(光の効果も)
- 定期的に位置を変える(慣れを防ぐ)
「アライグマ対策しながら、庭も素敵に」なんて、一石二鳥ですよね。
しかも、電気を使わないので環境にも優しい。
風の力だけで働いてくれるんです。
ただし、風がない日は効果が薄れちゃうので、他の対策と組み合わせるのがおすすめです。
「風車だけじゃなく、反射板や音も一緒に」なんて感じで。
そうすれば、天気に関係なく、常にアライグマを寄せ付けない環境が作れるんです。
「自然の力を借りて、アライグマとの知恵比べ」。
そんな感じで対策を楽しんでみてはいかがでしょうか。
「強い香りのハーブ」を植えてアライグマを遠ざける
アライグマの鋭い嗅覚を利用して、庭を守る作戦です。強い香りのハーブを植えて、アライグマに「ここは居心地が悪いぞ」と感じさせちゃいましょう!
アライグマって、匂いに敏感なんです。
おいしそうな匂いには寄ってくる反面、強烈な香りは苦手。
「くんくん...うわ、この匂いはダメだ!」って感じで避けちゃうんです。
そこで活躍するのが、強い香りのハーブ。
ただの調理用ハーブじゃありません。
アライグマ撃退の頼もしい味方なんです。
ミント、ローズマリー、タイムなど、香りの強いハーブを庭に植えると、アライグマにとっては「立ち入り禁止ゾーン」の出来上がりです。
ハーブは庭のあちこちに植えます。
特に、アライグマが侵入しそうな場所を重点的に。
例えば、塀の周り、家の周囲、菜園の近くなんかがおすすめです。
「ふわっ」と漂う強い香りが、アライグマを遠ざけてくれるんです。
- 効果的なハーブの種類:
- ペパーミント(清涼感のある強い香り)
- ローズマリー(爽やかな木の香り)
- タイム(独特の芳香)
- ラベンダー(リラックス効果のある香り)
- ハーブの植え方のコツ:
- 境界線に沿って列状に植える
- 風下に植えて香りを広げる
- 定期的に剪定して香りを強く保つ
「アライグマ対策しながら、庭も素敵に、そして香り豊かに」なんて、一石三鳥ですよね。
しかも、ハーブは料理にも使えるので、実用的。
自然の力を借りて、アライグマを寄せ付けない環境が作れるんです。
ただし、ハーブだけに頼りすぎるのは禁物。
アライグマは賢いので、慣れてしまう可能性もあります。
他の対策と組み合わせて使うのがおすすめです。
例えば、「ハーブを植えつつ、風車も設置」なんて感じで。
そうすれば、視覚、聴覚、嗅覚と、複数の感覚に訴えかけられるんです。
「自然の香りで、アライグマとの知恵比べ」。
そんな感じで、ハーブを使った対策を楽しんでみてはいかがでしょうか。
庭の景観も良くなり、アライグマ対策も進む。
まさに一石二鳥の対策方法なんです。