アライグマの巣はどこにある?【屋根裏が最多】自然環境と人工物の利用率から効果的な対策を考える

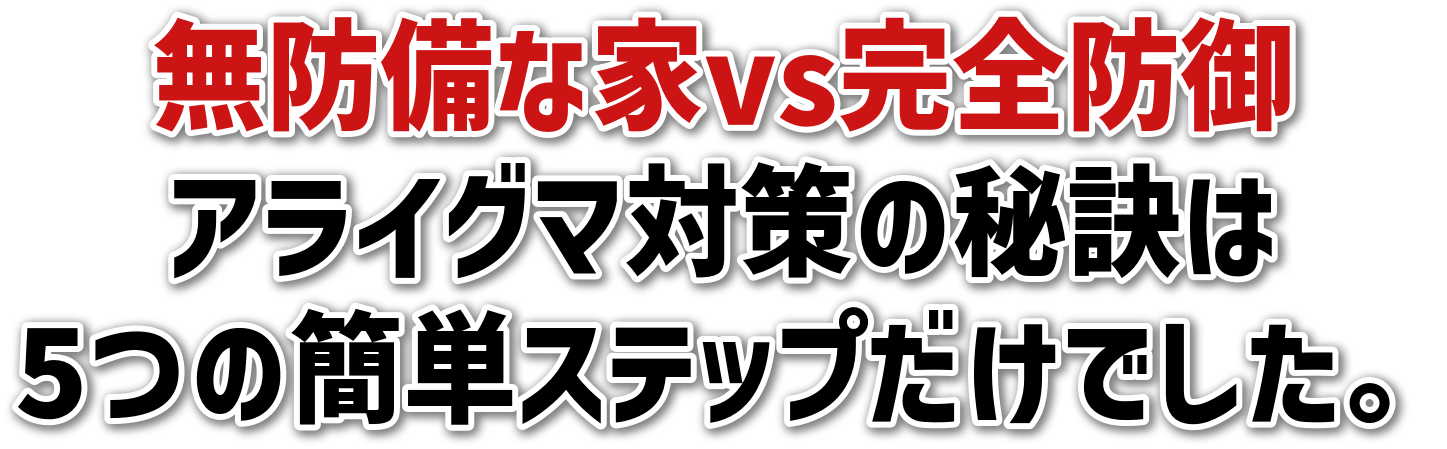
【この記事に書かれてあること】
アライグマの巣、一体どこにあるのでしょうか?- アライグマは暗く乾燥した場所を好んで巣を作る
- 巣の70%以上が人工物で、屋根裏が最多
- 巣の入り口は直径10cm程度あれば侵入可能
- 季節によって巣の場所を変える習性がある
- 効果的な対策にはアンモニア臭や超音波の利用がある
実は、その答えがあなたの家のすぐそばかもしれません。
アライグマは意外にも人間の生活圏内に巣を作る傾向があり、屋根裏が最も人気の場所なんです。
「えっ、うちの屋根裏に?」と驚く方も多いはず。
でも、安心してください。
この記事では、アライグマの巣の特徴や場所、そして効果的な対策方法まで詳しく解説します。
アライグマとの「お隣さん生活」を上手に回避する方法、一緒に学んでいきましょう!
【もくじ】
アライグマの巣はどこにある?屋根裏が最多の理由

アライグマが好む巣の特徴「暗く乾燥した場所」に注目!
アライグマが好む巣の特徴は、暗くて乾燥した場所です。これらの条件を満たす場所を見つけると、アライグマはそこを巣として利用しようとします。
アライグマにとって理想的な巣は、次のような特徴を持っています。
- 人目につきにくい隠れた場所
- 雨や風を避けられる乾燥した環境
- 外敵から身を守れる安全な空間
- 温度変化が少ない安定した場所
実は、これらの特徴は野生動物としてのアライグマの本能に深く根ざしているんです。
暗い場所を好むのは、夜行性であるアライグマの習性によるものです。
日中は安全に休息できる場所が必要なんですね。
また、乾燥した場所を選ぶのは、湿気が多いと病気にかかりやすくなるからです。
さらに、人目につきにくい場所を選ぶのは、捕食者から身を守るためです。
アライグマにとって、安全に休息し、子育てができる環境が最も重要なんです。
例えば、森の中の樹洞を思い浮かべてみてください。
暗くて乾燥していて、外からは見えにくい。
まさにアライグマにとっての理想的な巣の条件を満たしているんです。
このようなアライグマの好みを理解することで、家屋への侵入を防ぐヒントが見えてきます。
家の中に暗くて乾燥した場所がないか、チェックしてみるのが効果的です。
そんな場所を見つけたら、明るくしたり、風通しを良くしたりすることで、アライグマを寄せ付けない環境づくりができるんです。
巣のサイズは意外と小さい!成獣1匹で約0.5平方メートル
アライグマの巣のサイズは、意外にも小さいんです。成獣1匹あたり、約0.5平方メートルのスペースがあれば十分なんです。
これは畳半分くらいの広さですね。
「えっ、そんな狭いところで暮らせるの?」と驚く方も多いでしょう。
でも、アライグマにとっては十分な広さなんです。
この小ささが、実は家屋への侵入を容易にしているんです。
アライグマの巣のサイズについて、もう少し詳しく見ていきましょう。
- 成獣1匹:約0.5平方メートル
- 母親と子供2〜3匹:約1〜1.5平方メートル
- 複数の成獣:1匹につき約0.5平方メートルずつ追加
小さな隙間さえあれば、そこを巣にしてしまうんですね。
例えば、屋根裏の小さな空間。
人間には狭すぎて使い道がないと思えるような場所でも、アライグマにはぴったりの巣になってしまうんです。
「ガサガサ…ゴソゴソ…」夜中に屋根裏から聞こえてくる不気味な音。
実はこれ、0.5平方メートルほどの小さな空間で、アライグマが快適に暮らしている証拠かもしれません。
この小ささを理解することで、家の中のどんな場所がアライグマの巣になりうるか、予測できるようになります。
壁の中、床下、物置の隅…。
小さな空間を見つけたら、そこがアライグマの潜在的な巣になる可能性があるんです。
こんな小さな空間でも巣になってしまうんだ、という認識を持つことが、効果的な対策の第一歩になります。
家の中の小さな隙間や空間を見つけたら、すぐにふさいでしまうのが賢明です。
そうすることで、アライグマの侵入を未然に防ぐことができるんです。
侵入口は直径10センチの穴があれば十分「要注意」
アライグマの侵入口、実はとても小さいんです。直径わずか10センチの穴があれば、大人のアライグマでも難なく通り抜けられてしまいます。
これは、ソフトボールくらいの大きさです。
「えっ、そんな小さな穴から入れるの?」と驚く声が聞こえてきそうです。
でも、これがアライグマの恐ろしいところなんです。
この小ささが、家屋への侵入を非常に容易にしているんです。
アライグマの侵入口について、もう少し詳しく見ていきましょう。
- 最小サイズ:直径約10センチ
- 好みのサイズ:直径15〜20センチ
- 形状:円形、楕円形、四角形など様々
- 場所:屋根、壁、床下、換気口など
彼らは鋭い視覚と触覚を使って、侵入可能な穴を探し出します。
例えば、屋根の軒下にある小さな隙間。
人間には気づかないような穴でも、アライグマには絶好の侵入口に見えてしまうんです。
「カリカリ…ガリガリ…」夜中に壁から聞こえてくる音。
これは、10センチほどの小さな穴を見つけたアライグマが、さらに穴を広げようとしている音かもしれません。
この小さな侵入口を理解することで、家のどんな場所がアライグマの侵入経路になりうるか、予測できるようになります。
屋根の隙間、壁のひび割れ、床下の穴…。
直径10センチ以上の穴や隙間を見つけたら、そこがアライグマの潜在的な侵入口になる可能性があるんです。
こんな小さな穴でも侵入口になってしまうんだ、という認識を持つことが、効果的な対策の第一歩になります。
家の外周を注意深く点検し、10センチ以上の穴や隙間を見つけたら、すぐにふさいでしまうのが賢明です。
金属板や金網を使って補強すれば、アライグマの侵入を未然に防ぐことができるんです。
屋根裏が最多!人工物を巣として利用する割合70%以上
アライグマの巣、実は人工物の中が大人気なんです。特に屋根裏が最多で、全体の70%以上が人工物を巣として利用しているんです。
これは驚くべき数字ですね。
「えっ、そんなに人工物が好きなの?」と思う方も多いでしょう。
でも、アライグマにとっては人工物の方が快適な暮らしができるんです。
この習性が、実は家屋被害の主な原因になっているんです。
アライグマが人工物を巣として利用する理由について、もう少し詳しく見ていきましょう。
- 屋根裏:温度が安定し、雨風をしのげる
- 物置や納屋:人目につきにくく、安全
- 床下:湿気が少なく、外敵から守られる
- 放置された車:密閉空間で安心感がある
- 煙突:縦に長い空間が好み
彼らにとっては、人間の住居こそが理想的な生活環境なんです。
例えば、閑静な住宅街の屋根裏。
人間にはただの空間でも、アライグマには温かくて安全な巣に見えるんです。
「カサカサ…ゴソゴソ…」夜中に屋根裏から聞こえてくる音。
これは、人工物を快適な巣として利用しているアライグマの生活音かもしれません。
この人工物好きの性質を理解することで、家のどんな場所がアライグマの巣になりやすいか、予測できるようになります。
屋根裏、物置、床下、車庫…。
これらの場所を定期的に点検し、アライグマの痕跡がないか確認することが大切です。
人工物が巣として利用されやすいんだ、という認識を持つことが、効果的な対策の第一歩になります。
家の周りの人工物を整理整頓し、アライグマが侵入しにくい環境を作ることが重要です。
例えば、物置はしっかり戸締まりをする、車庫は常に使用状態にしておく、といった対策が効果的です。
こうすることで、アライグマの侵入を未然に防ぎ、快適な生活を取り戻すことができるんです。
自然の巣vs人工物の巣「長期利用されるのはどっち?」
アライグマの巣選び、自然と人工物どちらが長持ちするのでしょうか?実は、人工物の巣の方が長期間利用される傾向にあるんです。
これは意外な事実かもしれません。
「えっ、自然の巣の方が長く使えそうなのに?」と思う方も多いでしょう。
でも、アライグマにとっては人工物の方が快適で安全なんです。
この習性が、実は家屋被害を長期化させる原因になっているんです。
自然の巣と人工物の巣の違いについて、もう少し詳しく見ていきましょう。
- 安定性:人工物の方が天候の影響を受けにくい
- 安全性:人工物の方が捕食者から身を守りやすい
- 快適性:人工物の方が温度や湿度が安定している
- 資源の豊富さ:人工物の周りの方が食べ物が豊富
- 子育ての成功率:人工物の方が高い傾向にある
彼らにとっては、一度居心地の良い巣を見つけたら、そこに長く住み続けたいという本能があるんです。
例えば、古い納屋の屋根裏。
人間には使い道のない空間でも、アライグマには世代を超えて利用できる理想的な巣に見えるんです。
「ギーギー…パタパタ…」毎年同じ時期に聞こえてくる音。
これは、同じ巣を代々利用しているアライグマ家族の生活音かもしれません。
この長期利用の傾向を理解することで、一度アライグマが侵入した場所は徹底的に対策する必要があることがわかります。
一時的な追い出しだけでは不十分で、再侵入を防ぐための恒久的な対策が必要なんです。
人工物の巣が長期利用されやすいんだ、という認識を持つことが、効果的な対策の第一歩になります。
一度アライグマが利用した場所は、単に穴をふさぐだけでなく、その周辺も含めて徹底的に対策することが重要です。
例えば、侵入経路を完全に封鎖し、さらに忌避剤を使用するなど、複合的なアプローチが効果的です。
こうすることで、アライグマの長期滞在を防ぎ、快適な生活環境を取り戻すことができるんです。
アライグマの巣作りパターンと季節変化を徹底解析

冬は保温重視!夏は風通し重視「季節で巣が変わる」
アライグマの巣は、季節によって大きく変化します。冬は体温を保つために暖かい場所を、夏は涼しさを求めて風通しの良い場所を選ぶんです。
「えっ、アライグマって季節で引っ越しするの?」と驚く方も多いでしょう。
実は、アライグマは季節の変化にとても敏感な動物なんです。
冬の巣作りの特徴を見てみましょう。
- 厚い壁や屋根のある建物の中を好む
- 日当たりの良い南向きの場所を選ぶ
- 他のアライグマと一緒に暮らして体温を保つ
- 巣材として布や紙、毛皮などの保温性の高いものを集める
- 木の上や開けた場所など、風通しの良い所を選ぶ
- 水辺に近い涼しい場所を好む
- 日陰になる北向きの場所を選ぶことも
- 巣材は最小限で、涼しさを重視
これは、寒さをしのぐためにアライグマたちが集まって暖を取っている証拠かもしれません。
逆に真夏、「カサカサ…」と木の上から聞こえる音。
これは涼を求めてやってきたアライグマかもしれませんね。
この季節による巣の変化を理解することで、アライグマ対策もより効果的になります。
冬は家の中の暖かい場所、夏は庭の木や開けた場所など、季節に応じて注意する場所を変えることが大切です。
例えば、冬に向かう前に屋根裏や壁の隙間をしっかりふさぐ。
夏前には庭の木の剪定を行い、アライグマが登りにくくするなど。
こうした対策で、季節を問わずアライグマを寄せ付けない環境づくりができるんです。
巣の移動頻度は2?3ヶ月に1回「新しい巣を探す習性」
アライグマは、平均して2〜3ヶ月に1回のペースで巣を移動します。この頻繁な引っ越し習性は、アライグマの生存戦略の一つなんです。
「えっ、そんなに頻繁に引っ越すの?」と驚く声が聞こえてきそうです。
でも、これがアライグマの賢い生き方なんです。
アライグマが巣を移動する理由には、いくつかあります。
- 天敵から身を守るため
- 食料が豊富な場所を探すため
- より快適な環境を求めて
- 繁殖期に適した場所を見つけるため
- 人間の活動を避けるため
「今日はここ、明日はあそこ」と、まるで遊牧民のような生活をしているんですね。
例えば、こんな感じです。
「カサカサ…ゴソゴソ…」今日まで屋根裏で聞こえていた音が、突然聞こえなくなった。
そして数日後、今度は物置から「ガサガサ…」と音が。
これは、アライグマが巣を移動した証拠かもしれません。
この習性を理解することで、アライグマ対策もより効果的になります。
一度アライグマを追い出しても油断は禁物。
すぐに別の場所に巣を作る可能性があるんです。
対策のポイントは、家全体を常にアライグマが入りにくい状態に保つこと。
例えば、
- 屋根や壁の小さな穴もすぐにふさぐ
- 物置や納屋の戸締まりを徹底する
- 庭の木の枝を家から離す
- 餌になりそうな物を外に放置しない
「引っ越してきても、すぐに出ていってもらう」。
そんな心構えで対策を続けることが大切です。
春と秋が要注意!新しい巣を探す行動が活発化
アライグマの巣探し、実は春と秋が特に活発になるんです。この時期、新しい巣を求めてあちこち探し回る姿が見られます。
「なぜ春と秋なの?」と思う方も多いでしょう。
実は、これにはアライグマの生態に深い理由があるんです。
春の巣探しの理由:
- 冬眠から目覚めて新しい環境を求める
- 繁殖期に向けて安全な巣を探す
- 子育てに適した場所を見つける
- 冬の間に壊れた巣の代わりを探す
- 冬を越すための暖かい巣を探す
- 秋の豊富な食料に近い場所に移動する
- 夏の間に人間に見つかった巣から逃げ出す
- 子どもたちが独立して新しい巣を探す
新居を探しに来たアライグマかもしれません。
この習性を理解することで、アライグマ対策もより的確になります。
春と秋には特に警戒レベルを上げる必要があるんです。
対策のポイントは、この時期に合わせて家の点検と対策を強化すること。
例えば:
- 春先と秋口に家の周りを徹底的に点検する
- 小さな穴や隙間も見逃さずにふさぐ
- 庭の整理整頓を行い、隠れ場所をなくす
- 物置や納屋の戸締まりを再確認する
- 餌になりそうな果物や野菜を放置しない
アライグマにとってもそんな感じなんです。
この時期に合わせて対策を強化することで、アライグマの新居探しを効果的に阻止できるんです。
子育て中の巣vs単独の巣「構造の違いに驚愕」
アライグマの巣、子育て中と単独生活では大きく構造が違うんです。この違いを知ることで、より効果的な対策が可能になります。
「えっ、巣にも種類があるの?」と驚く方も多いでしょう。
実は、アライグマは状況に応じて巣の作り方を変えるんです。
まずは、子育て中の巣の特徴を見てみましょう。
- 広さ:成獣1匹あたり0.5平方メートルの2〜3倍
- 構造:複数の部屋や出入り口がある
- 場所:地上に近い安全な場所を選ぶ
- 内装:柔らかい素材を敷き詰めて快適に
- 防御:入り口が狭く、外敵から守りやすい
- 広さ:成獣1匹あたり約0.5平方メートル
- 構造:シンプルで1つの空間のみ
- 場所:木の上や高所など、様々
- 内装:最小限の巣材で簡素
- 防御:逃げ道を確保しやすい場所を選ぶ
一方、単独の巣なら「カサッ」程度の軽い音でしょう。
この違いを理解することで、アライグマ対策もより的確になります。
特に子育て中の巣は長期間使用されるので、見つけたら早急に対処する必要があります。
対策のポイントは、巣の種類に応じたアプローチ。
例えば:
- 子育て中の巣を見つけたら、専門家に相談する
- 単独の巣なら、すぐに追い出し対策を行う
- 子育て中の巣がありそうな場所は重点的に点検
- 単独の巣は高所も含めて広範囲を確認
アライグマの巣作りもそんな感じなんです。
この違いを理解して対策を立てることで、より効果的にアライグマ問題に対処できるんです。
樹上の巣と地上の巣「アライグマの好みは年齢で変化」
アライグマの巣、実は年齢によって好みが変わるんです。若いアライグマは樹上の巣を、年老いたアライグマは地上の巣を好む傾向があります。
「えっ、年齢で巣の好みが変わるの?」と驚く方も多いでしょう。
でも、これにはアライグマなりの理由があるんです。
まずは、樹上の巣の特徴を見てみましょう。
- 高さ:地上から3〜20メートルの範囲
- 場所:枝分かれした部分や樹洞
- 利点:捕食者から身を守りやすい
- 欠点:天候の影響を受けやすい
- 好む年齢:若い成獣や子育て中のメス
- 場所:茂みの中、倒木の下、岩の隙間など
- 構造:地面を掘って作ることも
- 利点:安定していて快適
- 欠点:捕食者に見つかりやすい
- 好む年齢:年老いたアライグマや怪我をしたアライグマ
これは若いアライグマが樹上の巣で過ごしている証拠かもしれません。
一方、「ゴソゴソ…」と地面近くから聞こえる音は、年老いたアライグマの可能性が高いです。
この年齢による好みの違いを理解することで、アライグマ対策もより的確になります。
特に、複数の年齢層のアライグマが生息する地域では、両方のタイプの巣に注意を払う必要があるんです。
対策のポイントは、年齢層に応じたアプローチ。
例えば:
- 庭の木の剪定を定期的に行い、樹上の巣を作りにくくする
- 地面近くの茂みや倒木を整理し、地上の巣の隠れ場所をなくす
- 家の周りの木に登りにくくする対策を施す
- 地面と接する部分の隙間をしっかりふさぐ
アライグマの巣選びも、人間と似たようなものなんです。
この年齢による違いを理解して対策を立てることで、より効果的にアライグマ問題に対処できるんです。
アライグマの巣を見つけたらすぐ対策!5つの効果的な方法

巣の周辺にアンモニア臭の布を置く「意外な効果」
アンモニア臭は、アライグマを追い払う強力な武器になります。アライグマは鋭い嗅覚を持っているため、この強烈な臭いを嫌います。
「えっ、臭いだけでアライグマが逃げるの?」と思う方もいるでしょう。
でも、実はこれが意外と効果的なんです。
アンモニア臭を利用したアライグマ対策の方法を見てみましょう。
- 古いタオルや布にアンモニア溶液を染み込ませる
- 巣の周辺や侵入経路に布を置く
- 雨に濡れないよう、ビニール袋に入れて置く
- 2、3日おきに新しい布に交換する
確かに、取り扱いには注意が必要です。
使用する際は必ず手袋を着用し、直接触れないようにしましょう。
例えば、こんな使い方があります。
屋根裏にアライグマの気配を感じたら、アンモニア臭の布を梯子で上って置いてみるんです。
「プンプン」という強烈な臭いに、アライグマは「ここは危険だ!」と感じて、すぐに逃げ出すかもしれません。
この方法の良いところは、アライグマに直接危害を加えないことです。
単に嫌な場所だと思わせて立ち去らせるだけなんです。
ただし、注意点もあります。
人間にも強烈な臭いなので、家族や近所の人に迷惑をかけないよう配慮が必要です。
また、ペットがいる家庭では使用を控えましょう。
アンモニア臭を使った対策は、手軽で効果的。
でも、使いすぎには注意が必要です。
適度に使って、アライグマとの平和的な「お別れ」を目指しましょう。
屋外照明に動体センサーを取り付ける「突然の明るさに警戒」
動体センサー付きの照明は、アライグマ対策の強い味方になります。突然の明るさの変化に、アライグマは警戒心を抱くんです。
「えっ、ただの明かりでアライグマが逃げるの?」と思う方もいるでしょう。
でも、これが意外と効果的なんです。
動体センサー付き照明を使ったアライグマ対策の方法を見てみましょう。
- 家の周りの暗い場所に設置する
- アライグマの侵入経路に向けて光が当たるようにする
- センサーの感度を調整し、小動物でも反応するようにする
- LED電球を使用し、省エネと明るさを両立させる
確かに、そこは配慮が必要です。
光の向きや強さを調整して、近隣に迷惑がかからないようにしましょう。
例えば、こんな使い方があります。
庭の木の周りに動体センサー付きの照明を設置するんです。
「パッ」と明るくなった瞬間、木を登ろうとしていたアライグマは「ビックリ仰天」して逃げ出すかもしれません。
この方法の良いところは、24時間体制で監視できることです。
寝ている間も、アライグマの接近を光で知らせてくれるんです。
ただし、注意点もあります。
バッテリー式の場合は定期的な電池交換が必要です。
また、雨や雪に強い防水タイプを選ぶことも大切です。
「ピカッ」という光の変化は、アライグマにとっては「ドキッ」とする瞬間。
この心理を利用して、アライグマを寄せ付けない環境を作りましょう。
動体センサー付き照明は、静かでクリーンな対策方法なんです。
屋根や外壁に滑りやすい金属板を設置「侵入を物理的に阻止」
滑りやすい金属板は、アライグマの侵入を物理的に阻止する強力な武器になります。アライグマの器用な手と足も、ツルツルの金属板では歯が立たないんです。
「えっ、ただの金属板でアライグマが登れないの?」と驚く方も多いでしょう。
でも、これが意外と効果的なんです。
滑りやすい金属板を使ったアライグマ対策の方法を見てみましょう。
- 屋根の端や角に幅30〜50センチの金属板を取り付ける
- 雨樋の周りにも金属板を巻き付ける
- 外壁の下部1メートルほどを金属板で覆う
- 金属板の表面は滑らかで光沢のあるものを選ぶ
- 定期的に表面を磨いて滑りやすさを維持する
確かに、見た目は変わります。
でも、アライグマ被害を考えれば、見た目よりも安全が大切ですよね。
例えば、こんな使い方があります。
屋根の端に金属板を取り付けるんです。
「ヨイショ」とジャンプしてきたアライグマも、「ツルッ」と滑って落ちてしまうかもしれません。
この方法の良いところは、長期的な効果が期待できることです。
一度設置すれば、何年も効果が続くんです。
ただし、注意点もあります。
金属板の端が鋭くないか確認し、人やペットが怪我をしないよう気をつけましょう。
また、強風で金属板が飛ばされないよう、しっかり固定することも大切です。
「ツルツル」の金属板は、アライグマにとっては「イライラ」の種。
この心理を利用して、アライグマを寄せ付けない環境を作りましょう。
金属板は、静かで確実なアライグマ対策方法なんです。
強い香りのハーブを植える「アライグマが嫌う自然の防衛策」
強い香りのハーブは、アライグマを追い払う自然の防衛策になります。アライグマは鋭い嗅覚を持っているため、特定の強い香りを嫌うんです。
「えっ、ただのハーブでアライグマが逃げるの?」と思う方もいるでしょう。
でも、これが意外と効果的なんです。
強い香りのハーブを使ったアライグマ対策の方法を見てみましょう。
- ペパーミントを庭や家の周りに植える
- ラベンダーを窓際や玄関周りに配置する
- セージやローズマリーを鉢植えで置く
- タイムやオレガノを地植えにする
- ハーブティーの茶葉を庭にまく
確かに、植物の世話は少し手間がかかります。
でも、アライグマ対策になるだけでなく、香りを楽しんだり料理に使ったりもできるんですよ。
例えば、こんな使い方があります。
窓の下にラベンダーを植えるんです。
「クンクン」と匂いを嗅いだアライグマは「プンプン」怒って立ち去るかもしれません。
この方法の良いところは、環境にやさしいことです。
化学物質を使わず、自然の力でアライグマを追い払えるんです。
ただし、注意点もあります。
ハーブの種類によっては猫や犬にとって有毒なものもあるので、ペットがいる家庭では選び方に注意が必要です。
また、アレルギーのある人もいるので、家族の体質も考慮しましょう。
「フワッ」と漂うハーブの香りは、アライグマにとっては「ムッ」とする臭い。
この反応を利用して、アライグマを寄せ付けない環境を作りましょう。
ハーブは、美しく香り豊かなアライグマ対策方法なんです。
超音波発生装置の設置「人間には無害でアライグマには効果的」
超音波発生装置は、アライグマを追い払う強力な武器になります。人間には聞こえない高周波の音を出し、アライグマを不快にさせるんです。
「えっ、聞こえない音でアライグマが逃げるの?」と思う方もいるでしょう。
でも、これが意外と効果的なんです。
超音波発生装置を使ったアライグマ対策の方法を見てみましょう。
- 庭や家の周りに複数台設置する
- アライグマの侵入経路を中心に配置する
- 動体センサー付きの機種を選ぶ
- 太陽光パネル付きの機種で電気代を節約
- 防水機能付きの屋外用を選ぶ
安心してください。
人間の耳には聞こえない音なので、健康への影響はありません。
例えば、こんな使い方があります。
庭の入り口に超音波発生装置を設置するんです。
「キーン」という高周波音を聞いたアライグマは「ギャー」と驚いて逃げ出すかもしれません。
この方法の良いところは、静かで目立たないことです。
近所迷惑になる心配もなく、24時間稼働させられるんです。
ただし、注意点もあります。
ペットの中には敏感に反応する子もいるので、様子を見ながら使用しましょう。
また、効果は個体差があるので、他の対策と組み合わせるのがおすすめです。
「ピー」という超音波は、アライグマにとっては「ギャー」という不快音。
この反応を利用して、アライグマを寄せ付けない環境を作りましょう。
超音波発生装置は、静かで効果的なアライグマ対策方法なんです。