アライグマは冬眠する?【実は冬眠しない】日本の気候での生存戦略と対策時期を解説

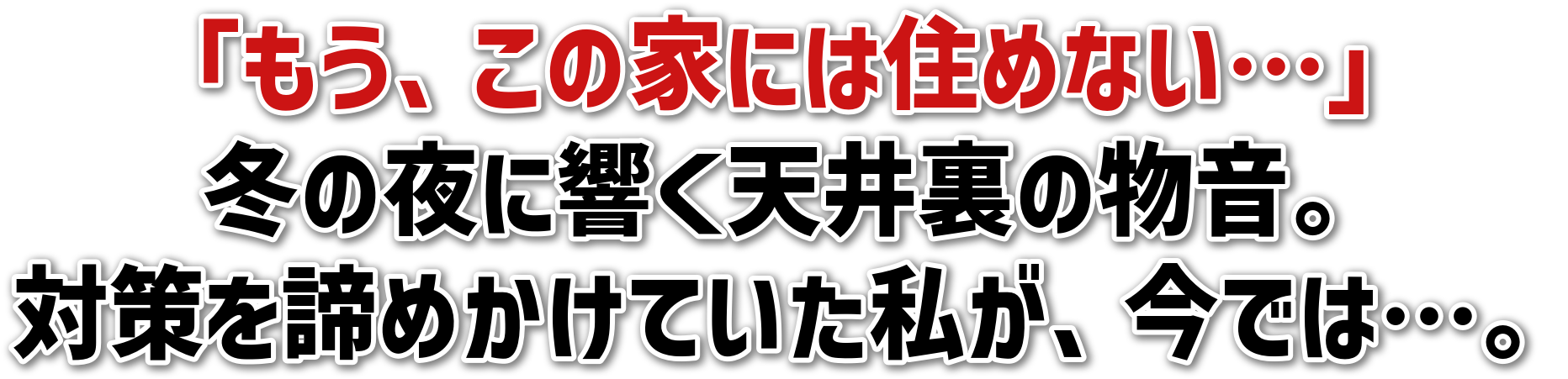
【この記事に書かれてあること】
「アライグマは冬眠するから冬は大丈夫」なんて油断していませんか?- アライグマは冬眠しないため、年間を通じた対策が必要
- 冬季は活動量が減少するものの、完全に停止することはない
- 寒さと食料不足により、冬は人家に接近しやすくなる
- 地域による違いがあり、北国と南国で冬の行動パターンが異なる
- 冬季には隙間の封鎖や食料管理が特に重要な対策となる
実はアライグマは冬眠しないんです!
寒い季節でも活動を続け、むしろ食料を求めて人家に接近する傾向があります。
冬こそアライグマ対策が重要なんです。
この記事では、アライグマの冬の生態と効果的な対策法を詳しく解説します。
冬眠しない彼らの行動を理解し、年間を通じた継続的な対策で被害を激減させましょう。
寒さに負けないアライグマ、その生態と撃退法をじっくり学んでいきましょう。
【もくじ】
アライグマの冬眠に関する誤解を解く

アライグマは冬眠しない!年中無休の活動サイクル
アライグマは冬眠しません。年中活動を続ける生き物なんです。
「えっ、アライグマって冬眠しないの?」と驚く方も多いでしょう。
実は、アライグマは北米原産の動物で、寒い冬でも活動を続ける能力を持っているんです。
冬眠しない理由は、アライグマの体の仕組みにあります。
- 体温調節能力が高い
- 厚い毛皮で寒さから身を守れる
- 雑食性で様々な食べ物を利用できる
「でも、寒い時期は動きが鈍くなるんじゃないの?」そう思う人もいるでしょう。
確かに、真冬の厳しい寒さの時期は活動量が減ります。
でも、完全に活動を止めることはありません。
年中活動するアライグマの習性は、私たちの生活に大きな影響を与えます。
冬でも油断できないんです。
「冬は大丈夫だろう」なんて思っていると、思わぬトラブルに見舞われるかもしれません。
アライグマの年中無休の活動サイクルを理解することで、効果的な対策を立てることができます。
冬眠しないからこそ、私たちも年間を通じて警戒を怠らない必要があるんです。
冬季のアライグマ「活動量減少」の真相とは?
冬季のアライグマは活動量が減少しますが、完全に止まることはありません。これが冬季のアライグマの真相です。
「冬になったらアライグマの姿を見なくなった」なんて経験はありませんか?
実は、姿が見えなくなっただけで、活動を続けているんです。
冬のアライグマの行動パターンは、夏とは大きく異なります。
冬季のアライグマの活動量減少の理由は主に3つあります。
- 寒さによるエネルギー消費の抑制
- 食料不足への対応
- 安全な隠れ家の確保
そのため、不必要な活動を控えるんです。
「まるで冬眠しているみたい」と思うかもしれません。
でも、実際は違うんです。
食料が少なくなる冬、アライグマは効率的に栄養を摂取しようとします。
そのため、活動時間を短縮し、エネルギーを温存するんです。
また、寒さを避けるため、暖かい隠れ家で過ごす時間が増えます。
ただし、注意が必要です。
活動量が減少しているからといって、警戒を緩めてはいけません。
むしろ、食料を求めて人家に近づく可能性が高まるんです。
「冬は大丈夫」なんて油断は禁物。
年中対策が必要なんです。
寒さに強い!アライグマの体温調節メカニズム
アライグマは寒さに強く、優れた体温調節メカニズムを持っています。これが冬眠せずに活動し続けられる秘密なんです。
「どうしてアライグマは寒い冬を乗り越えられるの?」そんな疑問を持つ人も多いでしょう。
実は、アライグマの体には寒さに負けない仕組みがいくつもあるんです。
アライグマの体温調節メカニズムの特徴を見てみましょう。
- 厚い二重構造の毛皮
- 体脂肪の蓄積
- 血流量の調整能力
- 代謝率の変化
外側の長い毛と内側の柔らかい毛の二重構造で、寒い外気から身を守ります。
まるで高性能のダウンジャケットを着ているようなものです。
体脂肪も重要な役割を果たします。
夏から秋にかけて蓄えた脂肪は、寒い冬を乗り越えるためのエネルギー源になるんです。
「太っているのは単なる食いしん坊じゃないんだ」と、ちょっと見方が変わりますね。
さらに、アライグマは血流量を調整する能力に優れています。
寒い時は体の中心部に血液を集中させ、熱を逃がさないようにするんです。
この能力のおかげで、体温を効率よく維持できるんです。
代謝率も冬に合わせて変化します。
寒い季節は代謝率を下げて、エネルギーの消費を抑えるんです。
「冬眠しなくても、体の中で冬眠に似たことが起きているんだな」と考えると面白いですね。
このような優れた体温調節メカニズムがあるからこそ、アライグマは冬眠せずに年中活動できるんです。
寒さに強い彼らの特性を理解することで、より効果的な対策を立てることができます。
冬眠しないからこそ要注意!「冬の被害対策」を怠るな
アライグマは冬眠しないため、冬の被害対策は非常に重要です。油断すると、思わぬ被害に遭うかもしれません。
「冬は寒いから大丈夫だろう」なんて考えていませんか?
実は、それが大きな間違いなんです。
冬のアライグマは食料不足に悩まされ、より積極的に人家に近づく傾向があります。
冬の被害対策で特に注意すべきポイントをいくつか挙げてみましょう。
- 屋根裏や壁の隙間の封鎖
- ゴミの適切な管理
- 庭の果樹や野菜の保護
- ペットフードの屋内保管
- 暖かい場所への侵入防止
屋根裏や壁の隙間は、絶好の隠れ家になってしまうんです。
「ちょっとした隙間くらい大丈夫」なんて思っていると、大変なことになりかねません。
5mm程度の小さな穴でも、アライグマは侵入できるんです。
食料が少ない冬、ゴミはアライグマにとって貴重な食料源です。
ゴミ箱の蓋をしっかり閉めるなど、適切な管理が欠かせません。
「冬だからゴミ出しが面倒」なんて気を抜いてはいけません。
庭の果樹や野菜も要注意です。
食料が少ない冬は、わずかな食べ物でもアライグマを引き寄せてしまいます。
収穫後の残り物も、きちんと片付けることが大切です。
ペットフードも、アライグマにとっては魅力的な食べ物。
「寒いから外に置いても大丈夫」なんて考えは危険です。
必ず屋内で保管しましょう。
暖かい場所への侵入防止も重要です。
特に、暖房の排気口周辺は要注意。
温かい空気に誘われて、アライグマが近づいてくる可能性があります。
冬眠しないアライグマだからこそ、年間を通じた対策が必要なんです。
「冬は大丈夫」という油断が、思わぬ被害を招くかもしれません。
冬こそしっかりと対策を立て、アライグマから家や庭を守りましょう。
冬季のアライグマの行動と生態を徹底解説

冬のアライグマvs夏のアライグマ!行動パターンの違い
冬と夏では、アライグマの行動パターンに大きな違いがあります。季節による変化を理解することが、効果的な対策の鍵となります。
「冬のアライグマは冬眠するから大丈夫」なんて思っていませんか?
実はそれ、大きな間違いなんです。
アライグマは冬眠しません。
でも、冬と夏では行動パターンが全然違うんです。
まず、活動時間の違いを見てみましょう。
- 夏:日が暮れてからガンガン活動
- 冬:活動時間が短くなり、ゆっくりモード
あっちこっちを動き回って、食べ物を探したり遊んだり。
まるで夜の街を楽しむ若者たちのようです。
一方、冬のアライグマは「寒いから引きこもりたい」モード。
外に出る時間が短くなり、動きもスローに。
でも、完全に活動を止めるわけではありません。
食べ物の好みも季節で変わります。
- 夏:果物や野菜が大好物
- 冬:高カロリーの食べ物を求めて奮闘
アライグマにとっては天国のようなもの。
でも冬は違います。
「おいしいものがない!」とアライグマも嘆いているかも。
だから、人間の食べ物に目をつけやすくなるんです。
冬のアライグマは、暖かい場所を求めてウロウロします。
「寒いよ〜」とばかりに、家の中に侵入しようとすることも。
夏は外で過ごすことが多いのに比べ、大きな違いですね。
このように、冬と夏ではアライグマの行動パターンが全然違います。
だから、季節に合わせた対策が必要なんです。
冬だからって油断は禁物。
むしろ、家の中に入ろうとする可能性が高まるので要注意です。
寒さと食料不足!アライグマが冬に人家に接近する理由
冬になると、アライグマが人家に接近する頻度が高くなります。その主な理由は、寒さをしのぐ暖かい場所と食料を求めているからなんです。
「冬はアライグマが出てこないから安心」なんて思っていませんか?
それは大きな間違い。
むしろ冬こそ、アライグマが家に近づいてくる可能性が高まるんです。
アライグマが冬に人家に接近する理由は主に2つ。
- 寒さを避けたい
- 食べ物を探している
アライグマだって寒いのは苦手。
「ブルブル、寒いよ〜」って感じで、暖かい場所を探しているんです。
そこで目をつけるのが、人間の家。
屋根裏や壁の隙間は、アライグマにとって最高の隠れ家になっちゃうんです。
次に、食べ物探し。
冬は自然の中で食べ物を見つけるのが難しくなります。
「お腹すいた〜」とアライグマも必死。
そこで、人間の家の周りにある食べ物に目をつけるわけです。
例えば、こんな場所がアライグマを引き寄せちゃいます。
- ゴミ置き場:残飯の宝庫
- 庭のコンポスト:野菜くずが魅力的
- ペットの餌:栄養満点の食事
実は、見落としがちな誘引物もあるんです。
例えば、鳥の餌台。
小鳥のためにまいた種も、アライグマにとっては魅力的な食事になっちゃうんです。
寒さと食料不足。
この2つの要因が、冬のアライグマを人家に引き寄せるんです。
だから、冬こそアライグマ対策が重要。
家の周りの食べ物を管理し、侵入経路をふさぐことが大切です。
油断は大敵。
冬でも気を抜かずに対策を続けましょう。
冬季の食料確保と人工的食物源への依存度の変化
冬季になると、アライグマの食料確保方法が大きく変わります。自然の食べ物が少なくなるため、人工的な食物源への依存度が急激に高まるんです。
「冬はアライグマの餌が少ないから、被害も減るんじゃない?」なんて考えていませんか?
実はその逆。
食べ物が少ないからこそ、アライグマは人間の生活圏に近づいてくるんです。
冬のアライグマの食料事情を見てみましょう。
- 自然の食べ物:がくっと減少
- 人工的な食物源:依存度アップ
でも冬になると、そんな自然の食べ物はめっきり少なくなっちゃうんです。
「おいしいものどこ?」とアライグマも必死。
そこで目をつけるのが、人間の食べ物。
ゴミ箱や農作物、ペットフードなど、人工的な食物源への依存度がグッと高まります。
まるで、冬限定の「人間の食べ物探検ツアー」に出かけるような感じです。
冬季にアライグマが狙いやすい人工的食物源を見てみましょう。
- ゴミ置き場:残飯の宝庫
- コンポスト:野菜くずが魅力的
- 果樹園:落ちた果物が大好物
- ペットフード:栄養満点の食事
- 鳥の餌台:小鳥の餌も狙い目
でも、意外なところにアライグマの「ごちそう」が隠れているかもしれません。
例えば、庭に植えた野菜。
冬でも育つ大根や白菜は、アライグマにとっては貴重な食料源になっちゃうんです。
この食料確保行動の変化は、私たちの生活に大きな影響を与えます。
冬こそ、家の周りの食べ物管理が重要。
ゴミは適切に処理し、ペットフードは屋内で保管。
庭の果物や野菜も、できるだけ早く収穫するのがおすすめです。
冬季のアライグマ対策の鍵は、この食料確保行動の変化を理解すること。
人工的な食物源をしっかり管理すれば、アライグマの被害を大幅に減らせるんです。
冬こそ気を抜かずに、しっかり対策を続けましょう。
エネルギー消費を抑える冬の生存戦略に注目!
冬のアライグマは、エネルギー消費を抑える巧みな生存戦略を持っています。この戦略を理解することで、より効果的な対策を立てることができるんです。
「冬は寒いから、アライグマも活動しないんじゃない?」なんて思っていませんか?
確かに活動量は減りますが、完全に止まるわけではありません。
むしろ、エネルギーを効率よく使う賢い戦略を取っているんです。
アライグマの冬の生存戦略、いくつかポイントを見てみましょう。
- 活動時間の短縮:エネルギー節約の基本
- 移動距離の削減:無駄な動きを避ける
- 体温調節の工夫:寒さ対策は万全
- 効率的な採餌:少ない食事で最大限の栄養
冬のアライグマは、外出する時間をぐっと減らします。
「寒いから外に出たくない」って感じですね。
人間で言えば、冬はこたつに籠もるようなものです。
移動距離も短くなります。
夏なら広い範囲を動き回るのに、冬は必要最小限の移動で済ませようとします。
まるで、買い物も近所のコンビニで済ませちゃうような感じ。
体温調節も上手です。
寒い時は体を丸めて熱を逃がさないようにしたり、暖かい場所を見つけて過ごしたり。
人間でいえば、厚着をしたりこたつに入ったりするようなものですね。
食事も効率的。
冬は1日1回程度の食事で済ませることも。
でも、その分カロリーの高い食べ物を選びます。
「少ない食事で最大限の栄養を」がモットーなんです。
この生存戦略を知ることで、私たちの対策も変わってきます。
例えば、アライグマが好む暖かい場所(屋根裏や壁の隙間など)をしっかり封鎖すること。
また、高カロリーの食べ物(ペットフードや残飯など)の管理を徹底することが重要になってきます。
アライグマの冬の生存戦略、なかなか賢いでしょう?
でも、この戦略を理解することで、私たちの対策もより効果的になるんです。
冬のアライグマ対策、エネルギー消費を抑える生存戦略を踏まえて考えてみましょう。
地域による違い!北国vs南国のアライグマの冬の過ごし方
アライグマの冬の過ごし方は、地域によって大きく異なります。北国と南国では、まるで別の生き物のように行動が変わるんです。
この違いを知ることで、より効果的な対策が可能になります。
「アライグマの冬の行動って、どこでも同じじゃないの?」なんて思っていませんか?
実は、地域によって大きく違うんです。
北海道のアライグマと沖縄のアライグマでは、まるで別の生き物のような違いがあるんです。
北国と南国のアライグマの冬の過ごし方、比べてみましょう。
- 北国のアライグマ:
- 活動期間が短い
- 冬眠に近い状態になることも
- 食料確保に必死
- 南国のアライグマ:
- 年中活動的
- 冬でも活発に動き回る
- 食料は比較的豊富
「ブルブル、寒すぎ!」って感じで、活動期間がぐっと短くなります。
極端な場合は、冬眠に近い状態になることも。
食べ物探しも一苦労で、人家に近づく頻度が高くなりがちです。
一方、南国のアライグマは冬でもわりと気楽。
「寒いのはちょっとの間だけ」くらいの感覚で、年中活発に動き回ります。
食べ物も比較的豊富なので、北国ほど必死になって人家に接近することはありません。
この違いは、私たちの対策にも大きく影響します。
北国では、冬の間の家屋への侵入防止が特に重要。
暖かい隠れ家になりそうな場所を徹底的にふさぐ必要があります。
南国では、年間を通じてコンスタントな対策が求められます。
都市部と山間部でも違いがあります。
都市部のアライグマは、人工的な食物源や暖かい隠れ家が豊富なため、冬でも活発に活動します。
一方、山間部のアライグマは、自然の厳しさにさらされるため、北国のアライグマに近い行動を取ります。
「へー、地域によってこんなに違うんだ」って驚いていませんか?
この違いを理解することで、自分の住む地域に合った効果的な対策を立てることができるんです。
北国に住んでいるなら、屋根裏や壁の隙間の封鎖を徹底的に。
南国なら、年間を通じてゴミ管理や餌場の片付けを怠らないこと。
それぞれの地域の特性に合わせた対策が、アライグマ被害を減らす鍵となるんです。
地域による違いを知ることで、アライグマ対策の効果はグンと上がります。
自分の住む地域のアライグマの特徴をよく観察し、それに合わせた対策を立てていきましょう。
そうすれば、アライグマとの共存も夢じゃありません。
冬のアライグマ対策、地域の特性を踏まえてしっかり取り組んでいきましょう。
冬季に効果的なアライグマ対策と防御法

冬の隙間を徹底封鎖!侵入防止の決め手となる対策法
冬季のアライグマ対策で最も重要なのは、家屋の隙間を徹底的に封鎖することです。これが侵入防止の決め手となります。
「冬だからアライグマは来ないだろう」なんて油断していませんか?
実は冬こそ、アライグマは暖かい場所を求めて家に侵入しようとするんです。
だから、隙間封鎖が超重要なんです。
アライグマが侵入しやすい場所をチェックしましょう。
- 屋根裏の換気口
- 壁の亀裂や隙間
- 基礎と建物の間の隙間
- 煙突やダクト周り
- 窓や戸のすき間
でも、アライグマは驚くほど小さな隙間から侵入できるんです。
なんと、直径10センチの穴があれば入れちゃうんです。
隙間を見つけたら、すぐに対策を。
金属製のメッシュや板で塞ぐのが効果的です。
「ちょっとした隙間くらいいいか」なんて思わないでください。
アライグマは小さな隙間を見つけると、がりがりと噛んで広げちゃうんです。
特に注意したいのが屋根裏です。
暖かくて隠れやすい屋根裏は、アライグマにとって冬の楽園。
ここから侵入されると大変なことに。
「屋根裏なんて見えないから大丈夫」なんて油断は禁物です。
冬の隙間封鎖、面倒くさいと思うかもしれません。
でも、これをサボると春には大変なことになっちゃうかも。
アライグマに家を占拠されて、「出て行ってー!」って泣きそうになる前に、しっかり対策しましょう。
冬の隙間封鎖、アライグマ対策の基本中の基本です。
寒さを味方につける!冬季限定の撃退テクニック
冬季ならではのアライグマ撃退テクニックがあります。寒さを味方につけることで、効果的にアライグマを遠ざけることができるんです。
「寒さを味方につける?どういうこと?」って思いますよね。
実は、アライグマの冬の行動特性を利用した撃退法があるんです。
寒さに弱いアライグマの性質を逆手に取るわけです。
冬季限定の撃退テクニックをいくつか紹介しましょう。
- 雪や氷を利用した滑り台作戦
- 冷たい水のペットボトル設置法
- 冬の香りを使った撃退法
- 寒冷地の動物の鳴き声再生作戦
- 偽の月光で行動を抑制
家の周りに滑りやすい傾斜を作ることで、アライグマの侵入を防ぎます。
「ズルッ」としてすべり落ちるアライグマ、ちょっと想像すると面白いですね。
次に、冷たい水のペットボトル設置法。
侵入経路に冷たい水を入れたペットボトルを置くんです。
アライグマは寒さを避けたいので、近づきたがらなくなります。
冬の香りを使った撃退法も効果的。
シナモンやクローブなど、冬らしい香りの植物をアライグマの侵入経路に置きます。
「この匂い、なんか苦手」ってアライグマも思うみたいです。
寒冷地の動物の鳴き声再生作戦も面白いです。
オオカミなど、寒い地域に住む動物の鳴き声を再生すると、アライグマが警戒して近づかなくなるんです。
偽の月光で行動を抑制する方法も。
発光ダイオード電球で作った偽物の「月光」を庭に設置すると、アライグマの行動を抑制できるんです。
これらの方法、ちょっと変わってますよね。
でも、アライグマの習性を利用しているので、意外と効果的なんです。
冬ならではの撃退テクニック、ぜひ試してみてください。
アライグマも「ここ、寒くて苦手」って思って、あなたの家を避けてくれるかもしれません。
冬の食料不足を逆手に取る!誘引物の管理と対策
冬季のアライグマ対策で重要なのが、食料源の管理です。食料不足に悩むアライグマの習性を逆手に取ることで、効果的に被害を防ぐことができます。
「冬は食べ物が少ないから、アライグマも来ないんじゃない?」なんて思っていませんか?
実はその逆。
食料が少ないからこそ、アライグマは人家に近づいてくるんです。
アライグマを引き寄せてしまう冬の誘引物をチェックしましょう。
- ゴミ箱の中身
- ペットフード
- 鳥の餌台
- 落ち葉の山
- 庭の果物や野菜の残り
でも、冬の食料不足に悩むアライグマにとっては、これらすべてが魅力的な食べ物なんです。
まず、ゴミ箱の管理が重要です。
「寒いから外に置いても大丈夫」なんて油断は禁物。
しっかり蓋をして、できれば屋内に保管しましょう。
ペットフードも要注意。
「寒いからちょっとくらい外に置いても」なんて考えはダメです。
アライグマにとっては、ごちそうそのものなんです。
鳥の餌台も意外と危険。
小鳥のためにまいた種も、アライグマの格好の食料になっちゃいます。
冬は地面に落ちた餌を片付けるのを忘れずに。
落ち葉の山も要チェック。
中に虫がいるかもしれないと、アライグマは落ち葉をかき分けて食べ物を探すんです。
こまめに片付けましょう。
庭の果物や野菜の残りも片付けが大切。
「寒いから腐らないだろう」なんて放置していると、アライグマの餌場になっちゃいます。
これらの誘引物をしっかり管理することで、アライグマを寄せ付けない環境を作れます。
「食べ物がない」と分かれば、アライグマも別の場所を探すはず。
冬の食料不足を逆手に取る、賢い対策で家を守りましょう。
音と光で威嚇!冬でも有効なアライグマ撃退法
冬季でも効果的なアライグマ撃退法として、音と光を使った威嚇があります。アライグマの嫌がる刺激を上手に利用することで、効果的に撃退できるんです。
「冬は静かだから、音や光は効かないんじゃない?」なんて思っていませんか?
実は冬こそ、音と光の威嚇が効果的なんです。
静かな環境だからこそ、突然の刺激にアライグマはびっくりしちゃうんです。
音と光を使ったアライグマ撃退法をいくつか紹介しましょう。
- 動きを感知する照明
- 突然の大音量
- 超音波装置
- 点滅するランプ
- 犬の鳴き声の再生
アライグマが近づくと突然明るくなるので、びっくりして逃げちゃいます。
「うわっ、まぶしい!」ってな具合です。
突然の大音量も効果的。
ラジオや音楽を突然流すと、アライグマは驚いて逃げ出します。
「なんだこの音!?」って感じでしょうね。
超音波装置も人気です。
人間には聞こえない高周波音を出すので、近所迷惑にならずアライグマを撃退できます。
「キーン」という音がアライグマには不快なんです。
点滅するランプも効果があります。
不規則に点滅する光は、アライグマにとってはストレスになるんです。
「目がチカチカする〜」って感じでしょうか。
犬の鳴き声の再生も意外と効果的。
アライグマは犬が苦手なので、「わんわん」という音を聞くと近づきたがらなくなります。
これらの方法、どれも「突然」がポイントです。
アライグマが予想していない時に刺激を与えることで、効果が高まります。
ただし、毎日同じパターンだと慣れてしまうので、時々変化をつけるのがコツです。
音と光を使った撃退法、ちょっと面白いですよね。
「人間には平気だけど、アライグマには効く」という方法で、冬の静かな夜にこっそりアライグマを撃退。
それって、なんだかちょっとスパイみたいでワクワクしませんか?
冬のアライグマ対策、音と光を味方につけて頑張りましょう。
冬眠しないからこそ可能!年間を通じた継続的な対策の重要性
アライグマは冬眠しないからこそ、年間を通じた継続的な対策が重要です。季節ごとに変化するアライグマの行動を理解し、それに合わせた対策を立てることが効果的な被害防止につながります。
「えっ、冬眠しないの?」って驚く方も多いかもしれません。
そうなんです。
アライグマは冬眠しないので、一年中活動しているんです。
だからこそ、私たちも油断せずに対策を続ける必要があるんです。
年間を通じたアライグマ対策のポイントをまとめてみましょう。
- 春:繁殖期に備えた侵入防止
- 夏:果物や野菜の管理
- 秋:冬に向けた準備の時期
- 冬:暖かい隠れ家対策
アライグマはお母さんになる準備で、安全な巣作りの場所を探します。
家の隙間や屋根裏がターゲットになりやすいので、しっかり封鎖しましょう。
「ここいいな〜」って思わせない工夫が大切です。
夏は食べ物が豊富。
果物や野菜が実る時期なので、庭の管理が重要です。
「おいしそう!」って寄ってくるアライグマを防ぐため、収穫はこまめに。
秋は冬への準備期間。
アライグマも冬に備えて食料を探し回ります。
ゴミの管理を徹底し、「ここにはおいしいものがない」と思わせることが大切。
冬は寒さをしのぐ場所を探す季節。
家の中の暖かい場所が狙われやすくなります。
隙間の封鎖を再チェックし、「ここ暖かそう」と思わせない工夫を。
このように、季節ごとにアライグマの行動は変化します。
「冬は大丈夫」なんて油断は禁物。
一年を通じて継続的に対策を行うことが、アライグマ被害を防ぐ鍵なんです。
年間を通じた対策、面倒くさいと思うかもしれません。
でも、アライグマとの知恵比べだと思えば、ちょっと楽しくなりませんか?
「よし、今月はこの対策だ!」って感じで、季節ごとに新しい作戦を立てるのも面白いかもしれません。
アライグマは冬眠しない。
だからこそ、私たちも気を抜かずに対策を続けることが大切なんです。
年間を通じた継続的な対策で、アライグマとの上手な付き合い方を見つけていきましょう。