アライグマ捕獲後の対処法は?【素手で触らないのが鉄則】安全な取り扱い方と適切な引き渡し先を解説

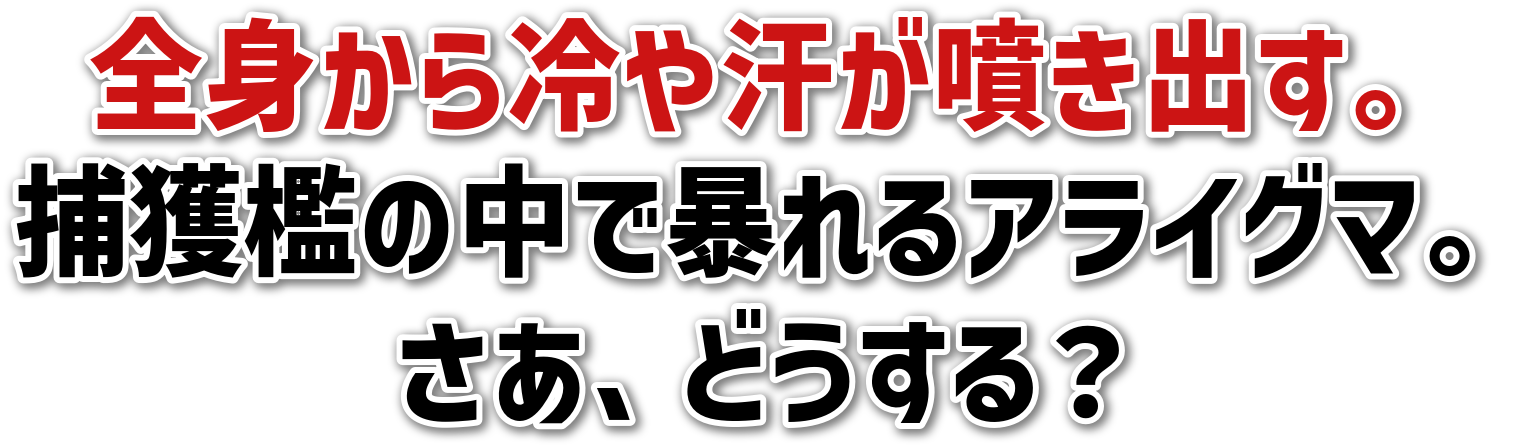
【この記事に書かれてあること】
アライグマを捕獲したけれど、その後どうすればいいの?- アライグマ捕獲後は素手での接触を厳禁
- 市町村への速やかな連絡と引き渡しが必要
- 捕獲したアライグマの勝手な処分は違法
- 48時間以内の引き渡しが望ましい
- 建物の隙間封鎖が再侵入防止の鍵
- 香りや音を利用した意外な対策法も効果的
実は、アライグマの捕獲後の対処には重要なポイントがたくさんあるんです。
素手で触ると大変なことになりかねません。
でも、安心してください。
この記事では、アライグマ捕獲後の正しい対処法を、わかりやすく解説します。
法律に沿った手続きや安全な取り扱い方、さらには再侵入を防ぐための驚きの対策法まで。
アライグマ対策のプロになれる情報が満載です。
さあ、一緒にアライグマ捕獲後の正しい対応を学んでいきましょう!
【もくじ】
アライグマ捕獲後の対処法とは

「素手で触らない」が鉄則!感染症リスクに要注意
アライグマを捕まえた後は、絶対に素手で触らないことが大切です。感染症のリスクが高いんです。
「やった!やっと捕まえたぞ」とうれしくなって、つい触りたくなりますよね。
でも、ちょっと待ってください。
アライグマは見た目はかわいいですが、実は危険な病気を持っていることがあるんです。
例えば、アライグマ回虫症という怖い病気があります。
この寄生虫は人間の体に入ると、目や脳に寄生してしまうことも。
ゾクゾクしますね。
他にも狂犬病やダニ媒介性の病気など、様々な感染症のリスクがあります。
では、どうすればいいのでしょうか?
- 必ず厚手の手袋を着用する
- 長袖、長ズボンで肌の露出を避ける
- マスクも着けると安全性アップ
実は、手袋をしていても油断は禁物。
アライグマは鋭い爪と歯を持っているので、噛みついたり引っかいたりして手袋を破ることもあるんです。
だから、できるだけ触らないのが一番なんです。
安全第一で、慎重に対応しましょう。
アライグマとの接触は最小限に、そして必要な防護策をしっかりと取ることが大切です。
捕獲直後の行動!まず市町村に連絡して引き渡し手続き
アライグマを捕まえたら、すぐに市町村の担当部署に連絡することが重要です。これが適切な対処の第一歩なんです。
「えっ、市役所に電話するの?」と驚く人もいるかもしれません。
でも、アライグマは特定外来生物に指定されているため、法律で定められた手続きが必要なんです。
まず、市町村の環境課や農林水産課に電話をかけましょう。
「アライグマを捕獲しました」と伝えれば、担当者が親切に対応してくれます。
連絡する際は、次の情報を準備しておくとスムーズです:
- 捕獲した日時と場所
- アライグマの状態(大きさ、怪我の有無など)
- 捕獲方法(どんな罠を使ったかなど)
多くの自治体では休日や夜間の連絡先も用意されています。
事前に確認しておくと安心ですね。
市町村への連絡後は、48時間以内に引き渡すのが望ましいとされています。
それまでの間、アライグマを適切に保管することも大切です。
風通しの良い日陰で、水と少量の餌を与えながら待機させましょう。
「ピンポーン」と玄関のチャイムが鳴り、「引き取りに来ました」という職員の声。
ほっとすると同時に、「これで一件落着」とちょっぴりうれしくなりますよね。
適切な手続きを踏むことで、地域の環境保護に貢献できるんです。
アライグマを勝手に処分するのは「違法行為」だ!
捕まえたアライグマを自分で処分しようと考えていませんか?それは絶対にダメです。
実は、勝手に処分するのは違法行為なんです。
「えっ、自分で捕まえたのに処分しちゃいけないの?」と思う人もいるでしょう。
でも、アライグマは特定外来生物に指定されているため、その取り扱いには厳しい規制があるんです。
外来生物法によると、アライグマを勝手に処分したり、野外に放したりすることは禁止されています。
違反すると、なんと最高で3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い罰則があるんです。
ゾッとしますね。
では、具体的にどんなことが禁止されているのでしょうか?
- 捕獲したアライグマを山や川に放すこと
- 自分で殺処分すること
- 他人に譲渡すること
- ペットとして飼育すること
しかし、放すことでかえって生態系を乱してしまう可能性があるんです。
アライグマは繁殖力が強く、在来種を脅かす存在。
一匹を逃がすことで、地域全体に大きな影響を与えかねません。
だからこそ、法律に従って適切に対処することが大切なんです。
「ふむふむ、なるほど」と納得していただけましたか?
アライグマの処分は、必ず行政機関に任せましょう。
それが、私たちにできる最も適切な対応なんです。
「檻から出すな」が安全の鍵!そのまま引き渡しを
捕獲したアライグマを檻から出そうとしていませんか?それは危険です!
檻から出さずに、そのまま引き渡すのが一番安全な方法なんです。
「えっ、檻ごと渡すの?」と驚く声が聞こえてきそうです。
そうなんです。
アライグマを檻から出す必要はありません。
むしろ、出さない方が良いんです。
なぜ檻から出してはいけないのでしょうか?
理由は主に3つあります:
- アライグマが逃げ出す危険性がある
- 噛まれたり引っかかれたりするリスクがある
- ストレスを与えて攻撃的になる可能性がある
確かにその気持ちはわかります。
でも、短時間なら檻の中でも大丈夫なんです。
むしろ、檻から出そうとするとアライグマは恐怖を感じ、パニックになってしまいます。
「ガタガタ」と檻を揺らしたり、「キーッ」と鋭い声を上げたりすることも。
そうなると、近所迷惑にもなりかねません。
檻ごと引き渡す際の注意点もいくつかあります:
- 檻にタオルや布をかけて刺激を減らす
- 直射日光や雨を避ける
- 車で運ぶ際は揺れに注意する
アライグマにとっても、人間にとっても、これが最善の方法なんです。
檻から出さず、そのまま引き渡す。
この簡単なルールを守ることで、安全かつスムーズな対応ができます。
アライグマとの思わぬトラブルを避けて、ホッと一安心できますよ。
捕獲後の一時保管と専門家への引き渡し方

一時保管の注意点!風通しの良い日陰で48時間以内に
アライグマを捕獲したら、風通しの良い日陰で48時間以内に引き渡すのが理想的です。「えっ、48時間も待つの?」と思われるかもしれません。
でも、すぐに引き渡せない場合もあるんです。
そんなときの対処法を知っておくと安心ですよ。
まず、アライグマを捕獲檻に入れたまま、風通しの良い日陰に置きましょう。
直射日光はNG!
アライグマがバテちゃいます。
温度は15度から25度くらいが適温です。
「ガタガタ」と檻を揺らしたり、「キャンキャン」と鳴いたりしていても、むやみに近づかないでください。
刺激を与えると、ますます興奮してしまいます。
一時保管中の大切なポイントは3つ!
- 水をたっぷり与える
- 少量の餌を用意する
- 人や他の動物が近づかないよう注意する
でも、過剰な給餌はストレスの原因になるんです。
ほんの少しで十分です。
そして、48時間を超えないようにしましょう。
「ズルズル引き伸ばしちゃダメ!」と心に刻んでおいてください。
長期保管は、アライグマにとっても大きなストレスになるんです。
一時保管は短期間で済ませる。
これが、アライグマにとっても、あなたにとっても、最善の方法なんです。
アライグマvs野良猫!一時保管時の餌やりの違いに注目
アライグマと野良猫、一時保管時の餌やり方は全然違うんです。アライグマには少量の餌を、野良猫にはたっぷりと。
この違いを知ることが大切です。
「えっ、アライグマには少ない方がいいの?」と驚く方もいるでしょう。
そうなんです。
アライグマは野生動物。
必要最小限の餌で十分なんです。
一方、野良猫は人間の生活に慣れています。
だから、たっぷりと餌をあげても大丈夫。
でも、アライグマにそれをしちゃうと大変なことに!
アライグマへの餌やりのポイントは3つ!
- 1日1回、少量の餌を与える
- 果物や野菜を中心に
- 生肉は絶対に与えない
でも、ぐっとこらえましょう。
過剰な給餌は、かえってストレスになるんです。
例えば、リンゴ半分とニンジン1本くらいで十分。
「こんなに少なくていいの?」と思うかもしれません。
でも、これくらいが適量なんです。
一方、野良猫なら「カリカリ」とドライフードをたっぷりと。
水も忘れずに。
野良猫は人間の餌に慣れているので、心配いりません。
「なるほど、動物によって全然違うんだね」とわかっていただけましたか?
適切な餌やりが、動物のストレス軽減につながるんです。
アライグマと野良猫、それぞれの特性を理解して対応することが大切ですよ。
引き渡し準備のコツ!捕獲状況の記録が重要ポイント
アライグマを行政に引き渡す際、捕獲状況の記録が重要なポイントです。しっかりと記録を取ることで、スムーズな引き渡しにつながります。
「えっ、記録を取るの?めんどくさそう…」と思われるかもしれません。
でも、大丈夫!
簡単なことばかりですよ。
まず、捕獲の日時と場所を記録しましょう。
「カチカチ」とスマホのカメラで撮影しておくのもいいですね。
写真があれば、状況がより詳しく伝わります。
次に、捕獲時のアライグマの様子も書き留めておきましょう。
例えば、「ガブッ」と噛みついてきたとか、「キャンキャン」と鳴いていたとか。
そんな細かい情報が役立つんです。
記録すべき重要なポイントは4つ!
- 捕獲の日時と場所
- アライグマの大きさや特徴
- 捕獲時の状況(餌を使ったかなど)
- 捕獲後の行動や健康状態
実は、この情報がアライグマ対策の貴重なデータになるんです。
例えば、「毎年6月頃に出没する」とか「果樹園の近くで多く捕獲される」といった傾向がわかれば、より効果的な対策が立てられます。
あなたの記録が、地域全体のアライグマ対策に役立つかもしれないんです。
引き渡し時には、これらの記録を行政の担当者に渡します。
「はい、これが記録です」と手渡すだけで大丈夫。
担当者も、詳しい情報があると助かるんです。
記録を取る。
これは面倒くさいことではなく、大切な役割なんです。
あなたの小さな行動が、大きな助けになる。
そう考えると、やりがいを感じませんか?
引き渡し先はどこ?市町村役場が基本の受け入れ窓口
アライグマの引き渡し先は、基本的に市町村役場です。具体的には、環境課や農林水産課が窓口になることが多いんです。
「えっ、市役所に行くの?」と驚く方もいるでしょう。
でも、心配いりません。
アライグマの引き渡しは、実はよくあることなんです。
まず、お住まいの市町村役場に電話をしましょう。
「アライグマを捕獲したんですが…」と伝えれば、担当部署に繋いでくれます。
電話する際のポイントは3つ!
- 捕獲した日時と場所を伝える
- アライグマの状態(大きさ、怪我の有無など)を説明する
- 引き渡し可能な日時を確認する
そんなシーンを想像すると、ちょっとドキドキしますよね。
でも、大丈夫。
引き取りは素早く、スムーズに行われるんです。
注意点として、アライグマを市役所まで自分で運ぶのは避けましょう。
多くの場合、職員が引き取りに来てくれます。
「ガタガタ」と揺れる車での移動は、アライグマにとって大きなストレスになるんです。
「休日だったらどうしよう…」と心配な方もいるでしょう。
安心してください。
多くの自治体では、休日や夜間の連絡先も用意されています。
事前に確認しておくと、いざというときに慌てずに済みますよ。
引き渡し後のアライグマの処遇が気になる方もいるでしょう。
実は、多くの場合、安楽死処分されます。
「かわいそう…」と思う気持ちはわかります。
でも、これは生態系を守るために必要な措置なんです。
市町村役場への引き渡し。
これが、アライグマ対策の第一歩なんです。
あなたの行動が、地域の環境保護につながっている。
そう考えると、少し誇らしい気持ちになりませんか?
アライグマの再侵入を防ぐ驚きの対策法

建物の隙間封鎖が鍵!5mm以下の穴もしっかり塞ぐ
アライグマの再侵入を防ぐには、建物の隙間をしっかり封鎖することが何よりも大切です。特に5mm以下の小さな穴も見逃さないようにしましょう。
「えっ、5mmの穴からアライグマが入れるの?」と驚く方もいるでしょう。
でも、アライグマは体を驚くほど小さく縮めることができるんです。
まるでスクイーズおもちゃのように、ぐにゃぐにゃと変形して侵入してしまいます。
では、具体的にどんな場所を注意すればいいのでしょうか?
- 屋根と壁の接合部
- 換気口や排水口
- 窓や戸の隙間
- 配管やケーブルの通り道
「ちょっとした隙間くらい…」と油断は禁物です。
アライグマにとっては、その「ちょっとした隙間」が絶好の侵入口になるんです。
隙間を塞ぐ材料としては、金属製のメッシュや板が効果的です。
プラスチックや木材は、アライグマの鋭い歯で簡単に噛み砕かれてしまいます。
「ガリガリ」と音を立てて、あっという間に大きな穴になっちゃうんです。
定期的な点検も忘れずに。
台風や地震の後は特に要注意です。
「ビリビリ」と音がしたら、どこかに隙間ができた合図かもしれません。
隙間封鎖は面倒くさい作業かもしれません。
でも、これをしっかりやっておけば、アライグマの再侵入をグンと減らすことができます。
「よし、今日から隙間ハンターになるぞ!」という気持ちで、家の周りを探検してみてはいかがでしょうか。
ラベンダーの香りでストレス軽減!捕獲檻に活用も
アライグマ対策に、ラベンダーの香りが効果的だってご存知でしたか?実は、この香りでアライグマのストレスを軽減できるんです。
捕獲檻に活用すれば、より人道的な対応が可能になります。
「えっ、アロマテラピーみたいなこと?」と思われるかもしれません。
でも、これ、本当に効果があるんです。
ラベンダーの香りには、動物を落ち着かせる効果があるんです。
具体的な使い方は、こんな感じです:
- 捕獲檻の近くにラベンダーの鉢植えを置く
- 檻の周りにラベンダーオイルを数滴たらす
- ラベンダーの香りのする布を檻の中に入れる
暴れたり、ストレスで体調を崩したりするリスクが減るんです。
ただし、注意点もあります。
強すぎる香りは逆効果。
アライグマの鼻は非常に敏感なので、強い香りはかえってストレスになってしまいます。
「ほんのり」程度の香りを心がけましょう。
「でも、ラベンダーってアライグマを寄せ付けちゃうんじゃない?」という疑問も出てくるかもしれません。
確かに、香りだけではアライグマを追い払うことはできません。
でも、捕獲時のストレス軽減には大いに役立つんです。
ラベンダーの香りを利用することで、アライグマにも優しい対策が可能になります。
「アライグマさん、ゆっくり休んでいってね」なんて声をかけながら、檻の周りにラベンダーを置いてみるのはいかがでしょうか。
人間にもアライグマにも、優しい対策法なんです。
意外な防御線!アルミホイルでアライグマを寄せ付けない
アライグマ対策に、なんとアルミホイルが効果的だってご存知でしたか?意外かもしれませんが、このキッチンでおなじみのアイテムが、立派な防御線になるんです。
「えっ、アルミホイル?冗談でしょ?」と思われるかもしれません。
でも、これ、本当に効くんです。
アライグマは、アルミホイルの感触や反射する光が苦手なんです。
具体的な使い方は、こんな感じです:
- 庭の周りにアルミホイルを敷き詰める
- 植木鉢の周りをアルミホイルで囲む
- ゴミ箱の蓋にアルミホイルを貼る
- 侵入されやすい場所にアルミホイルのカーテンを作る
「なんか怖いところだな」と思って、近づかなくなるんです。
ただし、注意点もあります。
雨や風に弱いので、定期的に点検と交換が必要です。
また、長期間放置すると、アライグマが慣れてしまう可能性もあります。
「でも、庭中アルミホイルだらけじゃ、見た目が悪くない?」という心配も出てくるでしょう。
確かに、美観を損なう可能性はあります。
でも、一時的な対策としては十分効果的。
徐々に他の方法に切り替えていけばいいんです。
アルミホイル作戦、意外と効果的なんです。
「よーし、今日からアルミホイルマスターになるぞ!」なんて意気込んで、家の周りをキラキラに飾ってみるのはいかがでしょうか。
意外な防御線で、アライグマを撃退できるかもしれませんよ。
音の力を借りて!風鈴で他のアライグマを警戒させる
アライグマ対策に、風鈴を活用するという方法があるんです。この日本の夏の風物詩が、実は優れたアライグマ撃退グッズになるんですよ。
「えっ、風鈴?夏みたいな音じゃん」と不思議に思う方もいるでしょう。
でも、この「チリンチリン」という音が、アライグマにとっては警戒信号になるんです。
風鈴の効果的な使い方は、こんな感じです:
- 庭の木々に風鈴を吊るす
- 侵入されやすい場所の近くに設置する
- 複数の風鈴を使って音の壁を作る
- 風鈴の音色を変えて、慣れを防ぐ
「何かいるぞ!」と警戒心を抱かせるんです。
特に、複数の風鈴を使うと効果的。
まるで音の迷路のようになって、アライグマを混乱させます。
ただし、注意点もあります。
人間にとっても騒音になる可能性があるので、近所迷惑にならないよう気をつけましょう。
また、アライグマが音に慣れてしまう可能性もあるので、定期的に風鈴の位置や種類を変えるのがおすすめです。
「でも、風鈴って夏っぽくない?」という疑問も出てくるかもしれません。
確かに、季節感は気になるところ。
でも、最近は四季を問わず使える風鈴もたくさんあるんです。
むしろ、季節外れの音だからこそ、アライグマを驚かせる効果があるかもしれません。
風鈴作戦、意外と効果的なんです。
「よーし、我が家は風鈴音楽隊だ!」なんて楽しみながら、アライグマ対策をしてみるのはいかがでしょうか。
涼しげな音色で、アライグマを寄せ付けない環境を作れるかもしれませんよ。
匂いで撃退!ペパーミントオイルが新たな対策に
アライグマ対策の新兵器として、ペパーミントオイルが注目されているんです。この爽やかな香りが、実はアライグマを寄せ付けない効果があるんですよ。
「えっ、ミント?お菓子の香りじゃん」と思う方もいるでしょう。
でも、アライグマにとっては強烈な刺激臭なんです。
この「スーッ」とする香りに、アライグマは「ちょっと近寄りがたいな」と感じるわけです。
ペパーミントオイルの効果的な使い方は、こんな感じです:
- 庭の周りに綿球にオイルを染み込ませて置く
- スプレーボトルで水で薄めたオイルを散布する
- 侵入口付近にペパーミントの鉢植えを置く
- ゴミ箱の周りにオイルを数滴たらす
「うわっ、くさい!」とアライグマが思うほどの強烈な香り。
でも、人間にとってはさわやかな香りなので、一石二鳥なんです。
ただし、注意点もあります。
濃すぎる香りは逆効果になる可能性があります。
また、雨や風で香りが飛んでしまうので、定期的な補充が必要です。
「でも、家中ミントの香りじゃ、くらくらしない?」という心配も出てくるでしょう。
大丈夫です。
適度な量を使えば、むしろ空気清浄効果も期待できます。
家族みんなでリフレッシュできるかもしれませんよ。
ペパーミントオイル作戦、新しい対策法として注目されているんです。
「よーし、我が家はミントの森になるぞ!」なんて意気込んで、アライグマ対策を始めてみませんか?
爽やかな香りで、アライグマを寄せ付けない環境を作れるかもしれませんよ。