アライグマがメダカを食べる理由【タンパク質源として重要】池や水辺の生態系を守る3つの対策法

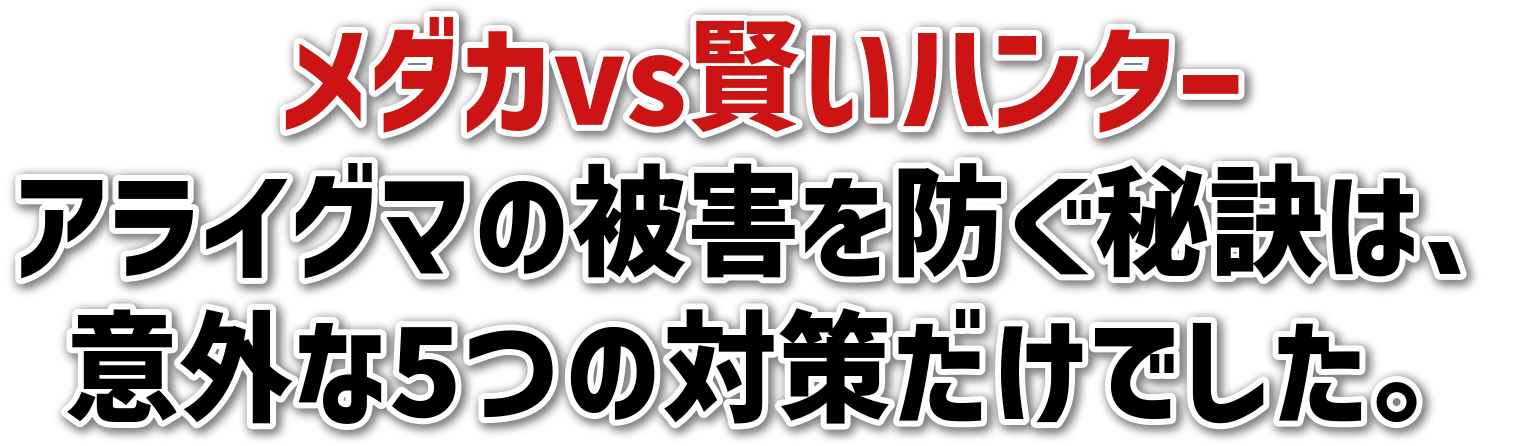
【この記事に書かれてあること】
大切に育てているメダカが、アライグマに食べられてしまう…。- アライグマがメダカを狙う理由と生態系への影響
- メダカへの脅威度を他の捕食者と比較
- 水辺の生態系バランス崩壊の危険性
- アライグマの高い知能と適応力が被害を拡大
- 5つの驚きの対策方法でメダカを守る
そんな悲しい経験をされた方も多いのではないでしょうか?
実は、アライグマがメダカを狙う理由には、驚くべき生態学的な背景があるんです。
メダカを守るためには、アライグマの本能を理解することが不可欠。
この記事では、アライグマがメダカを食べる理由を深掘りしつつ、水辺の生態系への影響にも迫ります。
さらに、意外と簡単にできる5つの対策法もご紹介。
あなたの大切なメダカを、アライグマから守る方法が見つかるはずです。
【もくじ】
アライグマがメダカを狙う理由と水辺の生態系への影響

タンパク質源として「メダカ」が狙われる!
メダカは、アライグマにとって栄養満点のごちそうなんです。アライグマがメダカを狙う最大の理由は、その高タンパク質含有量にあります。
「おや?アライグマって雑食じゃないの?」と思われるかもしれません。
確かにその通りです。
でも、アライグマの食生活の中で、動物性タンパク質はとても重要な位置を占めているんです。
アライグマの体は、常に高いエネルギーを必要としています。
特に、以下の時期にはタンパク質の需要が急増します:
- 子育ての時期
- 冬眠前の体力蓄積期
- 成長期の若いアライグマ
小さくて捕まえやすい上に、栄養価が高い。
「まさに、アライグマにとっての理想的なファストフード!」といえるでしょう。
さらに、メダカは群れで泳ぐ習性があります。
これは、アライグマにとって「一網打尽」のチャンス。
「わーい、おいしいビュッフェだ!」とばかりに、一度に多くのメダカを食べることができるんです。
このように、メダカはアライグマの食生活において、手軽で栄養価の高いタンパク質源として重要な役割を果たしているのです。
「メダカさん、アライグマにとってはあなたが最高のごちそうなんです。ごめんね。」
アライグマの「高い知能」が餌の確保を可能に
アライグマの知能の高さは、メダカ捕獲の成功率を格段に上げています。その知能は犬並みと言われ、問題解決能力や記憶力に優れているんです。
まず、アライグマの手先の器用さに注目です。
前足は、まるで人間の手のよう。
「ちょいちょい」と水中を探り、メダカを巧みに捕まえます。
この器用さは、高い知能と相まって、効率的な捕食を可能にしているんです。
次に、学習能力の高さ。
一度成功した捕食方法を、しっかり記憶します。
- メダカが多く集まる場所
- 餌やりの時間帯
- 池の構造や深さ
「ふむふむ、この時間にここに来れば、おいしいメダカが食べられるぞ」と、頭の中でスケジュールを立てているかのよう。
さらに、アライグマは状況に応じて戦略を変える柔軟性も持っています。
例えば、人間が対策を講じても、すぐに新たな侵入経路を見つけ出すんです。
「へへへ、こっちから入ればバレないぞ」なんて、ずる賢く考えているのかも。
この高い知能は、アライグマの生存戦略の要となっています。
自然環境だけでなく、人間の作り出した環境にも素早く適応できるのは、この知能のおかげなんです。
結果として、アライグマの高い知能は、メダカにとっては大きな脅威になっています。
「頭のいい敵には要注意!」メダカを守るには、アライグマの知能を上回る対策が必要になるというわけです。
水辺での採餌行動「夜間2〜3時間」が被害のピーク
アライグマの水辺での採餌行動は、主に夜間の2〜3時間に集中します。この時間帯がメダカにとって最も危険な「ピークタイム」なんです。
夜行性のアライグマは、日が沈むとお腹が空いてきます。
「さあ、夜ごはんの時間だ!」と活動を始めるのです。
特に注意が必要なのは、以下の2つの時間帯:
- 日没後2〜3時間
- 夜明け前の2〜3時間
暗闇に紛れて、こっそりと水辺にやってくるんです。
アライグマの夜間視力は人間の8倍以上。
真っ暗な中でも、メダカの動きをはっきりと捉えることができます。
「キラリ」と光る水面下の動きを見逃しません。
さらに、アライグマは水中での採餌に適した体の構造を持っています。
前足の感覚が鋭敏で、水中の物体を器用に探り当てられるんです。
「ざぶん」と音を立てずに、静かに水に入ります。
この夜間の採餌行動は、季節によっても変化します。
- 春から夏:活発に水辺で採餌
- 秋:冬眠に備えて食欲旺盛に
- 冬:活動が鈍るものの完全に休眠はしない
「子どもたちのためにも、たくさん食べなきゃ」と必死なんです。
このように、アライグマの夜間の採餌行動を理解することが、メダカを守るための第一歩。
「夜の静けさに潜む危険」を意識して、適切な対策を講じることが大切です。
メダカ以外の水生生物も「被害対象」に
アライグマの食欲は、メダカだけでは収まりません。水辺の生態系全体が、その旺盛な食欲の的になっているんです。
アライグマの食事メニューは、実に多様。
水辺で見つけられる様々な生き物が、その対象になります。
例えば:
- カエル:「ぴょんぴょん」跳ねる姿が格好の獲物に
- ザリガニ:「カチカチ」とした甲羅も、器用な手で簡単に剥がします
- 水生昆虫:小さくても栄養価の高い、おいしいおやつ
- 小魚:メダカ以外の小魚も、もちろん大歓迎
- 貝類:殻を器用に割って、中身をすくい取ります
「いろいろ食べられるから、生きていけるんだ」というアライグマの生存戦略が、皮肉にも他の生物の生存を脅かしています。
特に、在来種への影響が深刻です。
日本の水辺の生態系は、長い時間をかけて形成されてきました。
そこに突然、強力な捕食者であるアライグマが現れたのです。
在来種は、このような捕食者に対する防御機能を持っていません。
「えっ、こんな強い敵がいるの?」と、なすすべもなく捕食されてしまうのです。
さらに、アライグマの捕食は、食物連鎖のバランスを崩します。
例えば:
- 小魚が減少→それを餌にしていた鳥類も減少
- 水生昆虫が減少→水質浄化の機能が低下
- カエルが減少→害虫の天敵が減り、農作物被害が増加
「一つの種の増加が、こんなにも大きな影響を与えるなんて」と、その影響の大きさに驚かされます。
メダカを守ることは、すなわち水辺の生態系全体を守ることにつながるのです。
アライグマ対策は、単にメダカだけの問題ではないという認識が大切です。
アライグマの捕食で「生態系バランス崩壊」の危険性
アライグマの旺盛な食欲は、水辺の生態系バランスを大きく揺るがしています。その影響は、私たちの想像以上に深刻なんです。
まず、アライグマの捕食によって、在来種の個体数が急激に減少します。
例えば:
- メダカの激減:「あれ?昨日まで泳いでいたのに…」
- カエルの姿が見えなくなる:「蛙の鳴き声が聞こえなくなった…」
- 水生昆虫の減少:「水面に虫が浮かんでいないな…」
でも、生態系は複雑に絡み合った糸のよう。
一箇所が崩れると、全体のバランスが崩れてしまうんです。
その結果、次のような連鎖反応が起こります:
- 食物連鎖の乱れ:小魚が減ると、それを餌にしていた鳥類も減少
- 水質の悪化:水生昆虫や貝類が減ると、水の浄化機能が低下
- 植生の変化:水草を食べる生物が減ると、特定の水草が異常繁殖
- 害虫の増加:カエルなどの天敵が減ると、蚊やハエが増加
「あれ?ちょっとおかしいな」と気づいた時には、もう手遅れになっている可能性があるんです。
特に注意が必要なのは、「生態系の復元力」が失われてしまうこと。
自然界には、ある程度の変化を吸収する力があります。
でも、アライグマの影響があまりにも急激で大きいため、その復元力を超えてしまうのです。
「ごめん、もう立ち直れない…」と、生態系が悲鳴を上げているようです。
このような生態系バランスの崩壊は、最終的に人間の生活にも影響を及ぼします。
水質の悪化や害虫の増加は、直接的に私たちの健康や生活環境を脅かすことになるのです。
だからこそ、アライグマの捕食問題は深刻に受け止める必要があります。
「メダカだけの問題」ではなく、水辺の生態系全体、そして私たち人間の生活にまで関わる大きな問題なんです。
アライグマvsその他の捕食者!メダカへの脅威を比較

アライグマvsカワウソ「適応力の差」に注目
アライグマとカワウソ、どちらがメダカにとって大きな脅威でしょうか?結論から言うと、アライグマの方がより危険なんです。
まず、適応力の違いに注目してみましょう。
アライグマは陸上でも水中でも活動できる「万能選手」。
一方、カワウソは水辺に特化した生活をしています。
「えっ、じゃあカワウソの方が水中のメダカを捕まえるのが上手なんじゃない?」
そう思われるかもしれません。
でも、実はそうとも限らないんです。
アライグマの特徴を見てみましょう:
- 前足が器用で、まるで小さな手のよう
- 夜行性で、人間の目を避けて行動できる
- 木登りが得意で、高い場所からメダカを狙える
さらに、アライグマは人間の生活圏にも簡単に適応してしまいます。
「ごみ箱あさり名人」なんて呼ばれるくらい。
この適応力の高さが、メダカ飼育者にとっては大きな悩みの種になっちゃうんです。
カワウソが「水辺のスペシャリスト」だとすれば、アライグマは「どこでも生きられるジェネラリスト」。
この違いが、メダカへの脅威度の差につながっているというわけです。
「うちの庭の池にカワウソが来るよりも、アライグマが来る方が怖いかも…」
そう感じる方も多いのではないでしょうか。
アライグマの高い適応力を知ることで、より効果的な対策を考えることができますよ。
アライグマvsサギ類「昼夜を問わない活動」が脅威
アライグマとサギ類、どちらがメダカにとって厄介な相手でしょうか?実は、アライグマの方がより大きな脅威なんです。
その理由は、昼夜を問わない活動にあります。
サギ類は主に昼間に活動します。
朝日とともにやってきて、夕方には帰っていく。
そんなイメージですよね。
一方、アライグマはどうでしょう?
- 夜行性だけど、昼間も活動することがある
- 人間の生活リズムに合わせて行動パターンを変える
- 年中無休で活動し、冬眠もしない
「ええっ、休みなしなの!?」って驚きますよね。
サギ類の場合、日中に目撃されやすいので対策を立てやすい面があります。
でも、アライグマは「こっそり」「こそこそ」とやってくるので、被害に気づくのが遅れがちなんです。
さらに、アライグマの食性の幅広さも問題です。
サギ類が魚中心の食生活なのに対し、アライグマは果物や昆虫、小動物まで何でも食べちゃいます。
「おや?メダカがいない。じゃあ、池の周りの果物でも食べよう」なんて具合に。
これは水辺の生態系全体に大きな影響を与えます。
メダカだけでなく、カエルやザリガニ、水生昆虫まで、アライグマの食卓に上ってしまうんです。
「昼間はサギ、夜はアライグマに気をつけなきゃ!」
そんな風に考えると、アライグマ対策の重要性がよくわかりますよね。
メダカを守るためには、昼夜を問わない対策が必要になるというわけです。
アライグマvs外来魚「陸上生態系への影響」も
アライグマと外来魚、どちらが水辺の生態系に深刻な影響を与えるでしょうか?実は、アライグマの方がより広範囲に影響を及ぼすんです。
その理由は、陸上生態系への影響にあります。
外来魚の影響は主に水中に限られます。
でも、アライグマはどうでしょう?
- 水辺と陸地を行き来する「二足のわらじ」
- 木に登って鳥の卵を狙うこともある
- 農作物を荒らすことも
「えっ、そんなに広範囲に!?」って驚きませんか?
例えば、こんな連鎖反応が起こります:
- アライグマがメダカを食べ尽くす
- メダカを餌にしていた鳥が減少
- その鳥が食べていた陸上の昆虫が増加
- 昆虫の増加で特定の植物の受粉が過剰に
外来魚の場合、釣り人が「ぽいっ」と放流したり、水槽の魚を「じゃぼん」と川に捨てたりすることが問題になります。
でも、アライグマは自力で移動して分布を広げていくんです。
さらに、アライグマは高い学習能力を持っています。
「今日はここで餌が見つかったぞ」「あの家の裏庭に美味しそうな果物がなってる」なんて、どんどん新しい食料源を見つけていくんです。
これは、メダカを守る上で大きな課題になります。
「池にネットを張ったから安心」なんて思っていても、アライグマはどこからともなく現れて、思わぬ被害をもたらすかもしれません。
「水中だけじゃなく、陸上まで気をつけなきゃいけないなんて大変!」
そう思われるかもしれません。
でも、アライグマの生態を知ることで、より効果的な対策を立てることができるんです。
メダカを守るということは、実は水辺と陸上の生態系全体を守ることにつながっているんですね。
アライグマvs在来種「食物連鎖の乱れ」に警鐘
アライグマと在来種の捕食者、どちらがメダカにとって大きな脅威でしょうか?実は、アライグマの方がより深刻な問題を引き起こすんです。
その理由は、食物連鎖の乱れにあります。
在来種の捕食者は、長い時間をかけて地域の生態系と調和してきました。
でも、アライグマはどうでしょう?
- 日本の生態系に突然現れた「不法侵入者」
- 在来種が想定していない捕食者
- 驚異的な繁殖力で個体数を急増させる
「えっ、そんなに影響が大きいの?」って思いますよね。
例えば、こんな連鎖反応が起こります:
- アライグマがメダカを大量に食べる
- メダカが減少し、メダカの天敵(在来種)も餌不足に
- 在来種の捕食者が減少し、別の生物が増加
- 増加した生物が植物を過剰に食べ、植生が変化
在来種の捕食者なら、メダカの個体数が減れば自然と捕食圧も下がります。
でも、アライグマは「何でも屋さん」。
メダカがいなくなっても、他の食べ物にすぐに切り替えちゃうんです。
さらに、アライグマは人間の生活圏にも簡単に適応します。
「ごみ箱あさりの名人」なんて呼ばれるくらい。
これが、さらなる個体数増加につながるんです。
「ええっ、ゴミ箱もあさるの!?」って驚きですよね。
人間の食べ残しで栄養をつけたアライグマが、さらにメダカを狙いに来る。
そんな悪循環も起こりかねません。
この食物連鎖の乱れは、メダカだけでなく、水辺の生態系全体に大きな影響を与えます。
「メダカを守る」ということは、実は地域の生態系全体を守ることにつながっているんです。
アライグマ対策は、単にメダカを守るだけでなく、私たちの身近な自然環境を守ることにもなるんですね。
「メダカのために頑張ろう!」そんな気持ちで対策に取り組んでみてはいかがでしょうか。
アライグマvs人間「駆除と保護のジレンマ」
アライグマと人間、この対立はメダカにとってどんな影響があるのでしょうか?実は、駆除と保護のジレンマが大きな問題になっているんです。
人間がアライグマ対策に乗り出すと、こんな状況が生まれます:
- アライグマを駆除すれば生態系が回復?
- でも、動物愛護の観点から批判の声も
- 駆除しても、すぐに別のアライグマが侵入
アライグマ駆除のメリットとデメリットを見てみましょう:
- メリット:メダカへの直接的な被害が減少
- メリット:在来種の回復の可能性
- デメリット:一時的な効果に終わる可能性大
- デメリット:駆除方法によっては別の環境問題を引き起こす
でも、アライグマの生態を考えると、単純な駆除だけでは問題解決にならないんです。
例えば、ある地域でアライグマを駆除したとします。
するとどうなるでしょう?
「よっしゃ、これでメダカは安全だ!」
...なんて喜んでいたら、隣の地域からまたアライグマがやってきちゃうんです。
さらに、アライグマは高い学習能力を持っています。
「あそこは危ないぞ」「こっちの方が餌が多いぞ」なんて、どんどん新しい生存戦略を学んでいくんです。
「まるで頭脳戦みたい!」って感じですよね。
このジレンマを解決するには、地域全体で協力して総合的な対策を立てる必要があります。
例えば:
- 餌となるものを減らす環境整備
- 侵入経路を塞ぐ物理的対策
- 地域住民への啓発活動
そう、その通りなんです。
メダカを守るということは、実は人間とアライグマの共存方法を考えることにもつながっています。
難しい問題ですが、知恵を絞って解決策を見つけていく。
そんな姿勢が大切なんですね。
メダカを守る!アライグマ対策5つの驚きの方法

池の周りに「ハーブを植える」意外な効果
メダカを守るために、池の周りにハーブを植えるという意外な方法があるんです。これ、実はアライグマ撃退に驚くほど効果的なんですよ。
「えっ、ただの植物でアライグマが寄ってこなくなるの?」って思いますよね。
実は、アライグマは特定の強い香りが苦手なんです。
ハーブの中でも特に効果があるのは以下のようなものです:
- ミント:さわやかな香りがアライグマを遠ざける
- ラベンダー:リラックス効果のある香りがアライグマには不快
- ローズマリー:強い香りがアライグマの嗅覚を刺激
- タイム:独特の香りがアライグマを混乱させる
さらに、ハーブを植えることには他にもメリットがあります。
例えば:
- 見た目がきれいで庭の景観が良くなる
- 虫よけ効果もあるので、他の害虫対策にも
- 料理に使えるので一石二鳥
ただし、注意点もあります。
ハーブは強い日差しと水はけの良い土壌を好むので、池の周りの環境に合わせて適切な場所を選びましょう。
また、ハーブが池に落ちて水質に影響を与えないよう、適度な距離を保つことも大切です。
この方法、見た目も香りも楽しめて、なおかつアライグマ対策になるなんて、まさに「いいことづくめ」ですよね。
メダカを守りながら、庭の雰囲気も良くなる。
そんな素敵な効果が期待できるんです。
さあ、あなたも早速、ハーブガーデンづくりを始めてみませんか?
風車設置で「動きと音」でアライグマを威嚇
風車を設置して、その動きと音でアライグマを威嚇する。これ、意外と効果的な対策方法なんです。
「えっ、ただの風車で?」って思いますよね。
でも、アライグマは予測できない動きや突然の音が苦手なんです。
風車はまさにそんな特徴を持っているんです。
風車の効果は主に2つあります:
- 視覚的効果:くるくる回る姿がアライグマを不安にさせる
- 聴覚的効果:風で発生する音がアライグマを警戒させる
「うわっ、なんだあれ!」って感じでしょうか。
風車の選び方のポイントはこんな感じです:
- 金属製のものを選ぶ(キラキラ光って効果的)
- 複数の羽根があるもの(動きが複雑になる)
- サイズは大きめのものがおすすめ(存在感アップ)
「風車だらけの庭になっちゃうかも...」なんて心配する必要はありません。
strategicに置くことが大切なんです。
例えば、こんな風に設置するといいかもしれません:
「池の北側に1つ、南側に1つ。そして、アライグマが来そうな経路に1つ。」
風車には、アライグマ対策以外にもメリットがあります。
例えば:
- 庭の装飾になる
- 風向きがわかる
- 子供の観察学習に良い
強風の日は風車の音が大きくなりすぎて、近所迷惑にならないよう気をつけましょう。
また、定期的な手入れも忘れずに。
「キーキー」という音がしたら、油を差すタイミングです。
この方法、見た目も楽しめて、なおかつアライグマ対策になるなんて、まさに「一石二鳥」ですよね。
メダカを守りながら、庭の雰囲気も良くなる。
そんな素敵な効果が期待できるんです。
さあ、あなたも風車でアライグマ撃退、試してみませんか?
古いCDで「光の反射」アライグマを混乱させる
古いCDを使って光を反射させ、アライグマを混乱させる。これ、実は驚くほど効果的な対策方法なんです。
「えっ、捨てようと思っていた古いCDが役立つの?」って驚きますよね。
実は、アライグマは予期せぬ光の動きに非常に敏感なんです。
CDの反射光は、まさにアライグマを混乱させる「秘密兵器」なんです。
CDの効果は主に2つあります:
- 視覚的刺激:不規則に動く光の反射がアライグマを驚かせる
- 音響効果:風で揺れるCDが発する微かな音も効果的
「うわっ、なんだこれ!逃げろ〜」って感じでしょうか。
CDの設置方法のポイントはこんな感じです:
- 池の周りの木の枝やフェンスに吊るす
- 高さを変えて複数設置する(立体的な防御ライン)
- 風で自由に回転するように設置する
- 月光や街灯の光が当たる位置を選ぶ
適度な数と配置が大切です。
例えば:
「池の周り3〜4か所に2〜3枚ずつ。アライグマの侵入経路に特に注意して。」
CDには、アライグマ対策以外にも意外な効果があります:
- 鳥よけにもなる(果樹園の方にもおすすめ)
- 日中は虹色に輝いて庭の装飾に
- 環境に優しいリサイクル方法
強風の日はCDが飛ばされないよう、しっかり固定しましょう。
また、近隣の住宅に光が反射して迷惑にならないよう、角度調整も忘れずに。
この方法、コストほぼゼロで始められて、なおかつ効果的なアライグマ対策になるなんて、まさに「一石二鳥」ですよね。
捨てようと思っていたCDが、メダカの命を守る大切な道具に変身。
そんな素敵な「変身」が期待できるんです。
さあ、あなたも古いCDでアライグマ撃退、試してみませんか?
ペットボトルの波紋で「警戒心」を刺激
ペットボトルを使って池に波紋を作り、アライグマの警戒心を刺激する。これ、実は意外と効果的な対策方法なんです。
「えっ、ただのペットボトルで?」って思いますよね。
でも、アライグマは水面の不自然な動きにとても敏感なんです。
ペットボトルが作り出す波紋は、まさにアライグマの警戒心を刺激する「隠れた味方」なんです。
ペットボトルの波紋の効果は主に2つあります:
- 視覚的効果:不規則な波紋がアライグマを不安にさせる
- 聴覚的効果:水音がアライグマを警戒させる
「ヒエッ、危険かも...」って感じでしょうか。
ペットボトルの設置方法のポイントはこんな感じです:
- 500mlくらいのペットボトルを使う
- ボトルの下3分の1くらいに小さな穴をたくさん開ける
- 中に小石を入れて音を出す工夫も効果的
- ボトルのふたはしっかり閉める
「うわっ、ペットボトルだらけの池になっちゃう...」なんて心配する必要はありません。
池の大きさに応じて2〜3個程度で十分効果があります。
例えば、こんな風に設置するといいかもしれません:
「池の北側に1つ、南側に1つ。そして、アライグマが来そうな方向に1つ。」
ペットボトルの波紋には、アライグマ対策以外にもメリットがあります:
- 水面に酸素を取り込む効果がある
- 蚊の発生を抑制する
- 見た目も涼しげで夏の庭の雰囲気作りに
ペットボトルが藻で覆われたり、穴が詰まったりしないよう、定期的な清掃が必要です。
また、強風の日はペットボトルが流されないよう、紐などで固定しましょう。
この方法、身近なもので始められて、なおかつ効果的なアライグマ対策になるなんて、まさに「一石二鳥」ですよね。
捨てようと思っていたペットボトルが、メダカの命を守る大切な道具に変身。
そんな素敵な「変身」が期待できるんです。
さあ、あなたもペットボトルでアライグマ撃退、試してみませんか?
唐辛子スプレーで「接近を防ぐ」自然な忌避剤
唐辛子スプレーを使って、アライグマの接近を防ぐ。これ、実は自然で効果的な忌避方法なんです。
「えっ、キッチンにある唐辛子でいいの?」って思いますよね。
その通り、身近な食材が大活躍するんです。
アライグマは強い刺激臭が苦手で、特に唐辛子の辛味成分には敏感なんです。
唐辛子スプレーの効果は主に2つあります:
- 嗅覚への刺激:強い香りがアライグマを寄せ付けない
- 味覚への刺激:辛味成分が食べる気をなくさせる
もし触れてしまっても、その辛さで「二度と来るもんか!」ってなっちゃうわけです。
唐辛子スプレーの作り方と使い方のポイントはこんな感じです:
- 唐辛子パウダーを水で薄めて作る(比率は1:10くらい)
- ペットボトルなどの容器に入れて、スプレーノズルを付ける
- 池の周りの地面や植物にスプレーする
- 雨が降ったら再度スプレーする
薄めて使うので、目立つことはありません。
散布する場所は、例えばこんな感じです:
「池の周りの地面、アライグマが通りそうな小道、庭の入り口など」
さらに、唐辛子スプレーには他のメリットもあります:
- 他の害獣対策にも効果的
- 環境に優しい自然由来の材料
- 人体に害が少ない(ただし、目に入れないよう注意)
風向きに気をつけて散布しましょう。
自分に掛からないように要注意です。
また、愛犬や愛猫がいる家庭では、ペットが触れない場所を選んで使用してください。
この方法、台所にあるもので簡単に始められて、なおかつ効果的なアライグマ対策になるなんて、まさに「一石二鳥」ですよね。
普段は料理に使う唐辛子が、メダカの命を守る大切な味方に変身。
そんな素敵な「変身」が期待できるんです。
さあ、あなたも唐辛子スプレーでアライグマ撃退、試してみませんか?
辛い思いをするのはアライグマだけ、あなたのメダカは安心して泳げるはずです。