アライグマは何を食べる?【雑食性で80種類以上】自然環境での食生活と被害対策のヒントを解説

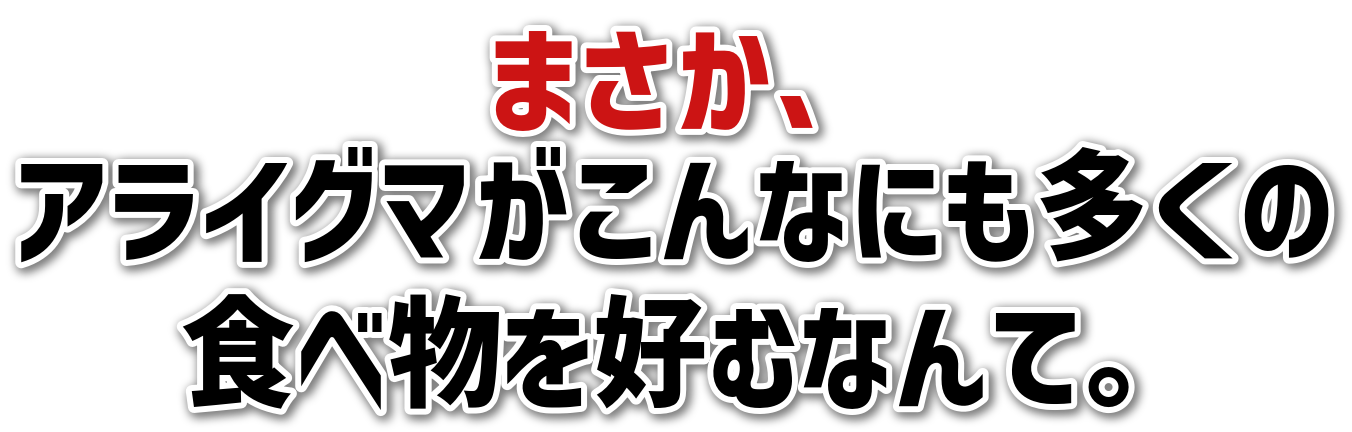
【この記事に書かれてあること】
アライグマの食生活、気になりますよね。- アライグマは果物や小動物など80種類以上を食べる雑食性
- 季節によって食性が変化し、冬は人里での被害が増加
- アライグマの食性が在来種との競合や生態系破壊を引き起こす
- 農作物被害は果樹園が特に狙われやすい
- アライグマの食性を理解した効果的な対策が被害防止のカギ
実は、このかわいらしい見た目の動物、驚くほど多様な食性を持っているんです。
果物からカエルまで、なんと80種類以上もの食べ物を食べちゃうんです!
でも、この雑食性が時として大きな問題を引き起こすことも。
季節によって変わる食べ物の好みや、それに伴う被害の実態を知れば、効果的な対策が立てられるかも。
さぁ、アライグマの食卓の秘密に迫ってみましょう!
【もくじ】
アライグマは何を食べる?雑食性の食性を知ろう

アライグマの主食は「果物」と「小動物」!80種類以上を摂取
アライグマは驚くほど多様な食べ物を食べる雑食性の動物です。なんと80種類以上もの食べ物を摂取するんです!
「えっ、そんなにたくさん食べるの?」と驚かれるかもしれませんね。
実は、アライグマの食事メニューはとってもバラエティ豊か。
主に果物と小動物を好んで食べますが、他にもいろいろな食べ物に手を出します。
具体的には、こんな感じです:
- 果物:リンゴ、ブドウ、イチゴ、スイカなど
- 小動物:カエル、トカゲ、ネズミ、鳥の卵など
- 昆虫:カブトムシ、バッタ、ミミズなど
- 魚:小魚、カニ、エビなど
- 植物:木の実、草、野菜など
「まるで小さな人間みたい!」と思うほど、器用に食べ物を操ります。
この多様な食性が、アライグマの生存能力の高さにつながっています。
食べ物が少ない環境でも、なんとか生き延びられるわけです。
でも、この特徴が人間との軋轢を生む原因にもなっているんですよ。
野生のアライグマが好む食べ物ランキング「ベスト5」
野生のアライグマは、ある食べ物に特に目がないんです。その好物ランキング「ベスト5」をご紹介しましょう!
1位:甘い果物
アライグマは甘党なんです。
特に熟した果物が大好物。
「もぎたてのリンゴ、おいしそう〜」とでも言いたげに、果樹園に集まってきます。
2位:小魚
川や池の近くでは、ぴちぴち跳ねる小魚を器用な手で捕まえます。
「今日のおかずはお魚だぁ」とでも考えているのかも?
3位:鳥の卵
巣を見つけると、「いただきま〜す」と卵を器用に割って食べてしまいます。
栄養満点の卵は、アライグマにとって最高のごちそうなんです。
4位:昆虫類
「プチプチ、サクサク」と音を立てながら、昆虫を楽しそうに食べます。
タンパク質たっぷりで、おやつ代わりになるんですね。
5位:小型哺乳類
ネズミやモグラなどの小動物も、アライグマの重要な栄養源。
「今日はねずみハンターだぞ」と意気込んで狩りをします。
この多彩な食性が、アライグマの生態系での役割を複雑にしているんです。
でも、同時に人間との衝突も引き起こしちゃうんですよね。
人里に出没するアライグマの食べ物は「生ゴミ」が増加中!
最近、街に出没するアライグマが増えています。そして驚くべきことに、彼らの食事メニューに「生ゴミ」が急増中なんです!
「えっ、ゴミを食べるの?」と思われるかもしれません。
でも、アライグマにとっては人間の残飯も立派な「ごちそう」なんです。
なぜ生ゴミを食べるようになったのでしょうか?
理由は主に3つあります:
- 簡単に手に入る:ゴミ箱をあさるだけで食べ物が手に入るんです。
- 栄養が豊富:人間の食べ残しは、意外と栄養価が高いんですよ。
- 美味しい:人間の食べ物には塩分や糖分が多く含まれていて、アライグマの口に合うんです。
- ゴミ箱をひっくり返す
- ゴミ袋を破って中身をあさる
- レストランの裏口で残飯を探す
これは大きな問題になっているんです。
なぜなら、ゴミ散らかしの原因になるだけでなく、アライグマが人里に慣れすぎてしまうからです。
結果として、アライグマと人間のトラブルが増加。
「困ったものだなぁ」と頭を抱える自治体も多いんです。
アライグマの食性と「季節変化」の関係!冬は要注意
アライグマの食べ物は、季節によってガラッと変わるんです。季節ごとの食性変化を知ることで、効果的な対策が立てられますよ。
春:新芽や若葉が主食
芽吹きの季節、アライグマは「春の味覚を楽しもう!」とばかりに、新芽や若葉を好んで食べます。
この時期は植物性の食べ物が中心になります。
夏:果物がたっぷり
「あま〜い果物がいっぱい!」とアライグマも大喜び。
夏は果樹園や家庭菜園が被害に遭いやすい季節です。
虫も多いので、タンパク質源として昆虫類もよく食べます。
秋:冬に備えて栄養チャージ
「冬に備えて、たくさん食べなきゃ」と、アライグマは食欲旺盛になります。
木の実や熟した果物を中心に、脂肪分の多い食べ物を好んで食べるようになります。
冬:人里での被害に要注意!
寒い冬は、野生の食べ物が少なくなります。
そこでアライグマは「人間の住む場所にエサがありそう」と、人里に出没する機会が増えるんです。
この時期は特に、ゴミあさりや家屋侵入などの被害が増加します。
このように、アライグマの食性は季節によってくるくる変わります。
対策を立てる時は、「今の季節はアライグマが何を食べているのかな?」と考えることが大切。
季節に合わせた対策を取ることで、被害を効果的に防ぐことができるんですよ。
アライグマの食性が引き起こす問題と被害

アライグマvs在来種!食物連鎖のバランスが崩れる危険性
アライグマの食性は、地域の生態系に大きな影響を与えています。在来種との競合や捕食により、食物連鎖のバランスが崩れる危険性が高まっているんです。
「え?アライグマって、そんなに大変な問題を引き起こしているの?」と驚かれるかもしれませんね。
実は、アライグマの旺盛な食欲と多様な食性が、生態系に次のような影響を与えているんです:
- 在来種の餌を奪う:アライグマは同じ食べ物を好む在来種と競合します
- 小動物を捕食する:カエルやトカゲなどの小動物を食べてしまいます
- 鳥の卵を狙う:巣を荒らして卵を食べるので、鳥の繁殖に影響します
- 植物の種子を食べる:種子の分散を妨げ、植生に変化をもたらします
アライグマは食物連鎖の中で、中位捕食者として位置しています。
つまり、小さな動物を食べる一方で、大きな捕食者に食べられる立場なんです。
でも、日本にはアライグマを捕食する動物があまりいないため、その数が増えすぎてしまうんですね。
「ぎゃー!このままじゃ大変なことになっちゃう!」そうなんです。
アライグマの食性を理解し、適切な対策を取ることが、生態系のバランスを守るためにとても大切なんです。
農作物被害と食性の関係!果樹園が狙われやすい理由
アライグマの食性は、農作物に深刻な被害をもたらしています。特に果樹園が狙われやすいんです。
なぜでしょうか?
まず、アライグマは甘いものが大好き。
果物の中でも特に糖度の高いものを好んで食べるんです。
「まるで甘いもの好きの人間みたい!」と思いませんか?
果樹園が狙われやすい理由は、こんな感じです:
- 栄養価が高い:果物は栄養が豊富で、アライグマの体力回復に最適
- 手に入れやすい:木に実る果物は、地面の作物より取りやすい
- まとまった量がある:一か所で大量の食べ物が手に入る
- 柔らかくて食べやすい:鋭い歯と器用な手で、簡単に食べられる
- 香りが強い:甘い香りに誘われて、遠くからやってくる
実際に被害を受けやすい果物には、ブドウ、イチゴ、スイカ、メロン、リンゴなどがあります。
これらは糖度が高く、アライグマにとっては最高のごちそうなんです。
被害の様子はこんな感じです。
「ガリガリ、ムシャムシャ」と音を立てながら、熟した果実を次々と食べていきます。
半分かじられた果実や、木の下に落ちた食べかすが散らばっているのが特徴的です。
農家さんにとっては大打撃。
「せっかく育てた果物が…」と嘆く声が聞こえてきそうです。
でも、がっかりしないでください!
アライグマの食性を理解することで、効果的な対策を立てることができるんです。
例えば、収穫直前の果実を重点的に守ったり、アライグマの嫌いな匂いを利用したりする方法があります。
アライグマの食性と人間の生活圏!ゴミ箱荒らしに要注意
アライグマの食性は、人間の生活圏にも大きな影響を与えています。特に注意が必要なのが、ゴミ箱荒らしなんです。
「えっ、ゴミ箱まで荒らされちゃうの?」と驚く声が聞こえてきそうですね。
実は、アライグマにとって、人間の残飯はとってもおいしい食べ物なんです。
ゴミ箱荒らしが起こる理由は、こんな感じです:
- 食べ物の匂いに誘われる:鋭い嗅覚で、ゴミの中の食べ物を感知します
- 栄養価の高い食べ物がある:人間の食べ残しは、意外と栄養満点なんです
- 簡単に手に入る:ゴミ箱をひっくり返すだけで、食べ物が手に入ります
- 安全な場所にある:人家の近くは、他の動物から身を守りやすいんです
1. まず、ゴミの匂いを嗅ぎつけます。
「むしゃむしゃ、おいしそう〜」
2. 次に、ゴミ箱に近づいて、中をのぞき込みます。
「何かあるかな〜?」
3. そして、器用な手でゴミ箱のふたを開けたり、ひっくり返したりします。
「よいしょ!」
4. 最後に、食べ物を探してゴミをあさります。
「ガサガサ、ゴソゴソ」
結果、翌朝には悲惨な光景が…。
「わー!ゴミが散らかってる!」なんて経験をした人も多いのではないでしょうか。
これは単なる迷惑行為ではありません。
ゴミを食べることで、アライグマが人里に慣れてしまい、さらなる被害を引き起こす可能性があるんです。
また、ゴミを食べることで病気にかかるリスクも。
でも、大丈夫。
アライグマの食性を理解すれば、効果的な対策が立てられます。
例えば、ゴミ箱にしっかりとしたふたをつけたり、ゴミ出しの時間を工夫したりすることで、被害を減らすことができるんです。
アライグマvsタヌキ!日本の生態系で起こる食物競争
アライグマとタヌキ、似ているようで実は大違い。この2つの動物の間で、日本の生態系における食物競争が起きているんです。
「えっ、アライグマとタヌキが争ってるの?」と驚かれるかもしれませんね。
実は、この2つの動物は似たような環境で生活しているため、食べ物を巡って競合しているんです。
アライグマとタヌキの食性の違いは、こんな感じです:
- アライグマ:より肉食性が強く、小動物や魚を積極的に捕食します
- タヌキ:植物性の食べ物への依存度が高く、雑食性ですが植物食が中心です
まず、アライグマの方が積極的に小動物を捕食するため、カエルやトカゲなどの小動物の数が減少してしまいます。
「ガブッ、パクッ」とアライグマに食べられてしまうんです。
一方、タヌキは主に植物性の食べ物を中心に食べるため、直接的な捕食の影響は比較的小さいです。
「もぐもぐ、おいしい木の実だなぁ」なんて感じでしょうか。
でも、両者とも果実や昆虫も食べるため、これらの食べ物を巡って競争が起きています。
特に、秋の実りの季節には激しい競争になるんです。
さらに、アライグマの方が体格が大きく、攻撃的な性格のため、タヌキを追い出してしまうことも。
「ここは俺の縄張りだ!」とばかりに、タヌキの生息地を奪ってしまうんです。
結果として、タヌキの生息地が狭められ、個体数が減少する可能性があります。
「タヌキさん、大丈夫かな…」と心配になりますよね。
この問題に対処するには、アライグマの個体数管理と、タヌキの生息地保護が重要です。
アライグマの食性を理解し、適切な対策を取ることで、日本の生態系のバランスを守ることができるんです。
アライグマの食性を利用した効果的な対策方法

果物の香りに注目!「誘引剤」を使った捕獲テクニック
アライグマの大好物である果物の香りを利用して、効果的な捕獲ができるんです。この「誘引剤」を使った捕獲テクニックは、アライグマ対策の強い味方になりますよ。
「えっ、果物の香りでアライグマを捕まえられるの?」と思われるかもしれませんね。
実は、アライグマの鋭い嗅覚を逆手に取ることで、効果的な捕獲が可能になるんです。
具体的な誘引剤の使い方は、こんな感じです:
- 甘い果物の香りがする市販の誘引剤を用意する
- 捕獲箱の中に誘引剤を設置する
- 捕獲箱の周りにも果物の切れ端を少量撒く
- アライグマが活動する夜間に設置する
- 定期的に見回って、捕獲状況を確認する
この方法のポイントは、アライグマの好みに合わせた香りを使うことなんです。
特に効果的な果物の香りには、次のようなものがあります:
- スイカ
- メロン
- イチゴ
- リンゴ
- バナナ
でも、注意点もありますよ。
誘引剤を使う際は、近所の人や他の動物に迷惑がかからないよう配慮が必要です。
「ご近所トラブルは避けたいですよね」という気持ち、わかります。
この方法を使えば、アライグマを効果的に捕獲できる可能性が高まります。
ただし、捕獲後の対応は自治体のルールに従うことを忘れずに。
「ちゃんとルールを守らなきゃ」ですよね。
アライグマの嫌いな「香り」で撃退!ハーブを活用した対策法
アライグマが苦手な香りを利用して、効果的に撃退する方法があるんです。特にハーブを活用した対策法が注目されています。
「へぇ、ハーブでアライグマを追い払えるの?」と驚かれるかもしれませんね。
実は、アライグマの鋭敏な嗅覚は、特定の香りに対して非常に敏感なんです。
アライグマが嫌う香りのハーブには、次のようなものがあります:
- ミント
- ローズマリー
- ラベンダー
- セージ
- タイム
- 庭の周りにハーブを植える
- ハーブオイルを水で薄めて、庭や家の周りに散布する
- 乾燥ハーブを袋に入れて、侵入されやすい場所に吊るす
- ハーブティーバッグを庭に散らばせる
- ハーブの香りがする市販の忌避剤を使用する
これらの方法は、自然な香りを使うので環境にも優しいんです。
例えば、ミントの香りに包まれた庭に近づいたアライグマは、「うぅ、この匂いはダメだ…」と思って逃げ出すかもしれません。
ただし、注意点もありますよ。
ハーブの香りは時間とともに弱くなるので、定期的な入れ替えや散布が必要です。
「めんどくさいなぁ」と思うかもしれませんが、継続することが大切なんです。
また、全てのアライグマに効果があるわけではないので、他の対策と組み合わせるのがおすすめです。
「いろんな方法を試してみよう」という気持ちが大切ですね。
この方法を使えば、アライグマを自然な方法で遠ざけることができます。
しかも、お庭が良い香りに包まれるので一石二鳥。
「いい香りだなぁ」と、きっとあなたも癒されるはずです。
餌場を絶つ!ゴミ箱や果樹園の「アライグマ対策」3ステップ
アライグマの被害を防ぐ鍵は、餌場を絶つことなんです。特にゴミ箱や果樹園は要注意。
ここでは、効果的な「アライグマ対策」を3つのステップでご紹介します。
「えっ、そんな簡単に対策できるの?」と思われるかもしれませんね。
でも、これらのステップを実践すれば、アライグマの被害を大幅に減らせる可能性が高いんです。
では、具体的な3ステップを見ていきましょう:
- ゴミ箱の対策
- 頑丈な蓋付きのゴミ箱を使用する
- ゴミ出しは収集日の朝に行う
- 生ゴミはよく水を切り、新聞紙で包む
- 果樹園の対策
- 熟した果実はすぐに収穫する
- 落果はこまめに拾い集める
- 果樹にネットを張る
- 庭全体の対策
- 餌になりそうなものを片付ける
- コンポストは密閉型のものを使用する
- ペットのエサは屋外に放置しない
例えば、ゴミ箱対策では、「ガチャン、バタン」と音がしてもびくともしない頑丈な蓋付きのゴミ箱を選ぶのがポイントです。
アライグマが「あれ?開かないぞ…」とお手上げになるはずです。
果樹園では、熟した果実を放置すると「わーい、ごちそうだ!」とアライグマが喜んでしまいます。
こまめな収穫が大切です。
庭全体の対策では、「あれ?食べ物がないぞ…」とアライグマが困惑するような環境作りを心がけましょう。
これらの対策を続けていくと、アライグマは「ここには餌がないな」と学習して、別の場所を探すようになるんです。
ただし、注意点もあります。
近所全体で取り組まないと、効果が薄れてしまう可能性があるんです。
「お隣さんちは大丈夫かな?」と気にかけて、地域ぐるみでの対策を呼びかけるのも良いでしょう。
この3ステップを実践すれば、アライグマの被害を効果的に防ぐことができます。
「よし、今日から始めよう!」という気持ちで取り組んでみてくださいね。
アライグマの食性を逆手に取る!「忌避剤」の効果的な使い方
アライグマの嫌いな味や匂いを利用した「忌避剤」を使えば、効果的に被害を防げるんです。ここでは、その賢い使い方をご紹介します。
「へぇ、忌避剤ってどんなものなんだろう?」と興味が湧いてきませんか?
実は、アライグマの鋭い感覚を利用して、彼らを寄せ付けない環境を作り出すことができるんです。
忌避剤の種類と効果的な使い方は、こんな感じです:
- 香り系忌避剤
- アンモニア臭のするもの
- 唐辛子成分を含むもの
- 使用場所:侵入経路、庭の周囲
- 味覚系忌避剤
- 苦味成分を含むもの
- 辛味成分を含むもの
- 使用場所:果樹や野菜の周り
- 音や光を利用した忌避装置
- 動きセンサー付きの音や光を発する装置
- 使用場所:庭や畑の入り口付近
例えば、アンモニア臭の忌避剤を使うと、アライグマは「うっ、この匂いは苦手…」と思って近づかなくなります。
唐辛子成分の忌避剤なら、「ヒリヒリする!もう来ないぞ」とアライグマに学習させることができるんです。
忌避剤の使用ポイントは、こんな感じです:
- 定期的に新しいものと交換する
- 雨に濡れない場所に設置する
- 人や家畜が誤って接触しない場所を選ぶ
- 複数の種類を組み合わせて使用する
忌避剤の中には強い匂いのものもあるので、「ご近所迷惑にならないかな?」と心配になるかもしれません。
使用する前に、周囲への配慮を忘れずに。
また、全てのアライグマに効果があるわけではないので、他の対策と併用するのがおすすめです。
「いろいろ試してみよう」という探究心が大切ですね。
この方法を上手く活用すれば、アライグマを効果的に遠ざけることができます。
「よし、これで安心だ!」という気持ちで、忌避剤を使ってみてはいかがでしょうか。
季節別「アライグマ対策カレンダー」で被害を最小限に!
アライグマの食性は季節によって変化します。この特性を理解して対策を立てる「季節別アライグマ対策カレンダー」を活用すれば、被害を最小限に抑えられるんです。
「えっ、季節によって対策を変えるの?」と驚かれるかもしれませんね。
実は、アライグマの行動パターンや食べ物の好みが季節で変わるので、それに合わせた対策が効果的なんです。
では、季節ごとの対策ポイントを見ていきましょう:
- 春(3月〜5月)
- 出産シーズンなので、屋根裏や物置の点検を
- 新芽や若葉を守るため、庭木にネットを設置
- 夏(6月〜8月)
- 果樹園や家庭菜園の防護を強化
- 生ゴミの管理を徹底(暑さで匂いが強くなるため)
- 秋(9月〜11月)
- 落果の管理を徹底(こまめに拾い集める)
- 冬眠に向けた食料探しが活発になるので警戒を
- 冬(12月〜2月)
- 家屋への侵入対策を強化(暖かい場所を探すため)
- ゴミ箱や倉庫の管理を徹底
例えば、夏には「わーい、おいしそうな果物がいっぱい!」とアライグマが喜ぶので、果樹園の防護が特に重要になります。
一方、冬には「寒いなぁ、暖かい場所はないかな」と家屋に侵入しようとするかもしれません。
この季節別カレンダーを活用するコツは、先手を打つこと。
次の季節の対策を考えて準備しておくことです。
「よし、次はこれをやろう!」という計画性が大切ですね。
ただし、注意点もあります。
地域によってアライグマの行動パターンが少し異なる場合があるので、自分の住む地域の特性も考慮しましょう。
「うちの地域はちょっと違うかも?」と感じたら、地域の情報も参考にしてみてください。
また、この対策カレンダーは基本的な指針です。
天候の変化や周辺環境の変化によって、アライグマの行動が予想外になることもあります。
「臨機応変に対応する」という柔軟な姿勢も大切です。
この季節別「アライグマ対策カレンダー」を活用すれば、年間を通じてアライグマの被害を効果的に防ぐことができます。
「これで一年中安心!」という気持ちで、季節に合わせた対策を実践してみてくださいね。