アライグマの性格が獰猛な理由【生存本能が強い】野生動物としての特性を理解し、安全に対処する方法

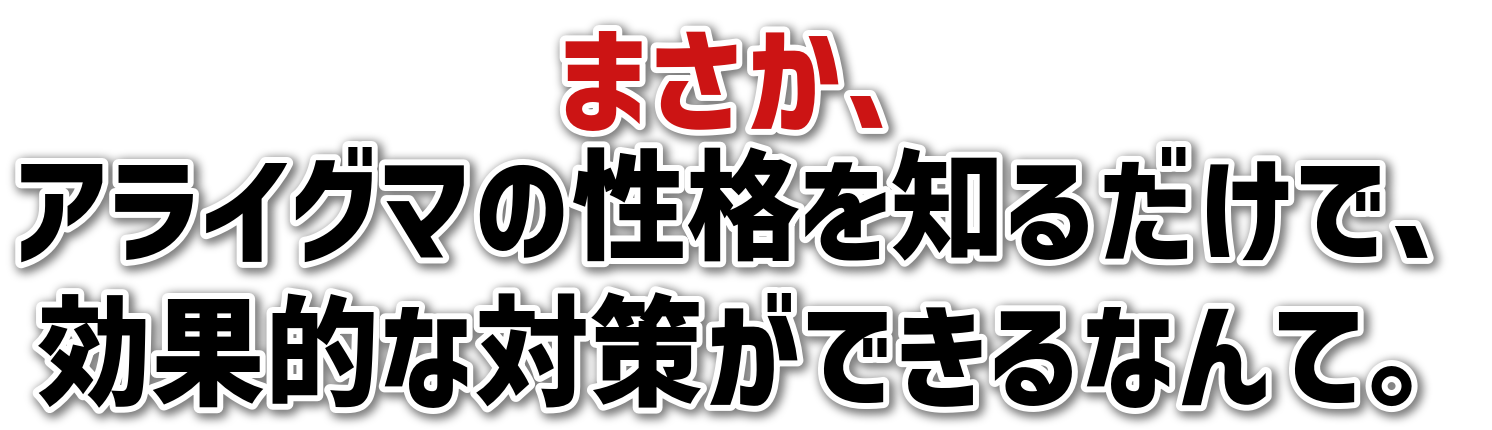
【この記事に書かれてあること】
アライグマの獰猛な性格に驚いたことはありませんか?- アライグマの獰猛な性格は生存本能の表れ
- 縄張り意識と子育て時の攻撃性に要注意
- 他の中型哺乳類と比べて人間への警戒心が低い
- 高い知能と学習能力が被害を深刻化させる要因に
- アライグマの生態を理解し適切な対策を講じることが重要
実は、その裏には強い生存本能が隠れています。
北米原産のアライグマが、なぜ日本で問題を引き起こすのか。
その理由と対策法を知れば、アライグマとの付き合い方が変わるかもしれません。
縄張り意識や子育て時の行動、他の動物との違いなど、アライグマの5つの特徴を徹底解説。
知れば知るほど面白いアライグマの世界、一緒に覗いてみませんか?
【もくじ】
アライグマの獰猛な性格と生存本能

野生のアライグマが示す「強烈な攻撃性」の理由
野生のアライグマが示す強烈な攻撃性は、その生存本能の表れです。厳しい自然環境で生き抜くために、アライグマは獰猛な性格を身につけてきたのです。
「どうしてアライグマはこんなに攻撃的なの?」と思った方も多いでしょう。
実は、アライグマの攻撃性には深い理由があるんです。
まず、アライグマの生息環境を考えてみましょう。
北米原産のアライグマは、常に食料や生活空間を巡って他の動物たちと競争しています。
そんな厳しい環境で生き残るには、強い攻撃性が必要不可欠なんです。
アライグマの攻撃性は、次の3つの場面で特に顕著に表れます:
- 食べ物を守るとき
- 縄張りを主張するとき
- 子どもを守るとき
「この食べ物は絶対に渡さないぞ!」という気持ちが、激しい攻撃性となって表れるのです。
また、アライグマの鋭い歯と爪も、その攻撃性を裏付けています。
これらの武器を使って、アライグマは自分の身を守り、獲物を仕留めるのです。
「でも、そんなに攻撃的だと危険じゃないの?」と心配になるかもしれません。
確かに、人間にとってはちょっと怖い存在かもしれません。
でも、アライグマにとっては、この攻撃性こそが生き抜くための重要な武器なんです。
アライグマの縄張り意識が引き起こす「危険な行動」
アライグマの縄張り意識は非常に強く、これが時として危険な行動を引き起こします。彼らは自分の縄張りを守るために、激しい攻撃性を示すことがあるのです。
「えっ、アライグマにも縄張りがあるの?」と驚く方もいるでしょう。
実は、アライグマの縄張り意識は、私たちが想像する以上に強いんです。
アライグマの縄張りの大きさは、オスで約1?3平方キロメートル、メスで約0.5?1平方キロメートルほどです。
この広さを必死で守ろうとするんです。
縄張りを主張する方法は、主に次の3つです:
- 尿や糞でのマーキング
- 鳴き声による警告
- 直接的な攻撃
そうなると、ガブッと人を噛んだり、ひっかいたりする危険な行動を取ることがあるんです。
「うちの庭に来るアライグマ、もしかして縄張りだと思ってる?」なんて心配になってきませんか?
例えば、ある家族が庭でバーベキューをしていたら、突然アライグマが現れて食べ物を奪おうとした、なんてことも。
これは、その庭をアライグマが自分の縄張りだと思い込んでいる証拠かもしれません。
アライグマの縄張り意識に基づく行動は、季節によっても変化します。
特に繁殖期には、オスの攻撃性が高まります。
「俺の縄張りに入るな!」とばかりに、激しく縄張りを守ろうとするんです。
このように、アライグマの強い縄張り意識は、時として私たち人間にとって危険な状況を生み出すことがあります。
アライグマとの遭遇時には、その縄張り意識を刺激しないよう、慎重に行動することが大切です。
子育て中のアライグマ母親は「特に危険」な存在
子育て中のアライグマ母親は、通常以上に警戒心が強く、非常に危険な存在となります。子どもを守ろうとする強い本能が、激しい攻撃性を引き起こすのです。
「え?アライグマのお母さんってそんなに怖いの?」と思う方もいるでしょう。
実は、子育て中のアライグマ母親は、普段の何倍も獰猛になるんです。
アライグマの子育て期間は、出産後約8?10週間です。
この期間中、母親アライグマは次のような特徴を示します:
- 極端に警戒心が高まる
- わずかな刺激にも過剰に反応する
- 子どもを守るためなら何でもする
「この子たちは絶対に守る!」という強い意志のもと、人間に対しても躊躇なく攻撃を仕掛けてくる可能性があるんです。
子育て中のアライグマ母親の危険性は、次のような状況で特に高まります:
- 巣の近くに人が近づいたとき
- 子どもが危険にさらされていると感じたとき
- 食料が不足しているとき
でも、それは絶対にダメ!
近くには必ず警戒中の母親がいると考えてください。
もし不幸にも子育て中のアライグマ母親に遭遇してしまったら、どうすればいいのでしょうか。
答えは簡単です。
その場からそっと立ち去ること。
決して刺激を与えたり、近づいたりしてはいけません。
子育て中のアライグマ母親の攻撃性は、私たち人間の想像を超えるものです。
その強い母性本能が、時として危険な状況を生み出すことを忘れないでください。
アライグマとの共存のために、この時期の彼らの特性をよく理解し、適切な距離を保つことが大切なんです。
人間に慣れたアライグマの「性格変化」に要注意
人間に慣れたアライグマは、野生の個体とは異なる性格を示すことがあります。一見おとなしくなったように見えても、実は新たな危険性が潜んでいるのです。
「人に慣れたアライグマって、おとなしくなるんじゃないの?」そう思う方も多いでしょう。
確かに、人間のそばで生活するうちに、アライグマの警戒心は薄れていきます。
でも、それは必ずしも良いことではないんです。
人間に慣れたアライグマの性格変化には、次のような特徴があります:
- 人を恐れなくなる
- 人の食べ物に興味を示す
- 人の生活空間に頻繁に侵入する
これは、人間の食べ物に慣れてしまった結果なんです。
「人間の食べ物っておいしいな」と覚えてしまうと、どんどん大胆になっていきます。
人間に慣れたアライグマが示す危険な行動には、次のようなものがあります:
- 人に近づいて食べ物をねだる
- 家の中に侵入して食べ物を探す
- 人を恐れずに攻撃的な態度を取る
でも、それが最悪の結果を招くんです。
餌付けされたアライグマは、人間を「食べ物をくれる存在」と認識してしまいます。
すると、食べ物を求めて頻繁に人に近づくようになり、時には攻撃的な行動を取ることも。
さらに、人間の食べ物に慣れたアライグマは、自然界での生存能力を失ってしまう可能性もあります。
「人間の食べ物しか食べられない」なんてことになったら、アライグマ自身にとっても不幸なことです。
人間に慣れたアライグマの性格変化は、一見おとなしくなったように見えても、実は新たな問題を引き起こす可能性があるのです。
アライグマとの適切な距離感を保ち、野生動物としての本来の姿を尊重することが、人間とアライグマの共存には不可欠なんです。
アライグマへの餌付けは「絶対にやっちゃダメ!」
アライグマへの餌付けは、絶対に避けるべき行為です。一時的には可愛らしく見えるかもしれませんが、長期的には深刻な問題を引き起こします。
「えっ、アライグマに餌をあげちゃダメなの?」と驚く方もいるでしょう。
でも、これは本当に重要なことなんです。
餌付けは、アライグマにとっても人間にとっても良くないことばかりなんです。
アライグマへの餌付けがもたらす問題には、次のようなものがあります:
- アライグマの数が急増する
- 人間への依存度が高まる
- 自然な警戒心を失う
- 攻撃的な行動が増える
「あそこに行けば食べ物がもらえるぞ!」とばかりに、どんどんアライグマが集まってくるんです。
餌付けされたアライグマは、次のような危険な行動を取るようになります:
- 人間に近づいて食べ物を要求する
- 家の中に侵入して食べ物を探す
- ゴミ箱を荒らす
- 庭や農作物を荒らす
そんな優しい気持ちはわかります。
でも、それが逆効果なんです。
餌付けされたアライグマは、自然な食べ物を探す能力を失ってしまいます。
「人間の食べ物の方がおいしいし、簡単に手に入る」と覚えてしまうんです。
これでは、本来のアライグマらしさを失ってしまいます。
さらに、餌付けは感染症のリスクも高めます。
アライグマが集まることで、病気が広まりやすくなるんです。
人間や他の動物にも感染する可能性があり、とても危険です。
ですから、アライグマを見かけても、絶対に餌を与えないでください。
代わりに、次のような対策を取りましょう:
- ゴミ箱にはしっかりとフタをする
- 庭に食べ物を放置しない
- ペットの餌は屋内で与える
アライグマと人間が共存するためには、お互いの領域を尊重し合うことが大切なんです。
アライグマvs他の中型哺乳類:性格の比較

アライグマとタヌキ「獰猛さの違い」を徹底解説
アライグマとタヌキ、どちらがより獰猛なのでしょうか?結論から言うと、圧倒的にアライグマの方が獰猛です。
「えっ、でもタヌキも結構怖そうじゃない?」なんて思う人もいるかもしれませんね。
確かにタヌキも野生動物ですから、油断はできません。
でも、アライグマとタヌキの獰猛さには、はっきりとした違いがあるんです。
まず、アライグマの特徴を見てみましょう:
- 強い縄張り意識を持つ
- 攻撃的な性格
- 人間に対する恐怖心が少ない
- 比較的温和な性格
- 人間を見ると逃げる傾向がある
- 警戒心が強い
アライグマなら「ガブッ」と噛みついてくる可能性があるのに対し、タヌキは「サッ」と逃げていってしまうでしょう。
「でも、タヌキも時々攻撃的になるんじゃない?」そう思う人もいるかもしれません。
確かに、追い詰められたり子育て中のタヌキは攻撃的になることがあります。
でも、それはあくまで防衛本能からくるもの。
アライグマの攻撃性は、より積極的で獰猛なんです。
結局のところ、アライグマの方が圧倒的に獰猛で、人間にとっては危険な存在なんです。
タヌキとの遭遇なら「ホッ」としますが、アライグマとの遭遇は「ドキッ」としちゃいますよね。
アライグマ対策は、タヌキ対策よりもずっと慎重に行う必要があるんです。
アライグマとキツネ「人間への警戒心」を比較
アライグマとキツネ、人間に対する警戒心はどちらが強いのでしょうか?答えは、キツネの方がずっと警戒心が強いんです。
「え?でもキツネって人里に出てくるイメージがあるけど...」そう思った人もいるかもしれませんね。
確かにキツネは時々人里に姿を見せますが、それでもアライグマに比べると、人間に対する警戒心は格段に高いんです。
アライグマとキツネの人間に対する態度を比べてみましょう:
- アライグマ:人間を見ても平気で近づいてくる
- キツネ:人間を見るとすぐに逃げ出す
アライグマなら「フンフン」と鼻を鳴らしながら近づいてくるかもしれません。
一方キツネは「ピョン」と跳んで、一目散に逃げていくでしょう。
アライグマが人間に警戒心が薄い理由はいくつかあります:
- 高い知能と好奇心
- 人間の食べ物への強い執着
- 北米原産で、日本の野生動物よりも人間に慣れている
キツネは警戒心が強いぶん、追い詰められると非常に危険です。
一方アライグマは警戒心が薄いぶん、人間との接触機会が多くなり、結果的に被害が増える傾向にあるんです。
結局のところ、どちらの動物も野生動物。
人間との適切な距離を保つことが大切です。
でも、アライグマの方が警戒心が薄いぶん、より慎重な対応が必要になるんです。
「キツネは逃げるけど、アライグマは逃げない」ということを、しっかり覚えておきましょう。
アライグマとアナグマ「知能と学習能力」の差
アライグマとアナグマ、どちらの知能と学習能力が高いでしょうか?結論から言うと、アライグマの方がずっと高いんです。
「えっ、アナグマってそんなに頭が悪いの?」なんて思った人もいるかもしれませんね。
いえいえ、アナグマだって決して頭が悪いわけではありません。
でも、アライグマの知能と学習能力は、他の中型哺乳類の中でもずば抜けているんです。
アライグマとアナグマの知能と学習能力を比較してみましょう:
- アライグマ:複雑な仕掛けも数分で解く
- アナグマ:単純な仕掛けは解けるが、時間がかかる
アライグマなら「カチャカチャ」と器用に開けてしまうでしょう。
一方アナグマは「ガリガリ」と噛んで開けようとするかもしれません。
アライグマの高い知能と学習能力は、次のような特徴として現れます:
- 複雑な仕掛けの罠を回避する
- 人間の行動パターンを学習する
- 新しい環境にすぐに適応する
- 問題解決能力が高い
でも、それが逆に厄介な問題を引き起こすんです。
アライグマの高い知能と学習能力は、被害対策を難しくします。
一度効果のあった対策も、すぐに学習して無効化してしまうんです。
「よし、これで撃退できた!」と思っても、次はもう通用しない、なんてことがよくあるんです。
一方アナグマは、一度効果のあった対策が長く通用する傾向があります。
「この方法で大丈夫」と安心できるんです。
結局のところ、アライグマの高い知能と学習能力は、私たち人間にとっては頭の痛い問題なんです。
対策を立てる時は、アライグマの賢さを甘く見ないことが大切。
「こんなの簡単に解くでしょ」くらいの気持ちで、高度な対策を考える必要があるんです。
アライグマの「高い適応力」が引き起こす被害の深刻さ
アライグマの高い適応力は、被害を深刻化させる大きな要因となっています。彼らは新しい環境にも素早く順応し、人間社会の中でたくましく生き抜いてしまうんです。
「え?適応力が高いってそんなに問題なの?」と思う人もいるかもしれませんね。
実は、この適応力こそがアライグマ被害を厄介なものにしているんです。
アライグマの高い適応力は、次のような形で現れます:
- 様々な気候や環境で生存できる
- 多様な食べ物に対応できる
- 人工的な構造物を巧みに利用する
- 人間の生活リズムに合わせて行動を変える
彼らは「ガサゴソ」とゴミ箱をあさり、「スイスイ」と雨樋を登り、「モグモグ」と庭の果物を食べてしまいます。
まるで都会生活を楽しんでいるかのようです。
この高い適応力が引き起こす問題は深刻です:
- 生息域の急速な拡大
- 農作物被害の増加
- 家屋への侵入被害の増加
- 在来種との競合
- 感染症の拡散リスク
でも、アライグマの適応力は群を抜いているんです。
例えば、新しい対策を導入しても、アライグマはすぐに「あれ?この方法なら大丈夫かも」と学習し、適応してしまいます。
一方、他の動物なら「怖いからもう近づかない」となることが多いんです。
この高い適応力のせいで、アライグマの被害は年々深刻化しています。
一度定着したアライグマを完全に排除するのは、ほぼ不可能と言われているほどです。
だからこそ、アライグマ対策は早めに、そして徹底的に行う必要があるんです。
「ま、なんとかなるでしょ」なんて甘く見ていると、あっという間に手に負えなくなっちゃいます。
アライグマの高い適応力を理解し、それに負けない対策を考えることが大切なんです。
アライグマの「群れ行動」vs他の動物の単独行動
アライグマの群れ行動は、他の中型哺乳類とは一線を画す特徴です。多くの動物が単独行動を好む中、アライグマは時として群れを形成し、協力して行動することがあるんです。
「えっ、アライグマって群れで行動するの?」と驚く人も多いかもしれませんね。
実は、この群れ行動が、アライグマの被害をより深刻にしているんです。
アライグマの群れ行動と他の動物の単独行動を比較してみましょう:
- アライグマ:最大16頭程度の群れを形成することも
- タヌキ:基本的に単独か、つがいでの行動
- キツネ:繁殖期以外は単独行動が基本
一方、タヌキやキツネなら「シーン」と1匹だけでこっそり現れる、といった具合です。
アライグマの群れ行動がもたらす問題点は次の通りです:
- 被害の規模が大きくなる
- 複数で協力して障害物を乗り越える
- 子育てを協力して行い、繁殖効率が上がる
- 群れでの学習により、新しい技術が広まりやすい
確かに発見はしやすいかもしれません。
でも、群れで行動するアライグマは、単独のアライグマよりもずっと大胆で危険なんです。
例えば、1匹のアライグマなら「ビクビク」しながら近づいてくるところ、群れなら「ドカドカ」と恐れ知らずにやってくるかもしれません。
これは、群れの中で安心感を得ているからなんです。
さらに、群れでの学習能力も侮れません。
1匹が新しい侵入方法を見つけると、すぐに群れ全体に広まってしまうんです。
「よし、これで対策完了!」と思っても、あっという間に無効化されてしまうかもしれません。
このように、アライグマの群れ行動は、被害対策をより複雑で困難なものにしています。
単独行動が基本の他の動物とは違い、アライグマ対策は常に「複数の個体」を想定して行う必要があるんです。
群れの力を甘く見ず、しっかりとした対策を立てることが大切です。
アライグマの生存本能を逆手に取った対策法

アライグマの「嫌がる匂い」を活用した撃退法
アライグマの鋭い嗅覚を利用して、彼らの嫌いな匂いで撃退する方法が効果的です。「え?匂いだけでアライグマを追い払えるの?」と思う方もいるかもしれませんね。
実は、アライグマの鼻はとっても敏感なんです。
彼らの嫌いな匂いを上手く使えば、家や庭への侵入を防げる可能性が高いんです。
では、アライグマが嫌う匂いにはどんなものがあるでしょうか?
- アンモニア臭
- 唐辛子の辛み成分
- 柑橘系の香り
- ミントの香り
- 木酢液の臭い
- アンモニア臭のある布を侵入口に置く
- 唐辛子パウダーを水で薄めて庭にスプレーする
- レモンやオレンジの皮を庭に散らす
- ペパーミントの精油を希釈して庭にスプレーする
- 木酢液を侵入経路に撒く
確かにその通りです。
でも、人間の鼻とアライグマの鼻では感度が全然違うんです。
人間には少し臭う程度でも、アライグマには強烈な悪臭として感じられるんです。
例えば、アンモニア臭のある布を置く場合。
「プンプン」と臭うほどの量は必要ありません。
人間が近づいてもかすかに臭う程度で十分なんです。
アライグマにとっては「うわっ、この臭いはヤバイ!」と感じるくらいの強さになるんです。
ただし、注意点もあります。
これらの匂いは雨で流されたり、時間とともに弱くなったりします。
定期的に補充や再設置が必要です。
「よし、これで完璧!」と油断せずに、継続的な対策を心がけましょう。
匂いを使った撃退法は、アライグマにとって不快なだけで、直接的な危害を加えるものではありません。
人間にも安全で、環境にも優しい方法なんです。
アライグマの生存本能を逆手に取った、賢い対策方法と言えるでしょう。
光と音で「アライグマを威嚇」する効果的な方法
アライグマの警戒心を刺激する光と音を上手く使えば、効果的に彼らを威嚇し、撃退することができます。「光と音だけで本当にアライグマを追い払えるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
でも、アライグマの習性をよく知れば、これが実は強力な武器になるんです。
アライグマは夜行性で、静かな環境を好みます。
突然の光や大きな音は、彼らにとって脅威となるんです。
この特性を利用して、次のような対策が効果を発揮します:
- 動きセンサー付き強力ライト
- 大音量の音楽や人の声
- 風鈴やベル
- 超音波発生装置
- 炎や煙
- 庭に強力な光センサー付きLEDライトを設置する
- 夜間、ラジオを低音量で流し続ける
- 庭に風船を設置し、動きと音でアライグマを驚かせる
- 超音波発生装置を侵入経路に向けて設置する
- 焚き火やたいまつで光と煙を発生させる(火災に注意!
)
確かにその配慮は大切です。
例えば、ラジオを流す場合は音量を控えめにし、深夜は避けるなどの工夫が必要です。
光と音を使った対策の良いところは、アライグマに直接的な危害を加えないことです。
ただし、彼らは賢い動物なので、同じ方法を続けていると慣れてしまう可能性があります。
「よし、これで完璧!」と安心せず、定期的に方法を変えたり、組み合わせたりすることが大切です。
例えば、ある日は光センサー付きライト、次の日は風船、その次は超音波装置...というように、不規則に変化をつけるのが効果的です。
アライグマに「ここは危険だ」と思わせ続けることが、長期的な撃退につながるんです。
光と音を使った威嚇は、アライグマの生存本能を刺激し、自然に遠ざかるよう促す方法です。
人間にも安全で、環境にも優しい対策と言えるでしょう。
アライグマとの共存を図りながら、被害を防ぐ賢い方法なんです。
アライグマの「縄張り意識」を利用した侵入防止策
アライグマの強い縄張り意識を逆手に取れば、効果的に侵入を防ぐことができます。彼らの習性を理解し、上手く利用するのがポイントです。
「えっ、アライグマの縄張り意識を利用するって、どういうこと?」と思う人も多いでしょう。
実は、アライグマは自分の縄張りを他のアライグマから守ろうとする強い本能を持っているんです。
この習性を利用して、「ここは既に他のアライグマの縄張りだ」と思わせることで、侵入を防げるんです。
では、具体的にどんな方法があるでしょうか?
- 尿やフンの匂いを利用する
- フェロモン系の忌避剤を使用する
- 縄張りマーキングを模倣する
- 他の動物の存在をアピールする
- アンモニア臭のある液体を庭の周りに撒く(アライグマの尿の匂いを模倣)
- 市販のアライグマ用フェロモン忌避剤を使用する
- 使用済みの猫の砂を庭に撒く(他の動物の存在をアピール)
- 人工的なマーキング跡を作る(水で薄めた茶色い絵の具を使用)
- 犬の毛を庭に散らす(天敵の存在をアピール)
でも、アライグマの鋭い嗅覚と縄張り意識を考えれば、十分に効果が期待できるんです。
例えば、アンモニア臭のある液体を庭の周りに撒くと、アライグマは「ここは既に他のアライグマのテリトリーだ」と勘違いします。
すると、「チッ、ここは危険だ」と思って、別の場所に移動しようとするんです。
ただし、注意点もあります。
これらの方法は雨で流されたり、時間とともに効果が薄れたりします。
定期的な再設置や補充が必要です。
また、本物のアライグマの縄張りマーキングと間違えないよう、適度な使用を心がけましょう。
縄張り意識を利用した方法の良いところは、アライグマに直接的な危害を加えないことです。
彼らの本能を巧みに利用して、自然に遠ざかってもらう賢い方法なんです。
「ガツンと撃退!」ではなく、「スッと去っていく」イメージです。
アライグマの生態をよく理解し、その習性を逆手に取る。
そんな賢い対策が、長期的な被害防止につながるんです。
「天敵の存在」をアピールしてアライグマを寄せ付けない
アライグマの天敵の存在を上手くアピールすることで、効果的に彼らを寄せ付けないようにできます。アライグマの警戒心を利用した、賢い対策方法です。
「え?アライグマにも天敵がいるの?」と驚く方もいるでしょう。
実は、アライグマにも天敵はいるんです。
そして、その天敵の存在を感じると、アライグマは本能的に危険を察知し、その場所を避けようとします。
では、アライグマの主な天敵にはどんな動物がいるでしょうか?
- 大型の犬
- オオカミ
- コヨーテ
- ボブキャット
- 大型の猛禽類
- 大型犬の毛を庭に散らす
- 犬の鳴き声や遠吠えの録音を夜間に再生する
- フクロウの鳴き声の録音を使用する
- オオカミやコヨーテの尿の匂いがする市販の忌避剤を使用する
- 大型の猛禽類の模型を庭に設置する
でも、アライグマの鋭い感覚と警戒心を考えれば、十分に効果が期待できるんです。
例えば、大型犬の毛を庭に散らすと、アライグマはその匂いを嗅ぎ取って「ここには危険な相手がいる」と感じ取ります。
すると、「ヒェッ、ここは危ないぞ」と思って、別の場所に移動しようとするんです。
ただし、注意点もあります。
これらの方法は雨で流されたり、時間とともに効果が薄れたりします。
定期的な再設置や補充が必要です。
また、本物の動物を使うのではなく、あくまでも存在をアピールするだけにしましょう。
天敵の存在をアピールする方法の良いところは、アライグマに直接的な危害を加えないことです。
彼らの本能的な警戒心を刺激して、自然に遠ざかってもらう賢い方法なんです。
「ガツンと撃退!」ではなく、「コソッと去っていく」イメージです。
アライグマの生態や習性をよく理解し、その警戒心を上手く利用する。
そんな賢い対策が、長期的な被害防止につながるんです。
人間とアライグマが共存しながら、お互いの生活空間を尊重し合える関係を築くことができるでしょう。
アライグマの「好奇心」を逆手に取った罠の仕掛け方
アライグマの強い好奇心を利用して、効果的な罠を仕掛けることができます。ただし、この方法は慎重に行う必要があります。
「えっ、アライグマって好奇心が強いの?」と驚く方もいるでしょう。
実は、アライグマはとても賢くて好奇心旺盛な動物なんです。
新しいものや珍しいものに興味を示す習性があります。
この特性を逆手に取ることで、効果的な対策が可能になるんです。
アライグマの好奇心を刺激するものには、どんなものがあるでしょうか?
- 光るもの
- 動くもの
- 音のするもの
- 珍しい形のもの
- 強い匂いのするもの
- キラキラ光るものを吊るして、その周りに忌避剤を撒く
- 風で動く風車を設置し、その周辺に超音波装置を置く
- 音の出るおもちゃを置き、その周りにアンモニア臭のある布を置く
- 立体的な迷路のようなものを作り、その出口に強い香りのするものを置く
- 水を張ったバケツを置き、その中に光るボールを浮かべる
でも、アライグマの好奇心と警戒心のバランスを上手く利用すれば、効果的な対策になるんです。
例えば、キラキラ光るものを吊るして周りに忌避剤を撒くと、アライグマは最初「わっ、なんだろうこれ?」と興味を示します。
でも、近づいてみると嫌な匂いがするので「うわっ、危ないところだった」と逃げ出すんです。
ただし、この方法を使う際は注意が必要です。
アライグマを傷つけたり、捕獲したりする目的で罠を仕掛けるのは法律で禁止されている場合があります。
あくまでも、アライグマを寄せ付けない、または追い払う目的で使用しましょう。
また、他の動物や子どもが誤って罠にかかる可能性もあるので、設置場所には十分注意が必要です。
定期的に点検し、不要になった罠はすぐに撤去することも大切です。
アライグマの好奇心を利用した方法の良いところは、彼らの行動パターンを学習させられることです。
「あそこに行くと嫌な目に遭う」という経験を積ませることで、長期的に効果が持続する可能性があるんです。
ただし、アライグマは非常に賢い動物なので、同じ手法を繰り返していると慣れてしまう可能性もあります。
定期的に方法を変えたり、組み合わせたりすることが大切です。
アライグマの生態や習性をよく理解し、その特性を上手く利用する。
そんな賢い対策が、長期的な被害防止につながるんです。
人間とアライグマが互いの生活空間を尊重しながら、共存していく方法を見つけていくことが大切ですね。