アライグマのジャンプ力がすごい【垂直に1.5m跳躍】侵入経路として重要な能力の対策法を解説

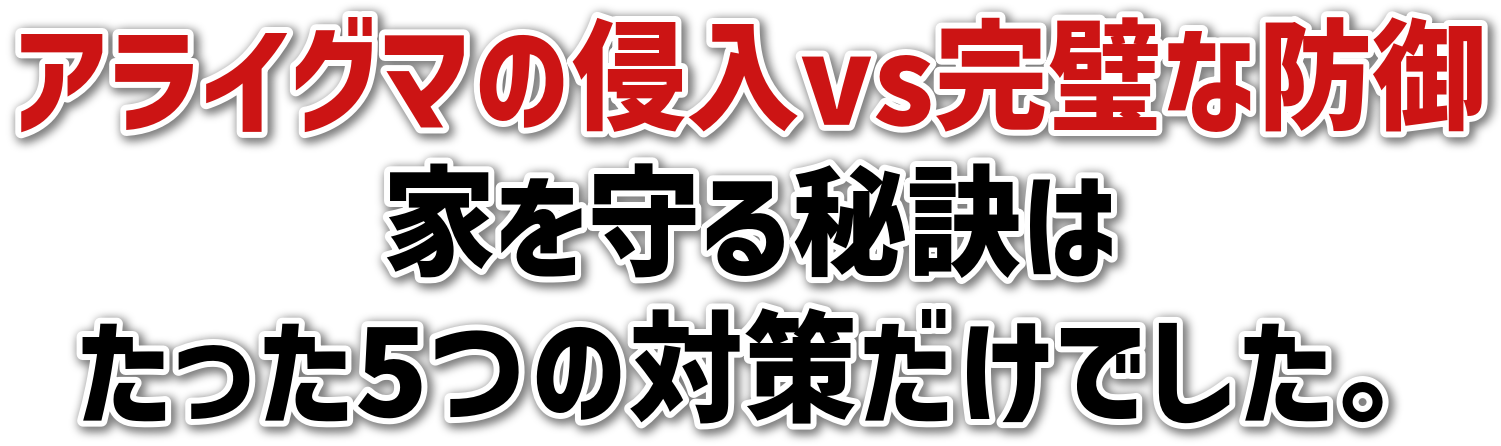
【この記事に書かれてあること】
アライグマの驚異的なジャンプ力をご存知ですか?- アライグマは垂直に1.5mもジャンプできる驚異的な身体能力の持ち主
- 体重が軽いほどジャンプ力が高く、若いアライグマほど要注意
- 水平方向にも2〜3mの距離を飛躍可能で、建物間の移動も容易
- 一般的な犬や猫よりも高いジャンプ力を持つ
- 2m以上の高いフェンスや滑る素材の活用が効果的な対策
なんと、垂直に1.5メートルも跳ね上がれるんです!
これは人間の2倍以上。
家に侵入されたらひとたまりもありません。
でも、大丈夫。
この記事では、アライグマの驚くべきジャンプ力の秘密を解き明かし、あなたの家を守る5つの効果的な対策をご紹介します。
アライグマの能力を知れば知るほど、対策の重要性が分かってきます。
さあ、アライグマから我が家を守る方法を一緒に学んでいきましょう!
【もくじ】
アライグマのジャンプ力は想像以上!垂直1.5m跳躍の驚異
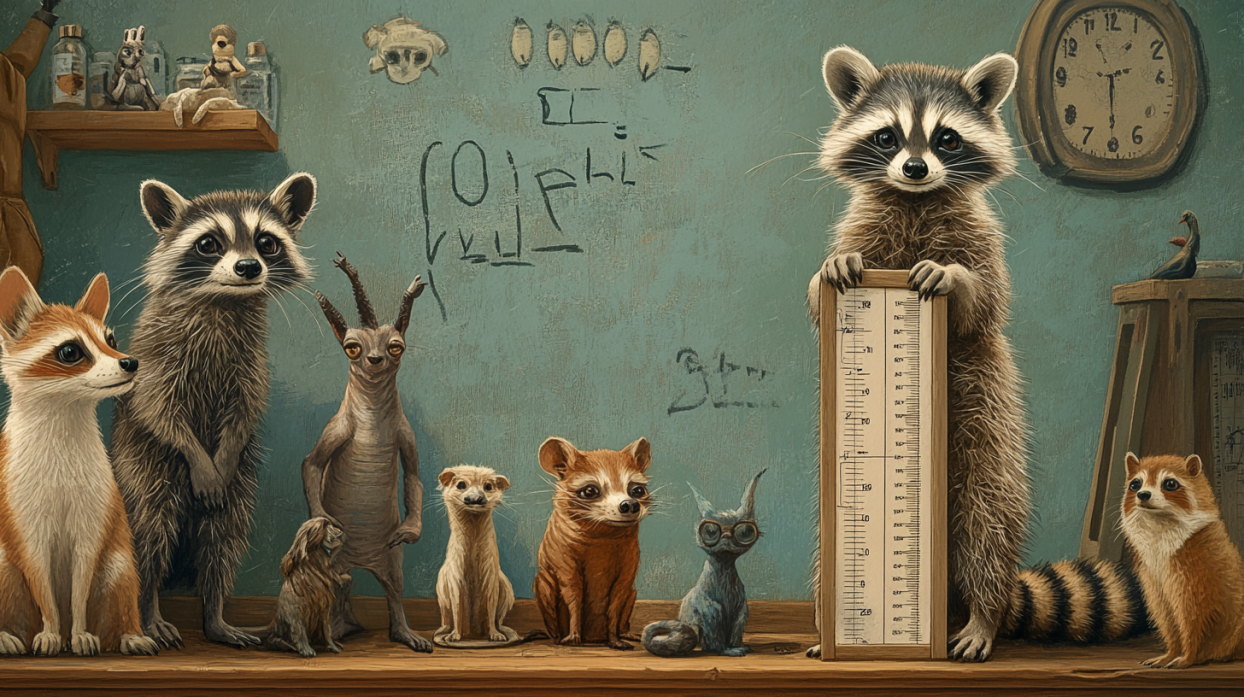
アライグマの最大垂直跳躍高は「1.5m」の衝撃!
アライグマの垂直跳躍力は驚くべき高さで、なんと1.5メートルもの高さまで跳び上がることができるんです。これは普通の家の軒下くらいの高さですよ。
「えっ、あの小さなアライグマがそんなに高く跳べるの?」と驚く人も多いでしょう。
アライグマの体長が40〜70センチメートルほどであることを考えると、自分の体長の2倍以上もの高さを跳躍できる計算になります。
これは人間で例えると、身長170センチの人が3メートル以上跳ぶようなものです。
オリンピック選手級のジャンプ力ですね。
この驚異的なジャンプ力の秘密は、アライグマの後ろ足にあります。
- 筋肉が発達した太い後ろ足
- しなやかで柔軟な背骨
- 軽量で引き締まった体つき
「でも、なんでそんなに高く跳ぶ必要があるの?」と疑問に思う人もいるでしょう。
実は、この能力は生存に直結しているんです。
木に登って安全な場所に逃げたり、餌を探したりするのに役立っています。
自然界では高いジャンプ力が生き残るための重要な武器になっているというわけです。
この驚異的なジャンプ力は、アライグマが人家に侵入する際にも大きな武器となります。
家の周りの対策を考える上で、この1.5メートルという数字は絶対に覚えておく必要がありますよ。
体重との関係!軽いアライグマほど「高くジャンプ」
アライグマのジャンプ力と体重には密接な関係があります。一般的に、体重が軽いアライグマほど高くジャンプできるんです。
「ええっ、じゃあ小さいアライグマの方が厄介なの?」そうなんです。
アライグマの体重は、年齢や性別、生息環境によってかなり差があります。
- 成熟したオス:6〜9キログラム
- 成熟したメス:4〜6キログラム
- 若いアライグマ:2〜4キログラム
体重が軽いほどジャンプ力が高くなる理由は、単純に物理法則に従っているからです。
同じ筋力で跳ぶなら、軽い方が高く跳べるというわけ。
例えば、バネの上に乗せる重さを変えて跳ねさせてみると、軽い物の方が高く跳ねるのと同じ原理です。
特に注意が必要なのは、繁殖期直後の若いアライグマたち。
「ピョンピョン跳ねる元気いっぱいの子アライグマ」をイメージしてみてください。
これらの若いアライグマは、体重が軽い上に筋力も十分あるため、驚異的なジャンプ力を発揮します。
「じゃあ、太ったアライグマなら大丈夫?」残念ながら、そうとも限りません。
アライグマは体重が増えても、それに応じて筋力も発達させるので、ある程度のジャンプ力は維持するんです。
ただし、極端に太りすぎたアライグマは、さすがに高くジャンプできなくなります。
この特性を理解することで、効果的な対策を立てることができます。
特に軽量なアライグマに対応できる高さのフェンスや、滑りやすい素材を使った侵入防止策が重要になってくるんです。
ジャンプ力は「季節や年齢」で変化する?
アライグマのジャンプ力は、実は季節や年齢によって変化するんです。「えっ、動物のジャンプ力って変わるの?」と思う人もいるでしょう。
でも、これはアライグマの生態をよく表している特徴なんです。
まず、季節による変化を見てみましょう。
- 春〜夏:ジャンプ力が最も高くなる
- 秋:やや低下するが、まだ活発
- 冬:最もジャンプ力が低下する
「ピョンピョン跳ねまわる元気いっぱいのアライグマ」をイメージしてみてください。
この時期は繁殖期と重なり、餌も豊富なので、体力も充実しているんです。
結果として、ジャンプ力も最大になります。
一方、冬になるとアライグマの活動は鈍くなります。
「冬眠こそしないけど、ぼーっとしているアライグマ」といった感じですね。
寒さと餌の減少で体力を温存するため、ジャンプ力も自然と低下します。
年齢による変化も興味深いですよ。
- 若いアライグマ:最もジャンプ力が高い
- 成熟したアライグマ:安定したジャンプ力を維持
- 高齢のアライグマ:ジャンプ力が徐々に低下
「まるで跳ね回るゴムボールのよう」と形容できるほどです。
成熟すると体重は増えますが、筋力も発達するので、一定のジャンプ力を維持します。
高齢になると、さすがに体の衰えとともにジャンプ力も低下していきます。
この季節や年齢によるジャンプ力の変化を理解することで、より効果的な対策を立てることができます。
例えば、春から夏にかけては特に警戒を強め、若いアライグマの侵入にも注意を払う必要があります。
「季節や年齢によって変わるアライグマのジャンプ力」を知ることで、より賢く対策を立てられるんです。
アライグマの水平ジャンプ!「2〜3m」の飛距離に注意
アライグマの水平ジャンプ力も侮れません。なんと2〜3メートルもの距離を一気に飛び越えることができるんです。
「えっ、そんなに飛べるの?」と驚く人も多いでしょう。
これは普通の乗用車の長さくらいですからね。
この驚異的な水平跳躍力は、アライグマの生存戦略において非常に重要な役割を果たしています。
- 木から木へ素早く移動する
- 危険から逃げる
- 餌を追いかける
アライグマの水平ジャンプの特徴は、その正確さにもあります。
「ピタッ」と目標地点に着地する様子は、まるでスーパーヒーローのようです。
この正確さは、建物に侵入する際にも発揮されます。
例えば、木の枝から屋根へ、または隣接する建物間を軽々と飛び移ることができるんです。
水平ジャンプの能力は、垂直跳躍と組み合わさることで、さらに脅威となります。
例えば、1.5メートルの高さまで跳び上がり、そこから2〜3メートル先の場所へ飛び移るといった複雑な動きも可能なんです。
「まるでパルクールの達人みたい!」と思えるほどの身のこなしですね。
この能力を防ぐには、建物周辺の環境整備が重要です。
- 建物から2〜3メートル以上離して木を植える
- 屋根や壁面に滑りやすい素材を使用する
- 建物間の空間を広く取る
水平ジャンプの能力を理解することで、より包括的なアライグマ対策が可能になります。
垂直方向だけでなく、水平方向の動きにも注意を払うことが大切なんです。
アライグマの「飛び回る」能力を過小評価せず、しっかりと対策を立てましょう。
アライグマのジャンプ力は「逆効果な対策」を生む?
アライグマの驚異的なジャンプ力を知らずに対策を立てると、思わぬ落とし穴にはまることがあるんです。「えっ、対策が逆効果になるの?」と驚く人もいるでしょう。
でも、実際にそういうケースが少なくないんです。
最も典型的な逆効果な対策が、低すぎるフェンスの設置です。
- 1メートル以下のフェンス:簡単に飛び越えられる
- 1〜1.5メートルのフェンス:跳躍の足場になってしまう
- 表面が粗いフェンス:よじ登りやすくなる
むしろ侵入を助けてしまう可能性すらあるんです。
また、木の剪定も注意が必要です。
「枝を切れば安全」と思いがちですが、実はそうとも限りません。
枝を切りすぎると、かえってアライグマが飛び移りやすい「踏み台」を作ってしまうことがあるんです。
適度な枝の長さを保ちつつ、建物から十分な距離を取ることが大切です。
屋根や壁面の改修も、意外な落とし穴があります。
- 突起のある素材:足掛かりになってしまう
- 柔らかすぎる素材:爪で引っかけられる
- 隙間のある構造:侵入口になりかねない
「じゃあ、どうすればいいの?」と思う人もいるでしょう。
大切なのは、アライグマのジャンプ力を正しく理解し、総合的な対策を立てることです。
例えば、2メートル以上の高さがあり、表面が滑らかで、上部が内側に傾いたフェンスを設置するなど、複数の要素を組み合わせた対策が効果的です。
アライグマのジャンプ力を甘く見た対策は、時として逆効果になってしまいます。
「アライグマの能力を過小評価せず、賢く対策を立てる」。
これが、効果的なアライグマ対策の鍵なんです。
アライグマvs他の動物!ジャンプ力の驚きの比較

アライグマvsイヌ!「サイズ別」のジャンプ力対決
アライグマのジャンプ力は、多くの犬種を上回る驚異的な能力を持っています。「えっ、あの小さなアライグマが犬より高く跳べるの?」と驚く方も多いでしょう。
アライグマと犬のジャンプ力を比べてみると、その差は歴然です。
例えば、
- アライグマ:垂直に約1.5メートル
- 中型犬(ラブラドール・レトリバーなど):垂直に約1〜1.2メートル
- 小型犬(チワワなど):垂直に約0.5〜0.7メートル
「なんでそんなに差があるの?」と思いますよね。
その秘密は、アライグマの体の構造にあります。
アライグマの後ろ足は、跳躍に特化した筋肉構造を持っています。
さらに、しなやかな背骨がバネのような働きをして、ジャンプ力を増幅させているんです。
「まるで小さな跳躍マシーンみたい!」と言えるほどの効率的な体の仕組みですね。
一方で、犬の体は走ることに適した構造になっています。
長距離を走ったり、素早く方向転換したりするのは犬の方が得意です。
でも、垂直跳びとなるとアライグマの独壇場なんです。
この能力の差は、生活環境の違いから生まれました。
アライグマは木に登って生活することが多いので、高い跳躍力が必要だったんです。
犬は地上で走り回る生活をしてきたので、ジャンプ力よりも走る能力が発達したというわけ。
「じゃあ、アライグマは全ての犬より跳躍力があるの?」と思う人もいるでしょう。
実は、グレイハウンドやジャック・ラッセル・テリアなど、一部の犬種はアライグマに匹敵する跳躍力を持っています。
でも、それらは例外中の例外。
ほとんどの場合、アライグマの方が高くジャンプできるんです。
この比較から分かるのは、アライグマの侵入対策には犬用のフェンスでは不十分だということ。
アライグマ対策には、より高く、より工夫されたフェンスが必要になるんです。
アライグマvsネコ!「垂直跳び」で意外な結果に
アライグマとネコの垂直跳びを比べると、意外な結果が見えてきます。「ネコの方が軽いから、絶対高く跳べるはず!」と思う人も多いでしょう。
でも、実はそうとも限らないんです。
まず、それぞれの平均的なジャンプ力を見てみましょう。
- アライグマ:垂直に約1.5メートル
- ネコ:垂直に約1.5〜2メートル
でも、ここで大事なポイントがあります。
アライグマの体重は平均6〜9キログラムなのに対し、ネコは3〜5キログラム程度。
体重差を考えると、アライグマのジャンプ力はかなり驚異的なんです。
「じゃあ、なぜアライグマはそんなに高く跳べるの?」という疑問が湧いてきますよね。
その秘密は、アライグマの体の構造にあります。
アライグマは後ろ足に強力な筋肉を持っていて、それがバネのように働くんです。
さらに、しなやかな背骨がその力を増幅させる。
まるで、体全体がジャンプのために設計されているようなものです。
一方、ネコはより軽量で柔軟性に富んでいます。
ネコの跳躍は、瞬発力と正確さが特徴です。
「ピョン」っと軽やかに跳び、ピタッと着地する。
その姿は、まるでバレリーナのようですね。
アライグマとネコ、どちらが家に侵入しやすいのでしょうか?
実は、両方とも要注意なんです。
アライグマは力強いジャンプで高い場所に到達できますし、ネコは軽やかな動きで狭い隙間も通り抜けられます。
「えっ、じゃあどうすればいいの?」と困ってしまいますよね。
対策のポイントは、高さと隙間の両方に注意を払うことです。
2メートル以上の高さのフェンスを設置し、同時に小さな隙間もしっかりふさぐ。
そうすることで、アライグマもネコも侵入しにくくなるんです。
アライグマとネコ、どちらも驚異的なジャンプ力を持っています。
でも、その特性は少し違います。
この違いを理解して対策を立てることが、効果的な防御につながるんです。
アライグマvsリス!「木の上」での俊敏性は?
アライグマとリス、どちらが木の上で俊敏なのでしょうか?一見、小柄で軽快なリスの方が有利に思えますが、実はアライグマも侮れない能力を持っているんです。
「えっ、あのずんぐりしたアライグマが?」と驚く人も多いでしょう。
まず、それぞれの特徴を比べてみましょう。
- アライグマ:
- 垂直跳び:約1.5メートル
- 水平跳び:約2〜3メートル
- 木登り速度:ゆっくりだが確実
- リス:
- 垂直跳び:約1.2メートル
- 水平跳び:約4〜5メートル
- 木登り速度:非常に速い
リスは軽量で俊敏、木の枝から枝へと軽々と飛び移ります。
まるで空中ブランコの名人のよう。
「ヒュッ、ヒュッ」と風を切る音が聞こえてきそうですね。
一方、アライグマは重量級ですが、その分パワフル。
垂直跳びではリスを上回り、木に登る際も鋭い爪をしっかりと木肌に立てて、着実に登っていきます。
「ゴリゴリ」と木を削る音が聞こえてきそうです。
ではどちらが木の上で有利なのでしょうか?
答えは、状況によって変わるんです。
細い枝が多い木の上ならリスの方が圧倒的に有利。
軽量で素早い動きが生きるからです。
でも、太い枝が多い木だとアライグマも負けません。
力強い動きで安定した移動ができるんです。
家屋への侵入リスクを考えると、両方とも要注意です。
リスは小さな隙間から簡単に入り込めますし、アライグマは力強いジャンプと木登り能力で意外なルートから侵入してきます。
「じゃあ、どう対策すればいいの?」と思いますよね。
ポイントは、木と建物の距離を十分に取ることです。
木の枝を建物から2メートル以上離すことで、両方の動物の侵入リスクを大幅に減らせます。
アライグマとリス、どちらも木の上では驚くべき能力を発揮します。
この2つの動物の特性を理解し、適切な対策を取ることが、家屋を守る鍵となるんです。
アライグマvs人間!オリンピック選手との「驚きの差」
アライグマと人間のジャンプ力、どちらが上だと思いますか?「いやいや、さすがに人間の方が上でしょ」と思う人も多いかもしれません。
でも、実はアライグマのジャンプ力は、オリンピック選手レベルの人間と比べても、決して見劣りしないんです。
まずは、数字で比較してみましょう。
- アライグマ:
- 垂直跳び:約1.5メートル
- 水平跳び:約2〜3メートル
- 人間(オリンピック選手クラス):
- 垂直跳び:約1〜1.2メートル
- 走り幅跳び:約8〜9メートル
そうなんです。
体の大きさを考えると、アライグマのジャンプ力はまさに驚異的なんです。
アライグマの体長は約40〜70センチ。
その体で1.5メートルも跳ぶんですから、自分の体長の2倍以上跳んでいることになります。
人間に例えると、身長170センチの人が3.4メートル以上跳ぶようなものです。
「スーパーヒーローみたい!」と言いたくなりますね。
一方で、水平跳びでは人間の方が圧倒的に優れています。
これは、人間の足の長さと走る能力が影響しているんです。
アライグマには「助走をつけて跳ぶ」という発想がないんですね。
でも、家屋侵入のリスクを考えると、垂直跳びの能力の方が重要です。
アライグマは1.5メートルの高さまで直接跳び上がれるので、多くの塀や柵を簡単に越えられてしまうんです。
「じゃあ、人間の技術で作った対策なんて、アライグマには通用しないの?」と不安になる人もいるでしょう。
でも、大丈夫です。
人間には知恵があります。
アライグマの能力を理解した上で、適切な高さと素材のフェンスを設置したり、滑りやすい素材を使ったりすることで、効果的に対策できるんです。
アライグマと人間、ジャンプ力では意外な結果が見えてきました。
アライグマの驚異的な能力を知ることで、より効果的な対策を立てられるようになります。
人間の知恵と技術で、アライグマの侵入から家を守りましょう。
アライグマの驚異的ジャンプ力から我が家を守る方法

2m以上の「高いフェンス」でアライグマの侵入を防止
アライグマの侵入を防ぐには、2メートル以上の高さのフェンスが必要不可欠です。「えっ、そんなに高くしなきゃダメなの?」と驚く方も多いでしょう。
でも、アライグマの驚異的なジャンプ力を考えると、これくらいの高さは必要なんです。
アライグマは垂直に1.5メートルもジャンプできるんです。
さらに、ちょっとした足場があれば、そこから更に高く跳ねあがることができます。
だから、2メートル以上の高さがないと、簡単に乗り越えられちゃうんです。
フェンスを設置する際は、次の点に注意しましょう。
- 高さは最低2メートル、できれば2.5メートル以上に
- 地面との間に隙間を作らない
- フェンスの上部を内側に45度以上傾斜させる
- 滑りやすい素材を使用する
大丈夫です。
最近は見た目もオシャレなアライグマ対策用フェンスが多く販売されています。
庭の雰囲気を損なわずに、効果的な防御ができるんです。
高いフェンスを設置すると、アライグマだけでなく、他の野生動物の侵入も防げます。
「一石二鳥」というわけですね。
ただし、フェンスを設置しただけで安心してはいけません。
アライグマは賢い動物なので、フェンスの弱点を見つけようとします。
定期的にフェンスをチェックし、破損や隙間ができていないか確認することが大切です。
高いフェンスは、アライグマ対策の基本中の基本。
しっかりと設置して、安心・安全な生活環境を作りましょう。
「滑る素材」を活用!アライグマの足場を奪う戦略
アライグマの侵入を防ぐ効果的な方法の一つが、滑る素材の活用です。アライグマは驚くほど器用ですが、つるつるの表面には弱いんです。
「え?そんな簡単なことでアライグマを防げるの?」と思う方もいるでしょう。
でも、これが意外と効果的なんです。
アライグマは鋭い爪を持っていますが、滑らかな表面ではその爪が役に立ちません。
まるで、スケートリンクの上で走ろうとしているようなものです。
「ツルッ、ピョコッ」と滑って、なかなか前に進めないんです。
滑る素材を効果的に使うポイントは以下の通りです。
- フェンスや壁に金属板やプラスチック板を取り付ける
- 木の幹に滑らかな金属製のカラーを巻き付ける
- 屋根の軒下に角度のついた滑らかな板を設置する
- 雨樋をツルツルの素材に変える
アライグマが屋根に登ろうとしても、ツルッと滑って落ちてしまうんです。
「まるでスリップ芸人みたい!」と思わず笑ってしまうかもしれません。
でも、注意点もあります。
雨の日は特に滑りやすくなるので、人間も気をつける必要があります。
また、定期的なメンテナンスも忘れずに。
時間が経つと表面に細かい傷がついて、滑りにくくなることがあるんです。
「滑る素材って、見た目が悪くならない?」なんて心配する方もいるでしょう。
大丈夫です。
最近は家の外観に合わせた素材や色も多く販売されています。
むしろ、モダンな印象を与えることもあるんですよ。
滑る素材の活用は、アライグマにとっては大きな障害になります。
でも、人間にとっては比較的簡単に導入できる対策なんです。
家の周りをツルツルにして、アライグマの侵入を防ぎましょう。
屋根や壁に「不安定な仕掛け」でジャンプを阻止
アライグマの侵入を防ぐもう一つの効果的な方法が、屋根や壁に不安定な仕掛けを施すことです。アライグマは安定した足場を好むので、不安定な場所は苦手なんです。
「え?そんな簡単なことでアライグマを追い払えるの?」と驚く方もいるでしょう。
でも、これがかなり効果的なんです。
不安定な仕掛けの基本は、アライグマが安心して足を置けない環境を作ることです。
例えば、こんな方法があります。
- 屋根の端に傾斜のあるプラスチック板を取り付ける
- 壁面に不規則な凹凸のある素材を貼り付ける
- ベランダや窓際に不安定なシートを敷く
- 屋根の上に回転するローラーを設置する
アライグマが屋根に登ろうとしても、グラグラして足場が安定しません。
「まるでサーカスの綱渡りみたい!」とアライグマも戸惑うことでしょう。
ベランダや窓際に敷く不安定なシートも効果絶大です。
プラスチック製の波板やざらざらした素材のシートを使うと、アライグマは足元がフワフワして怖くて前に進めません。
「ピョコピョコ、ビクビク」と慎重になるあまり、諦めて帰っていくんです。
でも、注意点もあります。
これらの仕掛けは人間にとっても危険な場合があるので、設置場所には十分気をつけましょう。
また、強風で飛ばされないよう、しっかり固定することも忘れずに。
「でも、そんな仕掛けをしたら家の見た目が悪くならない?」なんて心配する方もいるでしょう。
大丈夫です。
最近は家の外観に合わせたデザインの製品も多く販売されています。
むしろ、モダンなアクセントになることもあるんですよ。
不安定な仕掛けは、アライグマにとっては大きなストレスになります。
でも、人間にとっては比較的安価で導入できる対策なんです。
アライグマを「ビクビク」させて、あなたの家を守りましょう。
木の剪定で「飛び移りルート」を遮断する方法
アライグマの侵入を防ぐ重要な対策の一つが、木の剪定です。実は、木はアライグマにとって絶好の侵入ルートなんです。
「え?庭木がアライグマの味方になってるの?」と驚く方も多いでしょう。
でも、木をうまく管理すれば、アライグマの侵入を大幅に減らせるんです。
アライグマは木を伝って屋根や2階のベランダに簡単に到達できてしまいます。
特に、家の近くにある大きな木は要注意。
枝を伝って「ヨイショ、ピョン」と軽々と家に侵入されちゃうんです。
効果的な木の剪定方法は以下の通りです。
- 家から2メートル以上離れた位置で枝を切る
- 地上から2メートル以下の枝を刈り込む
- 樹木の密集を避け、適度な間隔を保つ
- 果樹の実はこまめに収穫する
アライグマは2〜3メートルの水平ジャンプができるので、これくらい離さないと飛び移られちゃうんです。
「まるでターザンみたいにスイスイ移動されちゃう」なんてことにならないよう、しっかり対策しましょう。
地上から2メートル以下の枝を刈り込むのも効果的です。
これで、地上からの木登りルートを遮断できます。
アライグマに「えっ、登れない!」と困惑させることができるんです。
ただし、急激な剪定は木にストレスを与えるので注意が必要です。
徐々に理想の形に近づけていくのがコツです。
また、季節によって適切な剪定時期が異なるので、木の種類に応じた対応が大切です。
「でも、木を剪定しすぎたら、庭の景観が損なわれない?」なんて心配する方もいるでしょう。
大丈夫です。
適度な剪定は木の健康にも良いですし、むしろ庭全体がすっきりとして見晴らしが良くなるんです。
木の剪定は、アライグマ対策だけでなく、庭の美観を保つ上でも重要です。
定期的なメンテナンスで、アライグマの侵入ルートを遮断しながら、美しい庭を保ちましょう。
「センサーライト」でアライグマを驚かせて撃退!
アライグマ対策の効果的な方法の一つが、センサーライトの活用です。アライグマは夜行性の動物なので、突然の明るい光に非常に敏感なんです。
「え?ただの明かりでアライグマが逃げるの?」と半信半疑の方もいるかもしれません。
でも、これが意外と効果的なんです。
アライグマは暗闇に慣れた目を持っています。
そんな彼らにとって、突然のまぶしい光は大きな驚きとなるんです。
まるで、真っ暗な部屋で急に電気をつけられたときのような感覚でしょうか。
「ビックリ!」って感じで、逃げ出してしまうんです。
センサーライトを効果的に使うポイントは以下の通りです。
- アライグマの侵入経路に設置する
- 光の強さは1000ルーメン以上が理想的
- 複数のライトを連動させて広範囲を照らす
- 可能なら音や動きと組み合わせる
アライグマが侵入しようとした瞬間に「パッ!」と光って、びっくりさせることができます。
「うわっ、まぶしい!」ってな具合に、アライグマも退散せざるを得ません。
音や動きと組み合わせるのも良いアイデアです。
例えば、ライトが点くと同時に音が鳴ったり、スプリンクラーが作動したりすると、より効果的です。
「光、音、水しぶき」の三重奏で、アライグマを「もうここには来たくない!」と思わせることができるんです。
ただし、注意点もあります。
センサーの感度が高すぎると、小さな動物や風で揺れる枝にも反応してしまい、頻繁に点灯することがあります。
適切な感度調整が必要です。
また、近隣への配慮も忘れずに。
夜中に頻繁に明るい光が点滅すると、ご近所さんに迷惑をかけてしまうかもしれません。
「でも、電気代が心配...」という方もいるでしょう。
大丈夫です。
最近の製品は省電力設計で、ほとんど電気代はかかりません。
それに、家に侵入されて被害が出るよりずっと経済的です。
センサーライトは、アライグマ対策としても、防犯対策としても一石二鳥の効果があります。
光の力で、アライグマから家を守りましょう。