アライグマの感覚を利用した総合的対策【複数の刺激を組み合わせる】相乗効果を生む方法と実践例を解説

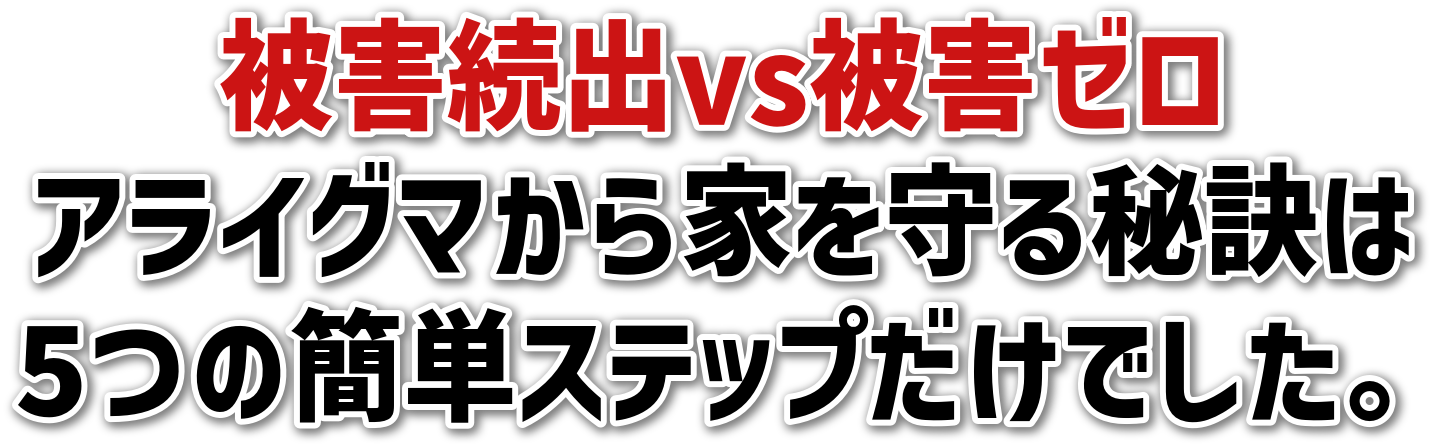
【この記事に書かれてあること】
アライグマの被害に悩まされていませんか?- アライグマの五感を理解し、効果的な対策を立てる
- 複数の刺激を組み合わせることで、より高い効果を発揮
- アライグマの学習能力に注意し、対策を定期的に変更する
- 季節による行動変化を考慮し、適切な対策を選択する
- 長期的な効果を維持するためのローテーション戦略を実践
単一の対策では効果が限られ、イタチごっこのような状況に陥りがちです。
でも、安心してください。
アライグマの五感を巧みに利用した総合的な対策で、効果的に被害を防ぐことができるんです。
この記事では、視覚、聴覚、嗅覚など、複数の刺激を組み合わせる驚きの方法をご紹介します。
さらに、季節に応じた対策や長期的な効果を維持するコツまで、詳しく解説していきます。
あなたの悩みを解決する10の裏技で、アライグマ被害から家や農地を守りましょう!
【もくじ】
アライグマの感覚を利用した総合的対策の重要性

アライグマの五感を理解し「効果的な対策」を!
アライグマの五感を理解することが、効果的な対策の第一歩です。アライグマは鋭い感覚を持つ賢い動物なんです。
「どうしてアライグマはすぐに対策を見破っちゃうの?」そう思った方も多いのではないでしょうか。
実は、アライグマの五感はとても発達しているんです。
特に聴覚、視覚、嗅覚が鋭敏で、これらの感覚を上手く利用すれば、効果的な対策が可能になります。
アライグマの感覚について、詳しく見ていきましょう。
- 聴覚:人間の約10倍も敏感!
小さな物音も逃しません - 視覚:夜間視力は人間の8倍!
暗闇でもよく見えます - 嗅覚:餌の匂いを遠くからかぎ分けます
この特徴を逆手に取れば、アライグマを効果的に撃退できるんです。
例えば、高周波音で聴覚を刺激したり、強い光で視覚を惑わせたり、嫌いな匂いで嗅覚を刺激したりすることで、アライグマを寄せ付けない環境を作れます。
アライグマの五感を理解し、それぞれの感覚に働きかける対策を組み合わせることで、より効果的な防御が可能になるのです。
まさに「知己知彼すれば百戦危うからず」というわけ。
アライグマの特性を知ることが、効果的な対策の近道なのです。
単一対策では限界あり!「複数の刺激」が決め手に
単一の対策だけでは、アライグマ撃退に限界があります。複数の刺激を組み合わせることが、効果的な対策の決め手となるのです。
「せっかく対策したのに、すぐに慣れちゃった…」こんな経験をした方も多いのではないでしょうか。
実は、アライグマは学習能力が高く、単一の対策にはすぐに慣れてしまうんです。
そこで効果を発揮するのが、複数の刺激を組み合わせる方法なのです。
では、具体的にどんな組み合わせが効果的なのでしょうか。
例えば、次のような組み合わせが考えられます。
- 視覚+聴覚:動きセンサー付きLED照明と超音波発生器
- 嗅覚+触覚:忌避スプレーとトゲトゲシート
- 味覚+視覚:苦味スプレーと反射テープ
「ピカッ」と光りながら「キーン」という音が鳴れば、アライグマもビックリ。
さらに嫌な匂いがして足元がチクチクするなんて、たまったもんじゃありません。
「でも、そんなにたくさんの対策をするのは大変そう…」と思った方もいるかもしれません。
確かに初期投資は少し高くなるかもしれませんが、長期的に見れば被害を抑えられるので、むしろコスト効率が良いんです。
複数の刺激を組み合わせることで、アライグマを効果的に撃退できます。
まるで「いたずら好きの子どもを何重もの障害物で阻止する」ような感覚です。
アライグマにとって、あなたの家や畑が「ちょっと寄りがたい場所」になるよう、複数の対策を組み合わせてみましょう。
アライグマの学習能力に注意!「対策の組み合わせ」が鍵
アライグマの高い学習能力を甘く見てはいけません。対策の組み合わせを工夫し、定期的に変更することが、長期的な効果を維持する鍵となります。
「せっかく効果があったのに、また被害が…」こんな経験をした方も多いのではないでしょうか。
実は、アライグマはとても賢く、一度効果のあった対策でも、時間が経つと慣れてしまうんです。
まるで「いたずら好きの子どもが親の対策を次々と突破していく」ような感じです。
では、どうすればアライグマの学習能力に対抗できるのでしょうか。
ポイントは以下の3つです。
- 複数の対策を組み合わせる
- 定期的に対策の内容や配置を変更する
- 季節に応じて対策を調整する
季節ごとに対策を変えれば、アライグマも「あれ?また新しい障害が…」と戸惑うはずです。
「でも、そんなにこまめに対策を変えるのは面倒くさそう…」と思った方もいるでしょう。
確かに手間はかかりますが、被害を長期的に防ぐためには必要な努力なんです。
まるで「ゲームの難易度を少しずつ上げていく」ように、アライグマにとっての「侵入難易度」を徐々に上げていくイメージです。
アライグマの学習能力を逆手に取り、常に新しい刺激を与え続けることで、効果的な対策が実現できます。
「この家は危険だ」とアライグマに学習させることが、最終的な目標なのです。
粘り強く対策を続け、アライグマとの知恵比べに勝利しましょう!
「アライグマに餌を与える」は逆効果!絶対にNG
アライグマに餌を与えるのは絶対にやめましょう。これは対策どころか、逆効果になってしまいます。
「かわいそうだから餌をあげちゃった…」なんて経験がある方もいるかもしれません。
でも、これがとんでもない間違いなんです。
餌をあげることで、アライグマはその場所を「餌場」として認識してしまいます。
そうなると、もう大変!
次々とアライグマがやってきて、被害が拡大してしまうんです。
では、なぜアライグマに餌を与えてはいけないのでしょうか。
理由は主に3つあります。
- アライグマが人間を恐れなくなる
- その場所に定住してしまう
- 繁殖率が上がり、個体数が増える
実は、餌付けの影響は想像以上に大きいんです。
例えば、1匹のメスアライグマに餌を与え続けると、1年後には10匹以上に増えてしまう可能性があるんです。
まるで「うさぎ小屋でうさぎが増えていく」ような勢いです。
また、餌付けされたアライグマは人間を恐れなくなります。
「人間=餌をくれる存在」と認識してしまうんです。
そうなると、家の中に侵入してくるなど、より大胆な行動を取るようになってしまいます。
「でも、どうしても餌をあげたくなっちゃう…」という方もいるかもしれません。
そんな時は、アライグマの被害の写真を見て、餌付けの危険性を思い出しましょう。
一時的な同情心で餌をあげるより、長期的な視点で対策を続けることが、結果的にアライグマのためにもなるんです。
餌付けは絶対NG!
これを守ることが、効果的なアライグマ対策の第一歩です。
アライグマに「ここには餌はない」と学習させることが、最も効果的な対策なのです。
感覚別アライグマ対策の効果と組み合わせ方

視覚vs聴覚!アライグマを驚かせる「効果的な刺激」
アライグマを驚かせるには、視覚と聴覚を同時に刺激するのが効果的です。これらの感覚を上手く利用すれば、アライグマを寄せ付けない環境を作ることができます。
まず、視覚刺激から考えてみましょう。
アライグマは夜行性ですが、意外にも明るい光に弱いんです。
「えっ、夜行性なのに光が苦手なの?」と思った方もいるでしょう。
実は、突然の強い光は彼らを驚かせ、不安にさせるんです。
そこで効果的なのが、動きセンサー付きのLED照明です。
アライグマが近づくとピカッと光るので、「うわっ!何だこれ!」とビックリしちゃうわけです。
次に聴覚刺激ですが、アライグマは私たちには聞こえない高い音にも敏感なんです。
そこで活躍するのが超音波発生器。
人間には聞こえませんが、アライグマにとっては「キーン」という不快な音なんです。
さて、ここからが重要ポイント。
これらの視覚刺激と聴覚刺激を組み合わせるんです。
例えば、こんな感じ。
- 動きセンサー付きLED照明と超音波発生器を同じ場所に設置
- 光と音が同時に作動するように設定
- 複数箇所に設置して、逃げ場をなくす
まるで遊園地のお化け屋敷みたいですね。
でも、アライグマにとっては楽しくない体験になるはずです。
「でも、光と音で近所迷惑にならない?」心配する方もいるでしょう。
大丈夫です。
人間の目や耳に優しい設定にすれば、ご近所さんに迷惑をかけることなく、アライグマ対策ができるんです。
視覚と聴覚を組み合わせた対策で、アライグマを効果的に撃退しましょう。
きっと、彼らも「ここはちょっと怖いところだな」と感じるはずです。
嗅覚vs触覚!アライグマを寄せ付けない「環境作り」
アライグマを寄せ付けない環境作りには、嗅覚と触覚を刺激する方法が効果的です。これらの感覚を上手く利用すれば、アライグマにとって「近寄りたくない場所」を作ることができます。
まず、嗅覚刺激について考えてみましょう。
アライグマは鼻がとても敏感なんです。
「へえ、犬みたいに嗅覚が鋭いの?」と思った方、その通りです。
でも、この特徴を逆手に取れば、効果的な対策になるんです。
アライグマが嫌う匂いには、次のようなものがあります。
- 唐辛子の辛み成分
- ミントの清涼感のある香り
- 柑橘系の強い香り
次に触覚刺激ですが、アライグマは意外と繊細なんです。
足裏が敏感で、歩きやすい場所を好みます。
そこで効果的なのが、不快な触感を与える素材の利用です。
例えば、こんな方法があります。
- トゲトゲした素材のマットを侵入口に敷く
- ザラザラした砂利を庭に敷き詰める
- 滑りやすい素材をフェンスに取り付ける
ただし、注意点もあります。
忌避剤や不快な触感を与える素材は、ペットや小さな子どもにも影響を与える可能性があります。
使用する際は安全性を確認し、適切な場所に設置しましょう。
「でも、いつも臭い環境で生活するのは嫌だな…」と心配する方もいるでしょう。
大丈夫です。
人間にはそれほど強く感じない程度の濃度で効果がありますし、設置場所を工夫すれば快適に暮らせます。
嗅覚と触覚を刺激する対策で、アライグマにとって「ちょっと寄りたくないな」と思わせる環境を作りましょう。
きっと彼らも「ここは居心地が悪いぞ」と感じるはずです。
味覚対策も重要!「忌避剤」と「誘引剤」の使い分け
アライグマ対策には味覚を利用した方法も効果的です。忌避剤と誘引剤を上手に使い分けることで、より強力な対策が可能になります。
まず、忌避剤について考えてみましょう。
アライグマは意外と味にうるさいんです。
「えっ、何でも食べる雑食じゃないの?」と思った方もいるでしょう。
確かに雑食ですが、苦味や辛味には敏感なんです。
効果的な忌避剤の成分には、次のようなものがあります。
- 唐辛子エキス(辛み成分)
- ニガヨモギ(苦み成分)
- クエン酸(強い酸味)
「ペッペッ、まずい!」とアライグマも思わず顔をしかめるかも。
一方で、誘引剤の使い方も重要です。
「えっ、寄せ付けたくないのに誘引剤?」と疑問に思った方もいるでしょう。
実は、誘引剤は罠と組み合わせて使うことで効果を発揮するんです。
誘引剤の例としては、次のようなものがあります。
- 魚の缶詰の汁
- バナナの皮
- ピーナッツバター
さて、ここからが重要ポイント。
忌避剤と誘引剤を上手に組み合わせるんです。
例えば、こんな感じ。
- 庭全体に忌避スプレーを散布
- 庭の隅に罠を設置し、その中に誘引剤を配置
- 罠の周囲だけ忌避剤を使わない
ただし、注意点もあります。
罠を使用する場合は、地域の法律や規制を確認し、適切な方法で行う必要があります。
また、捕獲したアライグマの処置についても、事前に確認しておきましょう。
味覚を利用した対策で、アライグマを効果的にコントロールしましょう。
忌避剤と誘引剤を賢く使い分けることで、より強力な防御線を築くことができます。
季節による行動変化に注目!「対策の使い分け」が重要
アライグマの行動は季節によって大きく変わります。この変化に合わせて対策を使い分けることが、効果的な防御の鍵となるんです。
まず、アライグマの季節ごとの行動パターンを見てみましょう。
- 春:子育ての時期。
巣作りに忙しい - 夏:活動が最も活発。
食料を求めてあちこち動き回る - 秋:冬に備えて食べ物を探し回る
- 冬:活動が鈍る。
暖かい場所を探す
この行動の変化を理解することが、効果的な対策の第一歩なんです。
では、季節ごとの対策を考えてみましょう。
春の対策:この時期は巣作りを防ぐことが重要です。
屋根裏や物置など、巣になりそうな場所をしっかりふさぎましょう。
「ガサガサ」という音がしたら要注意。
すぐに対策を。
夏の対策:活動が活発なこの時期は、総合的な対策が必要です。
忌避剤や音光刺激など、複数の方法を組み合わせましょう。
「あっちもこっちも対策だらけ!」というくらいが良いです。
秋の対策:食べ物を求めて動き回るこの時期は、誘引物の管理が重要です。
落ち葉や熟した果実は早めに片付け、ゴミ箱はしっかり密閉。
「食べ物なんてどこにもないぞ」と思わせることがポイントです。
冬の対策:暖かい場所を探すアライグマに注意。
家の周りの隙間や穴をしっかりふさぎましょう。
「ここは寒くて住めないな」と思わせるのが目標です。
季節に合わせて対策を変えることで、一年中効果的な防御が可能になります。
まるで「いたちごっこ」のように、アライグマの行動に合わせて対策を変化させるんです。
ただし、注意点もあります。
季節の変わり目には、前の季節の対策と次の季節の対策を組み合わせるなど、柔軟な対応が必要です。
「今日から夏だから対策を変える」というような機械的な切り替えは避けましょう。
季節による行動変化を理解し、適切な対策を使い分けることで、より効果的なアライグマ対策が可能になります。
「季節ごとに作戦を立てる」という感覚で、アライグマとの知恵比べを楽しんでみてはいかがでしょうか。
長期的効果を維持する「ローテーション戦略」とは?
長期的にアライグマ対策の効果を維持するには、「ローテーション戦略」が効果的です。これは、複数の対策を定期的に入れ替えることで、アライグマが慣れるのを防ぐ方法なんです。
なぜローテーションが必要なのでしょうか。
実は、アライグマはとても賢い動物なんです。
同じ対策を続けていると、「あ、このくらいなら大丈夫だな」と学習してしまいます。
まるで「いたずら好きの子どもが親の対策を次々と突破していく」ような感じです。
では、具体的にどんなローテーション戦略があるのか見てみましょう。
- 刺激の種類を変える:視覚刺激→聴覚刺激→嗅覚刺激の順に変更
- 設置場所を変える:庭→家の周り→侵入口付近と移動
- 対策の強度を変える:弱→中→強のように段階的に変更
- 複数の対策を組み合わせる:単独使用→2種類同時→3種類同時と増やす
確かに少し手間はかかりますが、長期的に見れば効果は絶大なんです。
例えば、1か月ごとにローテーションを行うとしましょう。
- 1か月目:動きセンサー付きLED照明を庭に設置
- 2か月目:超音波発生器を家の周りに設置
- 3か月目:忌避スプレーを侵入口付近に散布
- 4か月目:LED照明と超音波発生器を同時に使用
ただし、注意点もあります。
ローテーションのタイミングは、アライグマの出没状況を見ながら調整しましょう。
「1か月ごと」と決めすぎず、柔軟に対応することが大切です。
また、効果を確認するためのモニタリングも忘れずに。
定期的な見回りや、できれば監視カメラの設置がおすすめです。
「あれ、最近アライグマ見ないな」と感じたら、対策が効果を発揮している証拠かもしれません。
ローテーション戦略を実践することで、アライグマ対策の効果を長期的に維持できます。
まるで「いたずら好きの子どもとの知恵比べ」のように、アライグマとの攻防を楽しみながら、効果的な対策を続けていきましょう。
驚きの裏技!アライグマ撃退のための5つの秘策

ペットボトルの反射光で「アライグマを威嚇」する方法
ペットボトルを使った驚きの裏技で、アライグマを効果的に威嚇できます。この方法は、アライグマの視覚を利用した巧妙な対策なんです。
まず、空のペットボトルを用意しましょう。
「えっ、ペットボトルだけ?」と思われるかもしれませんが、これが意外と効果的なんです。
ペットボトルに水を半分ほど入れ、庭や畑の数か所に設置します。
ここがポイントです。
ペットボトルを設置する際は、必ず太陽光が当たる場所を選びましょう。
太陽の光がペットボトルの水面で反射して、キラキラとした光を放つんです。
この不規則に動く光が、アライグマにとっては不気味で警戒すべき存在に見えるんです。
「でも、夜はどうするの?」と思われるかもしれません。
実は、月明かりでも同じ効果が期待できるんです。
さらに、庭灯やソーラーライトを併用すれば、24時間体制の対策になります。
この方法の良いところは、以下の3点です。
- 費用がほとんどかからない
- 設置が簡単で誰でもできる
- 環境にやさしい対策である
強風の日はペットボトルが倒れる可能性があるので、重石を置くなどの工夫が必要です。
また、長期間放置すると藻が生えてしまうので、定期的に水を交換しましょう。
「こんな簡単な方法で本当に効果があるの?」と半信半疑かもしれません。
でも、アライグマの警戒心の強さを考えると、意外と効果的なんです。
まるで「おばけ屋敷のちょっとした仕掛け」のように、アライグマを怖がらせることができるんです。
ペットボトルの反射光、意外と侮れない威力を発揮します。
試してみる価値は十分にありそうですね。
アンモニア臭で「侵入を防ぐ」簡単トリック
アンモニア臭を利用した驚きの裏技で、アライグマの侵入を効果的に防ぐことができます。この方法は、アライグマの鋭敏な嗅覚を逆手に取った巧妙な対策なんです。
まず、アンモニア臭のする布を用意しましょう。
「えっ、臭い布?」と思われるかもしれませんが、これがアライグマ対策の強力な武器になるんです。
アンモニア臭は、アライグマにとって非常に不快な匂いなんです。
具体的な方法は以下の通りです。
- 古いタオルや布を用意する
- アンモニア水に浸す(市販の家庭用洗剤でもOK)
- よく絞ってから、ビニール袋に入れる
- ビニール袋に小さな穴をあける
- アライグマの侵入経路付近に吊るす
ビニール袋に小さな穴をあけることで、臭いが少しずつ漏れ出すようにするんです。
これにより、長期間効果が持続するんです。
「でも、人間も臭くないの?」と心配される方もいるでしょう。
確かに、近づくと少し臭いを感じますが、アライグマほど敏感ではないので、大丈夫です。
それに、庭の隅や侵入経路付近に設置するので、生活に支障はありません。
この方法の利点は以下の3つです。
- 材料が安価で手に入りやすい
- 設置が簡単で誰でもできる
- アライグマに直接危害を加えない人道的な方法
雨に濡れると効果が薄れるので、屋根のある場所に設置するか、定期的に交換する必要があります。
また、ペットがいる家庭では、ペットが不快に感じる可能性があるので、設置場所に注意しましょう。
「こんな簡単な方法で本当にアライグマが来なくなるの?」と疑問に思うかもしれません。
でも、アライグマの嗅覚の鋭さを考えると、意外と効果的なんです。
まるで「見えない壁」をアライグマの侵入経路に作るようなものです。
アンモニア臭、意外と強力なアライグマ撃退効果を発揮します。
ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
風鈴の音で「アライグマを混乱」させる裏技
風鈴の音を利用した意外な裏技で、アライグマを効果的に混乱させることができます。この方法は、アライグマの繊細な聴覚を利用した巧妙な対策なんです。
まず、風鈴を用意しましょう。
「えっ、風鈴?夏の風物詩でしょ?」と思われるかもしれませんが、これがアライグマ対策の強力な味方になるんです。
風鈴の不規則な音が、アライグマにとっては不安や警戒心を引き起こす要因になるんです。
具体的な方法は以下の通りです。
- 複数の風鈴を用意する(材質の異なるものがベスト)
- 庭や畑の数か所に設置する
- 風の通りやすい場所を選ぶ
- 高さを変えて設置する(地上1mから2m程度)
複数の風鈴を使うことで、音の種類や方向性に変化を持たせるんです。
これにより、アライグマはどこから音が聞こえてくるのか分からず、混乱してしまうんです。
「でも、近所迷惑にならない?」と心配される方もいるでしょう。
大丈夫です。
風鈴の音は一般的に心地よいものとされていますし、夜間はそれほど風が強くならないので、騒音問題にはなりにくいんです。
この方法の利点は以下の3つです。
- 見た目にも美しく、庭の装飾にもなる
- 電気を使わないので環境にやさしい
- 季節を問わず使用できる
強風の日は音が大きくなりすぎる可能性があるので、天気予報をチェックして必要に応じて取り外しましょう。
また、金属製の風鈴は錆びやすいので、定期的なメンテナンスが必要です。
「こんなのんびりした方法で本当にアライグマが来なくなるの?」と半信半疑かもしれません。
でも、アライグマの神経質な性格を考えると、意外と効果的なんです。
まるで「目に見えない音のバリア」を張るようなものですね。
風鈴の音、意外と強力なアライグマ撃退効果を発揮します。
夏の風物詩を、アライグマ対策に活用してみてはいかがでしょうか。
古いラジオで「人の気配」を演出!意外な効果とは
古いラジオを利用した意外な裏技で、アライグマに「人の気配」を感じさせ、効果的に撃退することができます。この方法は、アライグマの警戒心の強さを逆手に取った巧妙な対策なんです。
まず、古いラジオを用意しましょう。
「えっ、使っていないラジオがあるけど...」と思われた方、それが大活躍するんです!
ラジオから流れる人の声や音楽が、アライグマにとっては「人間がいる」という強力な警告信号になるんです。
具体的な方法は以下の通りです。
- 古いラジオを用意する(電池式がベスト)
- 庭や畑の数か所に設置する
- 夜間、低音量でラジオを流す
- チャンネルを時々変える
- 設置場所を定期的に変更する
音量を低くすることで、近所迷惑を避けつつ、アライグマには十分な警戒心を与えることができるんです。
また、チャンネルや設置場所を変えることで、アライグマが慣れるのを防ぐんです。
「でも、電気代が心配...」と思われる方もいるでしょう。
そんな時は電池式のラジオを使うのがおすすめです。
さらに、タイマーを使って必要な時間帯だけ作動させれば、より効率的です。
この方法の利点は以下の3つです。
- コストがほとんどかからない(古いラジオの再利用)
- 設置が簡単で誰でもできる
- アライグマに直接危害を加えない人道的な方法
雨の日は屋外に置けないので、防水カバーを使うなどの工夫が必要です。
また、長期間同じ場所で使用すると効果が薄れる可能性があるので、定期的に場所を変えましょう。
「こんな簡単な方法で本当にアライグマが来なくなるの?」と疑問に思うかもしれません。
でも、アライグマの人間に対する警戒心の強さを考えると、意外と効果的なんです。
まるで「見えない人間」が庭にいるかのような錯覚を与えるんです。
古いラジオ、意外と強力なアライグマ撃退効果を発揮します。
眠っているラジオに新しい役割を与えてみてはいかがでしょうか。
コーヒーかすで「アライグマを寄せ付けない」庭づくり
コーヒーかすを利用した驚きの裏技で、アライグマを寄せ付けない庭づくりができます。この方法は、アライグマの鋭敏な嗅覚を利用した巧妙な対策なんです。
まず、コーヒーかすを用意しましょう。
「えっ、捨てているコーヒーかすが使えるの?」と思われるかもしれませんが、これがアライグマ対策の強力な武器になるんです。
コーヒーの強い香りが、アライグマにとっては不快で避けたい匂いなんです。
具体的な方法は以下の通りです。
- 使用済みのコーヒーかすを集める
- 天日干しで水分を飛ばす
- 庭の周囲や侵入経路にまく
- 植木鉢やプランターの土にも混ぜる
- 定期的に新しいコーヒーかすに交換する
コーヒーかすを乾燥させることで、効果が長続きするんです。
また、土に混ぜることで、植物の肥料としても活用できるんです。
一石二鳥ですね。
「でも、庭中コーヒーの匂いがしない?」と心配される方もいるでしょう。
確かに、近づくとコーヒーの香りがしますが、人間にとっては不快な匂いではありません。
むしろ、虫除けの効果もあるので、庭時間が快適になるかもしれません。
この方法の利点は以下の3つです。
- コストがほとんどかからない(コーヒーかすの再利用)
- 環境にやさしい自然な対策方法
- 植物の生育を助ける効果もある
雨が降ると効果が薄れるので、定期的に新しいコーヒーかすを追加する必要があります。
また、ペットがいる家庭では、ペットが食べてしまう可能性があるので注意が必要です。
「こんな簡単な方法で本当にアライグマが来なくなるの?」と半信半疑かもしれません。
でも、アライグマの嗅覚の鋭さを考えると、意外と効果的なんです。
まるで「目に見えない香りのバリア」を庭に張るようなものです。
コーヒーかす、意外と強力なアライグマ撃退効果を発揮します。
毎朝のコーヒータイムが、アライグマ対策にもなるなんて素敵じゃありませんか。
家族みんなでコーヒーかすを集めて、環境にやさしいアライグマ対策を始めてみましょう。
「ほら見て!昨日まであんなにアライグマが来ていたのに、今日は全然来ていないよ」なんて会話が聞こえてきそうです。
コーヒーの香り漂う、アライグマの来ない素敵な庭。
そんな夢のような空間が、意外と簡単に手に入るかもしれませんね。