アライグマの食料探索行動とは【嗅覚が鋭敏で餌を発見】ゴミ以外の誘引要因と対策方法を詳しく解説

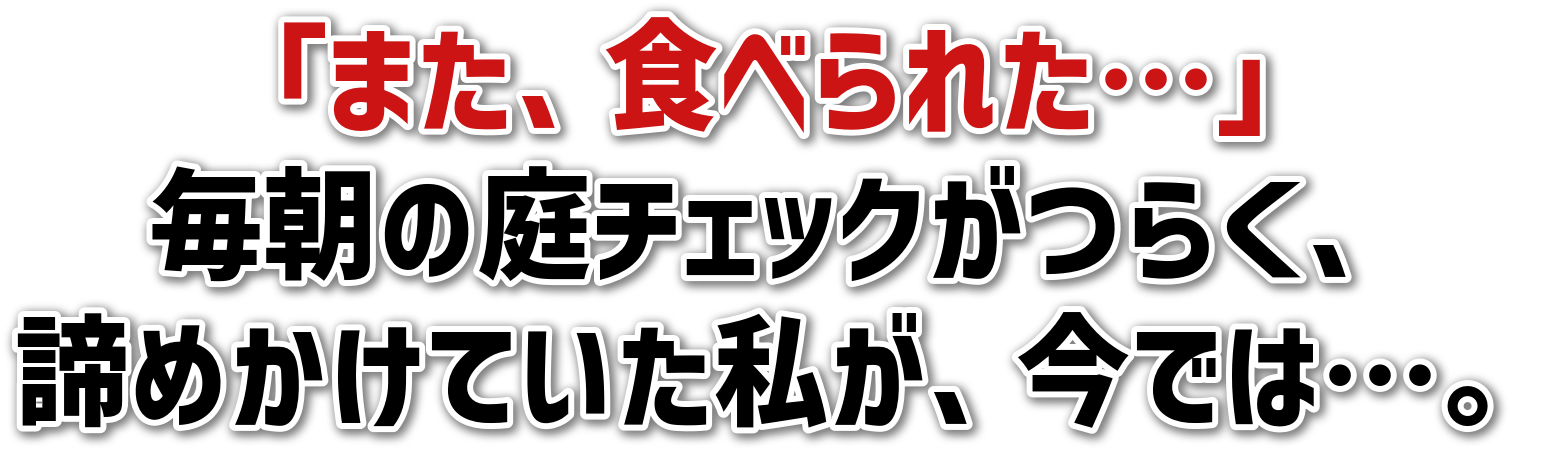
【この記事に書かれてあること】
アライグマの食料探索行動、知っていますか?- アライグマの驚異的な嗅覚能力が食料探索の核心
- 夜行性のため、夜間の対策が重要
- 庭の果樹や野菜が主な標的に
- ペットフードが意外な誘因になることも
- 自然環境と人工環境で異なる食料探索行動
- 効果的な対策で被害を大幅に軽減可能
彼らの驚くべき嗅覚と夜行性が、私たちの生活に思わぬ影響を与えているんです。
庭の果樹や野菜、はたまたペットフードまで、アライグマにとっては魅力的な食べ物がいっぱい。
でも大丈夫。
知恵と工夫で被害を激減できるんです。
自然環境と人工環境での行動の違いを理解し、効果的な対策を立てれば、アライグマとの上手な付き合い方が見えてきます。
さあ、アライグマの食料探索の秘密に迫り、快適な生活を取り戻しましょう!
【もくじ】
アライグマの食料探索行動とその特徴

アライグマの嗅覚が鋭敏!餌を発見する驚異の能力
アライグマの嗅覚は驚くほど鋭敏で、餌を見つける能力は抜群です。人間の約10倍もの嗅覚能力を持つアライグマは、まるで「歩く探知機」のよう。
「おや?この匂いは...」とアライグマが鼻をピクピクさせると、そこには必ず食べ物が!
彼らの鼻は、地中に埋まった虫や、遠く離れた果実の匂いまで感知できるんです。
アライグマの嗅覚の特徴は以下の通りです。
- 匂いの方向を正確に特定できる
- 地中や木の上など、目に見えない場所の餌も発見
- 腐敗した食べ物と新鮮な食べ物を区別できる
- 人間の食べ物の匂いに特に敏感
「ここにも、あそこにも、おいしそうな匂いがするぞ!」と、まるで宝探しゲームをしているかのよう。
でも、この能力が人間にとっては厄介の種。
庭や家の周りの食べ物の匂いを嗅ぎつけて、どんどん近づいてきちゃうんです。
「あれ?ゴミ箱が荒らされてる...」なんてことになりかねません。
アライグマの嗅覚パワーを知れば知るほど、食べ物の管理の大切さがわかりますね。
匂いを漂わせない工夫が、アライグマ対策の第一歩なのです。
夜行性のアライグマ!食料探索のピークタイムとは
アライグマの食料探索は、夜になると本格的に始まります。日が沈むとともに、彼らの活動時間がスタート。
まさに「夜の帝王」と呼ぶにふさわしい行動パターンなんです。
アライグマの食料探索のピークタイムは、夕方から真夜中にかけて。
特に、日没後2〜3時間がもっとも活発になる時間帯です。
「さあ、今夜も美味しいものを探しに行くぞ!」とばかりに、こっそりと行動を開始するんです。
夜行性のアライグマの特徴をまとめると:
- 視覚:夜間視力が人間の約8倍
- 聴覚:小さな物音も聞き逃さない
- 行動範囲:1晩で最大約5キロメートル移動
- 探索時間:1回の外出で3〜5時間
「あれ?何か庭を歩いてる?」なんて思ったら、きっとアライグマの食料探索が始まったサイン。
この夜行性という特徴を知っておくと、対策も立てやすくなります。
例えば、夕方にはペットフードを片付ける、夜間はゴミ箱を屋内に入れるなど。
「夜になったら要注意!」と心に留めておけば、アライグマの被害を減らせる可能性が高くなるんです。
夜型生活のアライグマ。
その行動パターンを理解すれば、私たちの生活との「すみ分け」も上手くいくはず。
夜の庭を歩く影に気をつけましょう。
庭の果樹や野菜が狙われる!アライグマの好物リスト
アライグマは庭の果樹や野菜が大好物。まるで「自然のビュッフェ」のように、あれこれと食べ歩きます。
特に甘くて柔らかい果物や野菜が狙われやすいんです。
アライグマの好物リストを見てみましょう:
- 果物:リンゴ、イチゴ、スイカ、ブドウ
- 野菜:トマト、キュウリ、ナス、トウモロコシ
- 根菜類:ジャガイモ、サツマイモ、ニンジン
- その他:メロン、カボチャ、柿
実は、アライグマは雑食性で、様々な食べ物を美味しくいただいちゃうんです。
特に注意が必要なのは、熟した果実。
甘い香りが漂うと、アライグマの鼻がクンクン。
「おっ、美味しそうな匂いがする!」と、まっしぐらに向かってきます。
でも、困ったことに彼らは「一度に少しずつ」食べる習性があるんです。
「今日はリンゴを少し、明日はトマトを少し」なんて具合に。
そのため、被害に気づくのが遅れがちです。
対策としては、収穫前の果実にネットをかけたり、低い位置になる果実や野菜は早めに収穫したりするのが効果的。
「ここは人間の食べ物だよ!」とアピールすることが大切なんです。
庭が豊かなほど、アライグマにとっては魅力的。
でも、ちょっとした工夫で、私たちの大切な収穫物を守ることができるんです。
アライグマの好物を知って、賢く対策を立てましょう。
ペットフードに注意!アライグマを引き寄せる意外な誘因
ペットフードがアライグマを引き寄せる、意外な誘因になっているってご存知でしたか?実は、ペットフードはアライグマにとって「宝の山」なんです。
なぜペットフードがアライグマを引き寄せるのか、その理由は:
- 高カロリーで栄養価が高い
- 強い香りがする
- 食べやすい大きさでまとまっている
- 常に同じ場所にある(予測しやすい)
でも、アライグマにとっては、ペットフードは「手軽で美味しい食事」そのもの。
特に屋外に置いたままのペットフードは、アライグマを招く赤信号です。
アライグマは鋭い嗅覚で、ペットフードの匂いを遠くからも感知します。
「むむ、この香ばしい匂いは...」と、ペットフードの置いてある場所まで真っすぐやってくるんです。
対策として、以下のことを心がけましょう:
- ペットフードは屋内で保管する
- 屋外での給餌は日中のみにし、夜は餌皿を片付ける
- 使用後のペットフード容器はよく洗う
- 餌やりの場所を定期的に変える
時間を決めて少量ずつ出てくるタイプなら、アライグマの被害を減らせる可能性が高いんです。
ペットフードの管理は、実はアライグマ対策の重要なポイント。
愛するペットのためにも、アライグマを寄せ付けない工夫をしてみましょう。
小さな心がけが、大きな効果を生むんです。
アライグマの食料探索は「やっちゃダメ!」な行動を招く
アライグマの食料探索行動は、私たちの「やっちゃダメ!」な行動を引き起こしやすいんです。知らず知らずのうちに、アライグマを呼び寄せてしまう行動をとっていることがあるんです。
まず、絶対にやってはいけないのが、アライグマに直接餌を与えること。
「かわいそうだから」という気持ちはわかりますが、これは大問題。
餌付けされたアライグマは人間を恐れなくなり、より大胆に食料を探すようになってしまいます。
他にも、こんな行動は要注意です:
- 生ごみを適切に管理せずに外に置く
- 果物の落ち葉を放置する
- バーベキューの後片付けを怠る
- コンポストを開けっ放しにする
- 屋外に食べ物を置いたまま忘れる
でも、アライグマにとっては、これらすべてが「おいしそうな匂いのする場所」なんです。
特に注意したいのが、夜間の行動です。
「ちょっとだけなら...」と思って、夜に庭に食べ物を置いたり、ゴミを出したりするのは大きな誘因になります。
アライグマは「ここに食べ物がある」と学習してしまい、毎晩やってくるようになってしまうんです。
対策としては、以下のことを心がけましょう:
- 食べ物は必ず屋内で保管する
- ゴミは密閉容器に入れ、収集日の朝に出す
- 庭の手入れをこまめにする
- 屋外での食事後は徹底的に清掃する
でも、これらの小さな心がけが、アライグマの被害を大きく減らすことにつながるんです。
アライグマの食料探索行動を知ることで、私たちの「うっかり行動」も減らせます。
賢く対策を立てて、アライグマとの共存を目指しましょう。
自然環境vs人工環境!アライグマの食料探索の違い

自然環境での広範囲探索vs人工環境での効率的探索
アライグマの食料探索行動は、自然環境と人工環境で大きく異なります。自然界では広範囲を移動しながら多様な食べ物を探すのに対し、人工環境では特定の場所に集中して効率よく探索するんです。
まず、自然環境でのアライグマの行動を見てみましょう。
「今日はどこで食事にありつけるかな?」と、広い範囲を歩き回ります。
森や川辺を探索し、木の実や小動物、魚などを見つけては食べる。
そんな具合です。
- 1晩で2〜3キロメートル移動することも
- 季節によって探索場所を変える
- 様々な食材を少しずつ食べる
- 群れで行動することもある
「ここに食べ物があったはず」と、前に食べ物を見つけた場所を覚えていて、そこを集中的に探索するんです。
- ゴミ置き場や庭を重点的に探る
- 人間の生活リズムに合わせて行動する
- 特定の食べ物(例:ペットフード)に執着する
- 単独行動が多い
自然環境は広いレストラン街を歩き回って食事を探すのに似ています。
対して人工環境は、おいしい料理が並ぶビュッフェコーナーを効率よく回るのに似ているんです。
「え?じゃあ人工環境のほうが楽じゃない?」と思うかもしれません。
確かに効率は良いのですが、人間との接触リスクが高まるという問題もあるんです。
この行動の違いを理解することで、より効果的な対策が立てられます。
例えば、人工環境では食べ物の管理を徹底することが重要。
自然環境に近い庭では、アライグマが好む植物を避けるなどの工夫が効果的です。
環境に合わせた対策で、アライグマとの上手な付き合い方を見つけていきましょう。
自然の食材vs人工的な食べ物!アライグマの食性の変化
アライグマの食性は、自然環境と人工環境で大きく変化します。本来の食性と、人間社会に適応した結果の食性には、驚くほどの違いがあるんです。
自然環境でのアライグマの食事メニューは、とってもバラエティ豊か。
「今日は何を食べようかな」と、季節や場所に応じて様々な食材を選びます。
- 果実:野イチゴ、木の実など
- 小動物:ネズミ、カエル、魚など
- 昆虫:カブトムシ、バッタなど
- 植物の根や茎
栄養バランスも取れていて、体に良い食生活と言えるでしょう。
一方、人工環境に適応したアライグマの食生活は、ガラッと変わります。
「人間の食べ物、おいしいじゃん!」と、人工的な食べ物にどんどんハマっていくんです。
- 生ゴミ:残飯、果物の皮など
- ペットフード:栄養価が高く大好物
- 庭の果樹:柿、ブドウなど
- コンポスト:生ゴミの宝庫
でも、「ちょっと待って!これ、健康的じゃないよね?」と心配になりますよね。
実は、この食性の変化がアライグマにとっても、人間にとっても問題なんです。
アライグマは栄養バランスが崩れて健康を害したり、人工的な食べ物への依存度が高まったりします。
人間側も、ゴミ荒らしや農作物被害などの問題に直面することに。
この食性の変化を理解することで、効果的な対策が立てられます。
例えば、ゴミの管理を徹底したり、庭の果樹に保護ネットを張ったりするのが有効です。
「アライグマさん、自然の食べ物のほうが体にいいよ」と、さりげなく自然の食材に誘導する工夫も大切かもしれません。
アライグマと人間、お互いが健康で幸せな共存を目指すには、この食性の違いを知ることが第一歩。
賢い対策で、みんなが笑顔になれる環境づくりを心がけましょう。
コンポストvs生ゴミ!アライグマが好む食料源の比較
アライグマにとって、コンポストと生ゴミは魅力的な食料源です。でも、その魅力度には違いがあるんです。
両者を比較して、アライグマ対策のヒントを見つけていきましょう。
まず、コンポストから見ていきます。
コンポストは、アライグマにとって「自然の宝箱」のような存在。
- 様々な有機物が混ざっている
- 発酵過程で香りが強くなる
- 虫や小動物も集まってくる
- 季節を通じて利用できる
栄養価も高く、自然の食べ物に近い組成なので、健康的な食事になるんです。
一方、生ゴミはどうでしょうか。
こちらは「人工的な食べ物の宝庫」と言えます。
- 調理済みの食品が多い
- 高カロリーな食べ物が含まれる
- 強い香りを放つ
- 定期的に新鮮な物が追加される
でも、栄養バランスは偏りがちで、健康面では問題があります。
では、アライグマはどちらを好むのでしょうか?
実は、両方が大好物なんです。
ただし、生ゴミのほうがより強く引き寄せられる傾向があります。
香りが強く、すぐに食べられる状態だからです。
この違いを踏まえて、対策を考えてみましょう。
- コンポスト対策:蓋付きの容器を使用し、周囲にワイヤーメッシュを設置する
- 生ゴミ対策:密閉容器に入れ、収集日まで屋内で保管する
- 共通対策:周囲に忌避剤を撒く、夜間はライトで明るくする
でも、一度アライグマに食料源として認識されると、繰り返し訪れるようになるんです。
だから、事前の対策が重要なんです。
コンポストと生ゴミ、どちらもアライグマにとっては魅力的な食料源。
でも、適切な管理をすれば、アライグマを寄せ付けない環境づくりができます。
「アライグマさん、ごめんね。でもここは人間の食べ物だから」と、やさしくも毅然とした態度で接していきましょう。
屋外料理の匂いに注意!アライグマを引き寄せる人間の行動
屋外料理の匂いは、アライグマを引き寄せる強力な誘因になります。バーベキューやキャンプの楽しい思い出が、思わぬトラブルを招くかもしれないんです。
アライグマにとって、屋外料理の匂いは「ごちそうさまのお知らせ」のようなもの。
その鋭い嗅覚で、遠くからでも香りを感じ取ります。
- 焼肉の香ばしい匂い
- 魚を焼く香り
- フライドポテトの油っぽい匂い
- 甘いデザートの香り
まるで漫画のように、匂いに誘われてフワフワ浮いて近づいてきそうです。
特に注意が必要なのは、料理後の後片付けです。
うっかり忘れがちな以下の点に気をつけましょう。
- 食べ残しをそのまま放置する
- 使用した調理器具を洗わずに置いておく
- ゴミ袋を屋外に置きっぱなしにする
- グリルの油を落とさずにそのままにする
では、どうすればいいのでしょうか?
屋外料理を楽しみつつ、アライグマ対策もばっちり決めるコツをご紹介します。
- 食べ終わったらすぐに片付ける
- 使用した調理器具はその場で洗う
- ゴミは密閉容器に入れて屋内で保管
- グリルは使用後にしっかり洗浄
- 食べ物や飲み物を屋外に放置しない
でも、これらの対策は、アライグマだけでなく他の野生動物対策にもなるんです。
屋外料理を楽しんだ後は、「きれいに片付けて、アライグマさんにバイバイ」と心がけましょう。
ちょっとした心遣いで、人間もアライグマも幸せな関係が築けるはず。
自然を大切にしながら、楽しい屋外料理の思い出を作りましょう。
アライグマの行動範囲!自然と都市部での違いに驚愕
アライグマの行動範囲は、自然環境と都市部で驚くほど違います。この違いを知ることで、効果的な対策が立てられるんです。
まず、自然環境でのアライグマの行動範囲を見てみましょう。
- オスの行動範囲:最大で1〜4平方キロメートル
- メスの行動範囲:0.5〜2平方キロメートル
- 1晩の移動距離:最大で3〜5キロメートル
- 季節による変動:繁殖期や冬季は範囲が縮小
自然界では、食べ物を探して広い範囲を探索する必要があるんです。
まるで、大きな自然公園を散歩しているような感じですね。
一方、都市部でのアライグマの行動範囲はどうでしょうか。
- 平均的な行動範囲:0.2〜0.6平方キロメートル
- 1晩の移動距離:1キロメートル未満が多い
- 特定の場所への依存:ゴミ置き場や庭を中心に行動
- 建物内での生活:屋根裏や物置を住処にすることも
都市部では、コンパクトな範囲で効率よく食べ物を見つけられるんです。
例えるなら、便利な町中のアパートに住んでいるようなものです。
この行動範囲の違いは、アライグマの生活スタイルを大きく変えます。
自然環境では広く薄く分布するのに対し、都市部では特定の場所に集中して生息するようになるんです。
では、この違いを踏まえて、どんな対策が効果的でしょうか?
- 都市部では:食べ物が集中している場所を重点的に管理する
- ゴミ箱は蓋付きの頑丈なものを使用
- 庭の果樹には保護ネットを設置
- ペットフードは屋内で保管
- 自然環境:広範囲に対策を施す
- フェンスやネットで広い範囲を囲む
- 忌避剤を広範囲に散布
- 野生動物用の給餌所を設置して誘導
アライグマの行動範囲を理解することで、より効果的な対策が立てられるんです。
都市部では集中的に、自然環境では広範囲に。
それぞれの環境に合わせた対策を心がけることで、アライグマとの上手な付き合い方が見つかるはずです。
「アライグマさん、お互いの領域を尊重しようね」という気持ちで、共存の道を探っていきましょう。
アライグマの食料探索を防ぐ効果的な対策

庭の果樹や野菜を守る!簡単3ステップ対策法
庭の果樹や野菜をアライグマから守るには、3つの簡単なステップを実践することが効果的です。これらの対策を組み合わせることで、被害を大幅に減らすことができます。
まず、ステップ1は「物理的な障壁を作る」ことです。
アライグマは器用な動物ですが、適切な防護ネットや柵を設置することで侵入を防ぐことができます。
- 果樹には細かい網目のネットをかぶせる
- 野菜畑の周りに高さ1.5メートル以上の柵を設置
- 柵の下部は地中に30センチほど埋める
でも、一度やってしまえば長期的な効果が期待できるんです。
ステップ2は「光と音を活用する」ことです。
アライグマは警戒心が強い動物なので、突然の光や音に驚いて逃げてしまいます。
- 動きを感知して点灯する照明を設置
- 風で鳴る風鈴やカラカラ
- ラジオを低音量で夜通し流す
むしろ、ご近所さんと協力して対策するのも良いアイデアです。
ステップ3は「香りで撃退する」ことです。
アライグマの鋭い嗅覚を逆手にとって、嫌いな匂いで寄せ付けないようにします。
- 唐辛子やわさびのパウダーを撒く
- アンモニア臭のする布を吊るす
- 柑橘系の果物の皮を置く
これら3つのステップを組み合わせることで、アライグマの被害を大幅に減らすことができます。
「よし、明日から実践してみよう!」という気持ちになりましたか?
少しずつでも始めてみることが大切です。
アライグマと上手に付き合いながら、美しい庭を守りましょう。
ペットフード管理のコツ!アライグマ対策の新常識
ペットフードの管理は、アライグマ対策の新しい常識として注目されています。実は、ペットフードがアライグマを引き寄せる大きな要因になっているんです。
まず、覚えておきたいのは「ペットフードは宝の山」ということ。
アライグマにとって、ペットフードは栄養価が高く、簡単に手に入る理想的な食べ物なんです。
「えっ、うちの犬のごはんがアライグマのごちそう?」と驚くかもしれませんね。
では、具体的な対策を見ていきましょう。
- 屋内給餌の徹底
- ペットの食事は必ず屋内で
- 食べ終わったら速やかに片付ける
- 保管場所の工夫
- 密閉容器を使用
- 涼しく乾燥した場所で保管
- 夜間の対策
- 日没後は餌皿を屋内に
- 屋外の給餌器は毎晩洗浄
そんな時は、時間式の自動給餌器を活用するのもいいアイデア。
必要な分だけ出てくるので、余分な餌をアライグマに狙われる心配がありません。
さらに、ペットフードの種類にも注目です。
強い匂いのするものは、アライグマを引き寄せやすいんです。
「あれ?いつもと違う匂いがする」とアライグマの鼻がクンクン。
できれば、匂いの控えめなタイプを選ぶのがおすすめです。
ペットフードの管理は、実はアライグマ対策の要。
「ちょっとした心がけで、大きな効果が得られる」というわけです。
愛するペットのためにも、アライグマとの共存のためにも、新しい習慣を身につけていきましょう。
家族みんなで協力すれば、きっとうまくいくはずです。
コンポスト活用のすすめ!アライグマを寄せ付けない工夫
コンポストは環境に優しい取り組みですが、アライグマを引き寄せる原因にもなりかねません。でも、ちょっとした工夫で両立できるんです。
アライグマを寄せ付けないコンポスト活用法、覚えていきましょう。
まず大切なのは、コンポストの「中身選び」です。
アライグマは肉や乳製品の匂いに敏感。
これらをコンポストに入れると「おいしそうな匂いがする!」とアライグマが寄ってきちゃいます。
- 入れてOKなもの
- 野菜くず
- 果物の皮
- 落ち葉
- 草刈りくず
- 入れてはダメなもの
- 肉類
- 魚
- 乳製品
- 油っこいもの
開放型のコンポストは、アライグマにとって「オープンビュッフェ」同然。
密閉型の容器を選ぶことで、匂いを閉じ込め、アライグマの侵入も防げます。
- 蓋つきの密閉型容器を使用
- 容器の周りに金網を設置
- 容器の底も塞ぐ(アライグマは下から掘ることも)
「家の近くなら安全だろう」と思いがちですが、実はそれが間違い。
アライグマは人間の生活圏に慣れています。
- 家から離れた場所に設置
- 周囲に光センサー付きライトを設置
- 定期的に中身をかき混ぜる(発酵を促進し、匂いを抑える)
でも、これらの対策はアライグマだけでなく、他の野生動物対策にもなるんです。
コンポスト活用は、環境にも家計にも優しい素晴らしい取り組み。
アライグマ対策をしながら、上手に続けていきましょう。
「環境にもアライグマにも優しい暮らし」、素敵じゃありませんか?
屋外での調理や食事後の注意点!匂い対策が鍵
屋外での調理や食事は楽しいものですが、アライグマを引き寄せる原因にもなります。でも、大丈夫。
ちょっとした注意点を押さえれば、アライグマを寄せ付けずに楽しむことができるんです。
まず、調理中の注意点から見ていきましょう。
アライグマは匂いに敏感。
「わぁ、おいしそう!」と遠くからやってくる可能性があります。
- 風向きを考えて調理場所を選ぶ
- 蓋付きの調理器具を使用
- こぼれた食材はすぐに拭き取る
「ちょっと席を外すくらいいいか」なんて思っていると、アライグマのごちそうになっちゃうかも。
- 食べ物を放置しない
- 飲み物もフタ付きの容器を使用
- 子どもの食べこぼしにも注意
ここをおろそかにすると、アライグマにとっては「また来てね」のサインになってしまいます。
- 食べ残しは必ず持ち帰る
- 使用した調理器具はその場で洗う
- ゴミは密閉して屋内で保管
- バーベキューグリルは完全に冷めてから洗浄
- 食事スペースを掃除し、匂いを消す
でも、これらの対策は他の野生動物対策にもなるんです。
自然を楽しみながら、自然と共存する。
そんな素敵な屋外での食事時間を過ごしましょう。
匂い対策の裏技をひとつ。
レモンやオレンジなどの柑橘系の皮を食事スペースに置いておくと、アライグマを寄せ付けにくくなります。
「いい匂いだな〜」と人間は喜びますが、アライグマは「うーん、ちょっと苦手」なんです。
屋外での調理や食事を楽しみつつ、アライグマ対策もばっちり。
そんな素敵な時間を過ごせるようになりましたね。
さあ、みんなで楽しい思い出を作りましょう!
驚きの裏技!身近なもので作るアライグマ撃退スプレー
アライグマ対策の新兵器、それが身近なもので作れる撃退スプレーです。簡単に作れて効果抜群。
しかも、環境にも優しい。
これを知れば、アライグマ対策がぐっと楽になりますよ。
まず、基本の材料を紹介します。
どれも家にあるものばかり。
「えっ、こんなもので大丈夫なの?」って思うかもしれませんが、アライグマの鋭い嗅覚を利用した裏技なんです。
- 水(1リットル)
- 唐辛子パウダー(大さじ1)
- にんにく(2かけ)
- ペパーミントオイル(10滴)
材料を全部混ぜて、一晩置くだけ。
「ふむふむ、これならできそう」って感じですよね。
さて、この撃退スプレーの使い方ですが、アライグマが来そうな場所に吹きかけるだけ。
例えば、こんな場所です。
- 庭の境界線
- ゴミ箱の周り
- コンポストの周辺
- 果樹の根元
- 家の外壁の下部
実は、この組み合わせがアライグマにとっては最悪の匂いの cocktail なんです。
唐辛子の辛さ、にんにくの強烈な匂い、ペパーミントの清涼感。
これらが混ざると、アライグマは「うわっ、なんだこの匂い!」って逃げ出しちゃうんです。
使用する時の注意点もあります。
雨が降ったら効果が薄れるので、再度吹きかける必要があります。
また、野菜や果物に直接かけるのは避けましょう。
食べる時に困っちゃいますからね。
この撃退スプレー、実は他の野生動物対策にも効果があるんです。
一石二鳥、いや一石三鳥くらいの効果があるかも。
「よーし、今日から作ってみよう!」という気持ちになりましたか?
簡単で効果的、そして環境にも優しい。
そんなアライグマ対策、素敵じゃありませんか。