アライグマ対策に効く柵とフェンス【高さ1.5m以上が必須】選び方と設置のコツを徹底解説

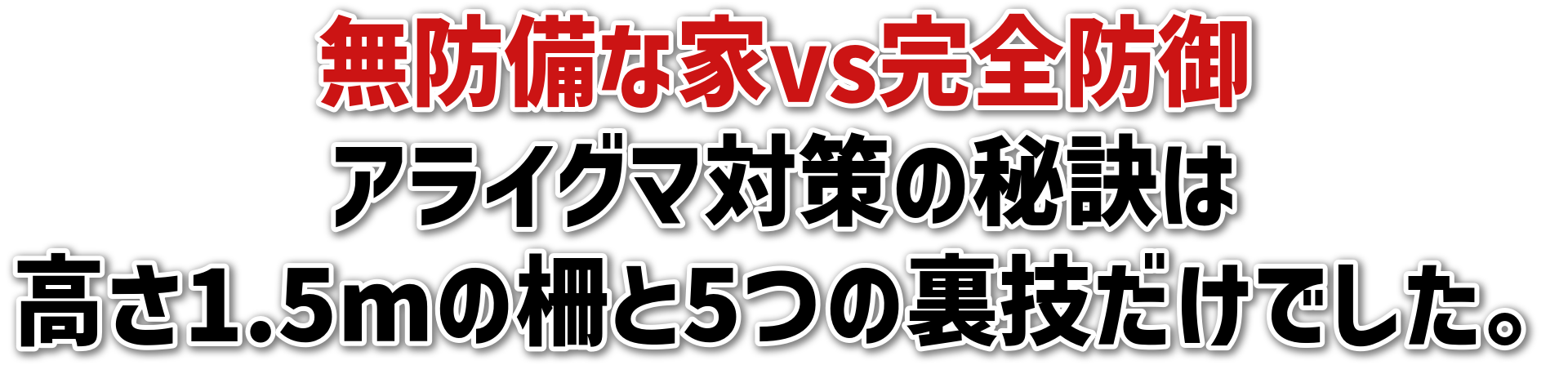
【この記事に書かれてあること】
アライグマの侵入に悩まされていませんか?- アライグマ対策には高さ1.5m以上の柵やフェンスが効果的
- 金属製や硬質プラスチック製の耐久性の高い素材を選ぶ
- 地中に30cm以上埋めることで掘り返し防止に
- 月1回の点検で破損や緩みを早期発見
- ローラーや滑りやすい素材を組み合わせて防御力アップ
そんなあなたに、驚くほど効果的な対策をお教えします。
実は、適切な柵やフェンスを設置するだけで、アライグマの侵入を劇的に防げるんです。
でも、ただ高いだけじゃダメ。
材質や設置方法にも秘訣があるんです。
「えっ、そんな簡単なの?」って思うかもしれませんが、大丈夫。
この記事を読めば、あなたもアライグマ対策のプロになれちゃいます。
さあ、一緒にアライグマとの知恵比べ、始めましょう!
【もくじ】
アライグマ対策に効く柵とフェンスの特徴

高さ1.5m以上が必須!アライグマの跳躍力に注意
アライグマ対策の柵やフェンスは、高さ1.5m以上が絶対条件です。これより低いと、あっという間に乗り越えられちゃうんです。
アライグマって、見た目はかわいいのに、実はすごい運動能力の持ち主なんです。
特に跳躍力がすごくて、なんと垂直に1.5mも跳び上がることができるんです。
「えっ、そんなに!?」って驚きますよね。
だから、柵やフェンスを設置するときは、この跳躍力を甘く見ないことが大切。
高さ1.5m以上あれば、アライグマが簡単に越えられないので、侵入を防ぐ効果が格段に上がります。
でも、もっと安心したいなら、2m以上の高さがおすすめです。
こうすれば、アライグマも「うーん、高すぎて無理かも…」って諦めちゃうかもしれません。
ただし、注意点があります。
- 斜面や起伏のある地形では、最も低い地点で1.5m以上の高さを確保すること
- 柵やフェンスの近くに木や物置がないか確認すること(足場になっちゃうので要注意!
) - 定期的に点検して、高さが維持されているか確認すること
高さだけでなく、他の特徴も組み合わせれば、さらに効果アップ!
次は、素材選びのコツを見ていきましょう。
金属製か硬質プラスチック製!耐久性重視の選び方
アライグマ対策の柵やフェンスは、金属製か硬質プラスチック製を選ぶのがベストです。これらの素材なら、アライグマの鋭い歯や爪にも負けません!
アライグマって、見た目はふわふわしてるけど、実は結構な力持ちなんです。
木製の柵なんて、ガジガジと噛み砕いちゃうこともあるんです。
「まるでビーバーみたい!」なんて笑えない状況になっちゃいます。
そこで、おすすめなのが金属製と硬質プラスチック製。
これらの特徴を見てみましょう。
- 金属製(ステンレスやアルミニウム)
- 耐久性抜群!
長持ちします
- 噛み切られる心配なし
- さびにくい素材を選べば、メンテナンスも楽チン - 硬質プラスチック製
- 軽くて扱いやすい
- 耐候性が高く、劣化しにくい
- 比較的安価
でも、長期的に見れば、金属製の方がコスパは良いかもしれません。
「でも、見た目が気になる…」という方には、カモフラージュネットを被せるという裏技も。
アライグマの目を欺くだけでなく、お庭の雰囲気も損なわずに済みますよ。
素材選びで大切なのは、アライグマの習性を理解すること。
彼らは賢くて器用なので、弱点を見つけては突いてきます。
だからこそ、丈夫で耐久性のある素材を選ぶことが、長期的な対策の鍵となるんです。
網目のサイズは5cm四方以下!隙間を作らない
アライグマ対策の柵やフェンスを選ぶとき、網目のサイズは5cm四方以下にするのがポイントです。これより大きいと、すり抜けられちゃう危険性が高まります。
アライグマってね、体はぽっちゃりしてるように見えるけど、実はすごく柔軟なんです。
「えっ、そんな小さな隙間に入れるの?」って思うような狭い場所でも、スルッと通り抜けちゃうんです。
まるでニンジャのよう!
だから、網目のサイズ選びが重要になってきます。
5cm四方以下なら、アライグマの体がすり抜けるのを防げます。
でも、それだけじゃないんです。
この小さな網目には、こんな効果もあるんです。
- アライグマの爪がひっかかりにくくなる
- 登りにくくなるので、柵を越えられにくい
- 子アライグマの侵入も防げる
大丈夫!
最近は、デザイン性の高い小さな網目の柵やフェンスも増えてきています。
お庭の雰囲気を損なわずに、しっかり守れるんです。
ちなみに、網目が小さいと風通しが悪くなるんじゃない?
って思う人もいるかも。
でも、5cm四方程度なら、風通しはほとんど変わりません。
むしろ、プライバシーの保護にもなるので一石二鳥なんです。
網目選びの極意は、「アライグマの目線で考える」こと。
彼らの体の大きさや動きを想像しながら選べば、効果的な対策ができますよ。
小さな網目で、大きな安心を手に入れましょう!
地中に30cm以上埋める!掘り返し防止が重要
アライグマ対策の柵やフェンスは、地中に30cm以上埋め込むことが超重要です。これで、下から潜り込まれるのを防げるんです。
アライグマって、見た目はゆるふわだけど、実は掘るのが得意なんです。
「まるでモグラみたい!」って思うくらい、器用に土を掘り返しちゃうんです。
だから、地上だけの対策じゃ不十分なんです。
地中に深く埋め込むことで、こんなメリットがあります。
- 掘り返し防止
- アライグマが下から潜り込むのを阻止 - 柵やフェンスの安定性アップ
- 強風でも倒れにくくなる - 長期的な効果
- 地盤沈下などの影響を受けにくい
確かに手間はかかりますが、この作業を怠ると、せっかくの対策が水の泡になっちゃうんです。
掘り返し対策の裏技をいくつか紹介しますね。
- 柵やフェンスの周囲に砂利や小石を敷き詰める
- 地中部分にL字型の金網を取り付ける
- コンクリートで基礎を作る
アライグマも「ここは無理だな〜」ってあきらめちゃうかも。
地中への埋め込みは、目に見えない部分だからこそ重要なんです。
「備えあれば憂いなし」のことわざどおり、しっかり対策して、安心できる環境を作りましょう。
アライグマに「お邪魔虫」にならせないためにね!
上部を内側に45度折り返す!乗り越え対策も忘れずに
アライグマ対策の柵やフェンスは、上部を内側に45度、15〜20cm折り返すのが効果的です。これで、アライグマが柵を乗り越えるのをグッと難しくできるんです。
アライグマって、まるでサーカスの曲芸師みたいに器用なんです。
普通の柵やフェンスなら、スイスイっと登って、あっという間に乗り越えちゃうんです。
「えっ、そんなに簡単に!?」って驚くくらい。
でも、上部を内側に折り返すと、状況が一変します。
アライグマが柵の上に来たとき、
「おっ、もうちょっとで越えられる!」
↓
「あれ?なんか変だぞ…」
↓
「うわっ、倒れそう!」
って感じで、バランスを崩しちゃうんです。
これが、乗り越え防止の秘訣なんです。
この方法のメリットは他にもあります。
- 見た目もスマート(ごつごつした印象が減る)
- 人間の侵入も防げる(防犯効果もアップ)
- 風の抵抗が減る(台風対策にも◎)
大丈夫!
最近は、最初から折り返し加工されている製品も多いんです。
DIYが苦手な人でも、簡単に設置できますよ。
ちなみに、折り返し部分に滑りやすい素材(ツルツルのプラスチックなど)を付けると、さらに効果アップ!
アライグマの爪がひっかからず、「あれ〜?全然登れないよ〜」ってなっちゃいます。
上部の折り返しは、アライグマ対策の仕上げの技みたいなもの。
これで、柵やフェンスが完璧な防御壁に変身します。
アライグマに「ここはお断り!」ってメッセージを送れるんです。
効果的な柵とフェンスの設置とメンテナンス
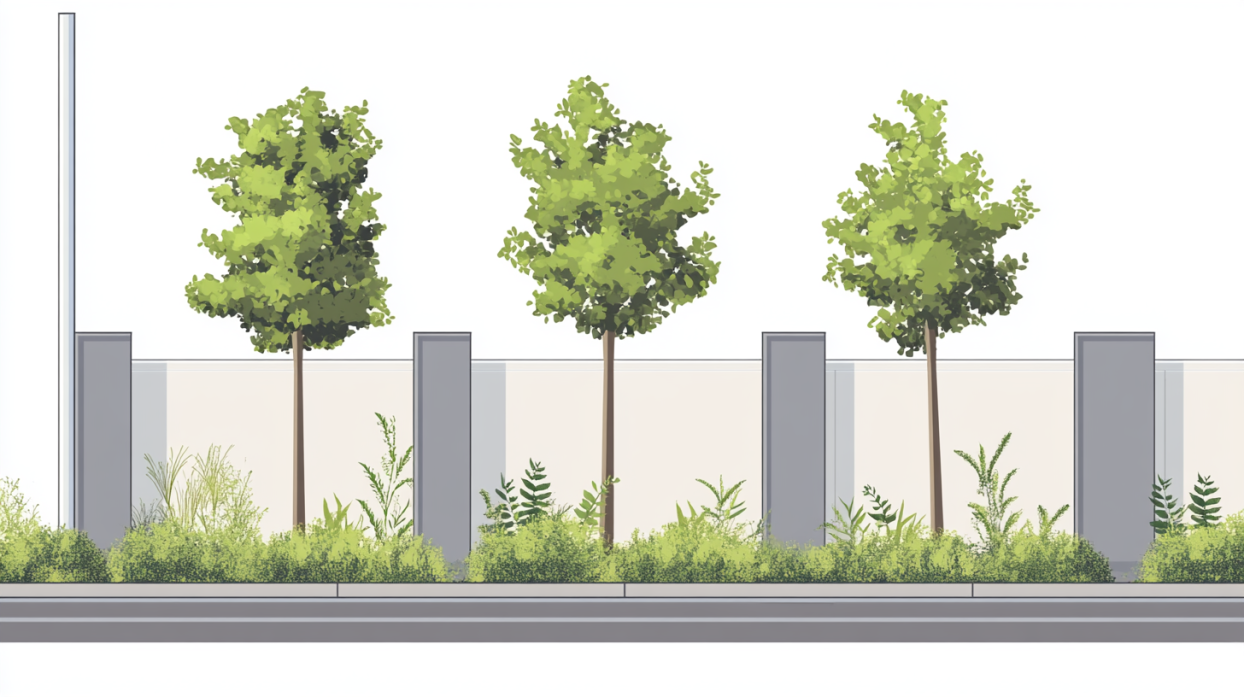
支柱は3mごとにコンクリート固定!強度確保のコツ
アライグマ対策の柵やフェンスを設置する際、支柱は3mごとにコンクリートで固定するのがコツです。これで十分な強度が確保できます。
支柱はアライグマ対策の柵やフェンスの要。
しっかりと固定しないと、アライグマに押し倒されちゃうかもしれません。
「えっ、そんな力持ちなの?」って思うかもしれませんが、アライグマは意外と力が強いんです。
では、具体的な設置方法を見ていきましょう。
- 支柱を地中に50cm以上埋め込む
- 穴にコンクリートを流し込み、支柱を固定
- 3mごとに支柱を設置していく
- 支柱が完全に乾くまで24時間以上待つ
でも、これくらいの間隔だと、アライグマが柵を押しても、びくともしないんです。
ちなみに、支柱の材質は金属製がおすすめ。
木製だと、アライグマにかじられちゃう可能性があるんです。
「まるでビーバーみたい!」なんて笑い事じゃありません。
支柱をしっかり固定すれば、台風が来ても大丈夫。
アライグマだけでなく、強風対策にもなるんです。
一石二鳥ですね!
設置作業は少し大変かもしれませんが、がんばって!
「よーし、これでアライグマさんお断りだぞ!」って気持ちで頑張りましょう。
建物との接続部分に注意!隙間なく密着させる
アライグマ対策の柵やフェンスを設置する時、建物との接続部分は隙間なく密着させることが超重要です。ここを甘く見ると、せっかくの対策が水の泡になっちゃいます。
アライグマって、まるで忍者のように小さな隙間を見つけては侵入してくるんです。
「えっ、そんな器用なの?」って驚くかもしれませんが、本当なんです。
だから、建物との接続部分には特に気を付けましょう。
では、具体的な対策方法を見ていきましょう。
- 柵やフェンスを建物にぴったりとくっつける
- 隙間があれば、金属板やプラスチック板で補強
- 接続部分の地面も掘り返されないよう、コンクリートで固める
- 建物の壁面に沿って、柵やフェンスを少し上まで延長する
でも、アライグマは本当に賢くて、ちょっとした隙をついてくるんです。
油断大敵ですよ。
接続部分の処理で気を付けたいのが、見た目です。
ガチガチに固めすぎると、なんだか要塞みたいになっちゃいますよね。
「うちは城じゃないんだけど…」なんて悩まなくても大丈夫。
最近は見た目もスッキリした補強材料がたくさんあるんです。
建物との接続部分をしっかり処理すれば、アライグマ対策はバッチリ。
「よーし、これで完璧だ!」って自信を持てるはずです。
家族みんなで安心して暮らせる環境づくりの第一歩、がんばりましょう!
月1回の点検が理想的!破損や緩みを早期発見
アライグマ対策の柵やフェンスは、月1回の点検が理想的です。こまめにチェックすることで、破損や緩みを早期発見できるんです。
「えっ、毎月チェックするの?面倒くさそう…」って思うかもしれませんね。
でも、アライグマは賢くて、ちょっとした隙も見逃しません。
定期点検は、そんなアライグマに「ここは入れないよ?」ってメッセージを送るようなものなんです。
では、具体的な点検方法を見ていきましょう。
- 目視で全体をチェック(破損や傾きがないか)
- 支柱をゆすって、グラつきがないか確認
- 金網や板に緩みがないかチェック
- 地面との隙間ができていないか確認
- 建物との接続部分に隙間ができていないか確認
小さな問題も、放っておくとどんどん大きくなっちゃうんです。
ちなみに、点検のコツは「アライグマ目線」で見ること。
「もし自分がアライグマだったら、どこから入ろうとするかな?」なんて考えながら点検すると、見落としも少なくなりますよ。
点検は、家族みんなで協力するのもいいかもしれません。
「よーし、今日はアライグマパトロールの日だぞ!」なんて、ちょっとしたイベント感覚で楽しむのもアリですね。
定期点検を習慣づければ、アライグマ対策はもっと効果的に。
安心して暮らせる環境づくりの第一歩、みんなで頑張りましょう!
周囲1m以内の草木は定期的に刈り込み!足場を作らない
アライグマ対策の柵やフェンスを設置したら、その周囲1m以内の草木は定期的に刈り込むことが大切です。これで、アライグマの足場になりそうな場所をなくせるんです。
「えっ、庭の手入れまで?」って思うかもしれませんね。
でも、アライグマはとっても器用なんです。
草木を伝って柵を乗り越えちゃうこともあるんです。
だから、周囲の環境整備も大切なんです。
では、具体的な管理方法を見ていきましょう。
- 柵やフェンスの周囲1m以内の草は、こまめに刈る
- 低木は定期的に剪定し、高さを抑える
- つる性の植物は柵に絡まないよう注意深く管理
- 落ち葉はこまめに掃除(隠れ場所になるため)
- 果樹がある場合は、落果をすぐに拾う
でも、この作業、実は一石二鳥なんです。
庭がキレイになるし、アライグマ対策にもなる。
「よーし、今日は庭の大掃除だ!」って気分で取り組めば、苦にならないかも。
ちなみに、草刈りや剪定の頻度は、季節によって変わってきます。
春から夏は成長が早いので月1回程度、秋から冬は2ヶ月に1回程度でOKです。
草木の管理は、アライグマにとっての「アクセス道路」をなくすようなもの。
「ここは通れないぞ?」ってメッセージを送っているんです。
家族みんなで協力して、アライグマに優しくないお庭作り、頑張りましょう!
金属製vs硬質プラスチック製!長期的コスト比較
アライグマ対策の柵やフェンス、金属製と硬質プラスチック製、どっちがいいの?って悩みますよね。
結論から言うと、長期的には金属製の方がコスパが良いんです。
「えっ、金属の方が高いんじゃ…?」って思うかもしれません。
確かに初期費用は高いんです。
でも、耐久性で見ると、金属製の方が断然優秀なんです。
では、具体的に比較してみましょう。
- 初期費用:
- 金属製:高い
- 硬質プラスチック製:安い - 耐久性:
- 金属製:10?15年
- 硬質プラスチック製:5?10年 - メンテナンス頻度:
- 金属製:低い
- 硬質プラスチック製:やや高い - 強度:
- 金属製:高い
- 硬質プラスチック製:やや低い
でも、長い目で見ると、金属製の方が交換頻度が少なくて済むんです。
ちなみに、金属製の中でもステンレスやアルミニウムがおすすめ。
さびにくいから、長持ちするんです。
「よーし、これで10年は安心だ!」って気分になれますよ。
硬質プラスチック製も悪くないんです。
軽くて扱いやすいし、見た目もスッキリしてます。
でも、強い衝撃には弱いんです。
「アライグマさん、そんなに体当たりしないでよ?」なんて言っても、聞いてくれませんからね。
結局のところ、予算と相談しながら選ぶのがベスト。
「うちはこれで決まり!」って自信を持って選べる柵やフェンス、きっと見つかるはずです。
アライグマ対策、一緒に頑張りましょう!
アライグマ対策の柵とフェンスを強化する裏技

柵の上部にローラーを設置!登れない仕組みを作る
アライグマ対策の柵やフェンスを強化するなら、上部にローラーを設置するのが超おすすめです。これで、アライグマが登ろうとしても、くるくる回って落ちちゃうんです。
「えっ、そんな単純な仕組みで効果あるの?」って思うかもしれませんね。
でも、これがびっくりするほど効果的なんです。
アライグマって、器用で頭がいいんですが、このローラーには太刀打ちできないんです。
ローラーの仕組みを簡単に説明すると、こんな感じです。
- 柵やフェンスの上部に、回転する筒状のものを取り付ける
- アライグマが登ろうとすると、ローラーがくるくる回る
- バランスを崩して、ポトンと落ちる
でも、アライグマにとっては全然楽しくないはず。
「うわっ、なんだこれ!」って驚いちゃうでしょうね。
ローラーの材質は、軽くて丈夫なものがいいです。
プラスチックや軽金属がおすすめ。
重すぎると回りにくくなっちゃいますからね。
設置する時のポイントは、しっかり固定すること。
ガタガタしてたら意味ないですからね。
でも、回転はスムーズにできるようにしましょう。
この裏技、見た目もちょっとおしゃれになるかも。
「我が家の柵、なんかクールでしょ?」なんて自慢できちゃいます。
アライグマ対策と庭のデザイン、一石二鳥ですね!
滑りやすい素材を組み合わせる!爪がかかりにくく
アライグマ対策の柵やフェンスをさらにパワーアップさせるなら、滑りやすい素材を組み合わせるのがおすすめです。これで、アライグマの爪がツルッと滑って、登れなくなっちゃうんです。
「滑りやすい素材って、どんなの?」って気になりますよね。
実は、身近なものでも代用できちゃうんです。
例えば、こんな素材が効果的。
- つるつるした金属板
- ツルツル仕上げのプラスチック板
- 滑り止め用の特殊塗料を塗ったもの
設置方法は簡単。
既存の柵やフェンスに、滑りやすい素材を巻き付けたり、貼り付けたりするだけ。
「よーし、今日は DIY だ!」って感じで、休日の作業にピッタリですね。
ただし、注意点もあります。
雨の日は特に滑りやすくなるので、人間も気をつけましょう。
「うわっ、転びそう!」なんてことにならないように。
この裏技、見た目もスタイリッシュになるかも。
特に金属板を使うと、モダンな雰囲気に。
「我が家の柵、おしゃれでしょ?」なんて、ご近所さんに自慢できちゃいます。
アライグマ対策と庭のイメージアップ、一石二鳥の裏技。
ぜひ試してみてくださいね!
反射板や風鈴を取り付ける!光と音で威嚇効果アップ
アライグマ対策の柵やフェンスをもっと強化したいなら、反射板や風鈴を取り付けるのが効果的です。光と音でアライグマを威嚇して、寄せ付けない環境を作るんです。
「えっ、そんな簡単なものでいいの?」って思うかもしれませんね。
でも、アライグマは意外と臆病なんです。
突然の光や音に驚いて、「うわっ、怖い!」って逃げちゃうんです。
では、具体的な方法を見てみましょう。
- 反射板の設置:
- CD や DVD の古いディスクを利用
- 小さな鏡を取り付ける
- 反射テープを貼り付ける - 風鈴の活用:
- 普通の風鈴を取り付ける
- 空き缶で手作り風鈴を作る
- 風で動く鈴付きの飾りを設置
アライグマにとっては、まるで目をつぶされるような感覚かも。
「まぶしすぎ?!」って感じでしょうね。
風鈴の音は、チリンチリンと不規則に鳴るので、アライグマを落ち着かなくさせます。
「なんだか気になる音だな?」って、警戒心を高めちゃうんです。
これらを組み合わせると、視覚と聴覚の両方からアライグマを威嚇できます。
しかも、人間にとっては心地よい演出にもなるんです。
「わ?、幻想的!」なんて、庭の雰囲気もアップしちゃいます。
ただし、近所迷惑にならないよう、音の大きさには注意してくださいね。
「うるさいなぁ」なんて言われちゃったら、元も子もありません。
この裏技、アライグマ対策と庭の演出を両立できる、素敵なアイデアです。
ぜひ、試してみてくださいね!
トゲのある植物を周囲に植える!自然な障壁に
アライグマ対策の柵やフェンスをさらに強化したいなら、周囲にトゲのある植物を植えるのがおすすめです。自然な障壁を作って、アライグマの侵入を防ぐんです。
「えっ、植物で防げるの?」って思うかもしれませんね。
でも、鋭いトゲを持つ植物は、アライグマにとって超厄介な存在なんです。
「いてっ!痛いよ?」って、近づきたくなくなっちゃうんです。
では、どんな植物がいいのか、具体的に見てみましょう。
- バラ(特に這いバラ)
- サボテン(寒さに強い種類)
- ヒイラギ
- パイナップルセージ
- ベリス
「わ?、素敵なお庭!」なんて、ご近所さんに褒められちゃうかも。
植える時のポイントは、密集させること。
隙間があると、そこから侵入されちゃう可能性があるので注意が必要です。
「よし、ギッシリ植えるぞ!」って感じで頑張りましょう。
ただし、気をつけなきゃいけないのは、人間も刺さっちゃう可能性があること。
特に子どもがいる家庭では、植える場所に注意が必要です。
「あっ、危ない!」なんてことにならないように気をつけてくださいね。
この方法のいいところは、見た目が自然なこと。
無機質な柵やフェンスだけじゃなく、緑豊かな庭の雰囲気を作れます。
「我が家の庭、まるで秘密の花園みたい!」なんて、素敵な空間になりますよ。
アライグマ対策と庭のデザイン、両方叶えちゃう素敵な裏技。
ぜひ、試してみてくださいね!
動きセンサー付きLEDライトを設置!突然の光で撃退
アライグマ対策の柵やフェンスをもっとパワーアップさせたいなら、動きセンサー付きのLEDライトを設置するのが超おすすめです。突然のピカッという光で、アライグマをびっくりさせて撃退しちゃうんです。
「えっ、ライトだけでいいの?」って思うかもしれませんね。
でも、アライグマって意外と臆病なんです。
突然の強い光に、「うわっ、何これ!」ってパニックになっちゃうんです。
では、具体的な設置方法を見てみましょう。
- 柵やフェンスの上部や周辺に、動きセンサー付きLEDライトを取り付ける
- センサーの感度を調整して、アライグマサイズの動きを検知できるようにする
- ライトの向きを、アライグマが来そうな方向に向ける
- 必要に応じて、複数のライトを設置して死角をなくす
アライグマにとっては、「わっ、まぶしい!」って感じで、びっくりして逃げ出しちゃうんです。
ただし、注意点もあります。
近所の人や車の通行にも反応しちゃう可能性があるので、センサーの向きや感度調整が重要です。
「おっと、また誤作動か」なんてことにならないように気をつけましょう。
この方法のいいところは、省エネなこと。
LEDライトなので電気代もそんなにかかりません。
「よし、これなら長期戦でも大丈夫!」って感じですね。
しかも、防犯対策にもなっちゃいます。
アライグマだけじゃなく、泥棒さんも寄り付かなくなるかも。
「我が家は二重の意味で安全だぞ!」なんて、ちょっと誇らしくなっちゃいますね。
アライグマ対策と防犯対策、一石二鳥の裏技。
ぜひ試してみてくださいね!