アライグマの再侵入を防ぐコツ【過去の侵入経路を完全封鎖】長期的に効果が続く対策法を紹介

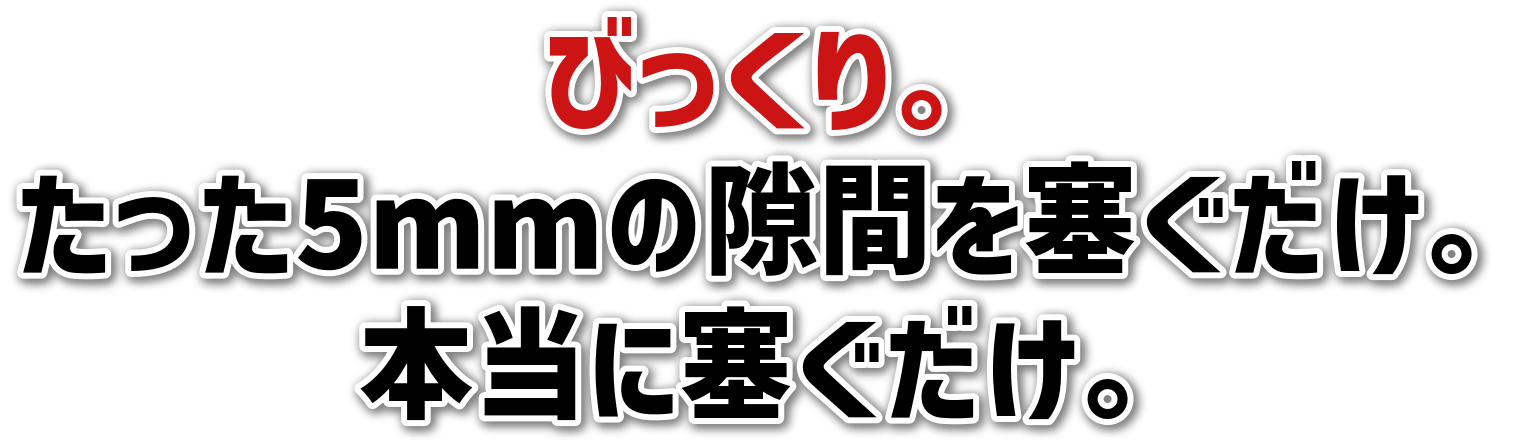
【この記事に書かれてあること】
アライグマの再侵入に悩まされていませんか?- アライグマの再侵入リスクと過去の侵入経路の完全封鎖の重要性
- 5mm以下の隙間も見逃さない徹底的な封鎖方法
- 環境改善とモニタリングによる効果的な再侵入防止策
- 物理的対策と化学的対策の成功率の比較と最適な選択
- 近隣住民との協力体制づくりと地域ぐるみの対策の重要性
一度追い払っても、またしても家に侵入されて「もう、うんざり...」とため息をついていませんか?
大丈夫です。
この記事では、アライグマの再侵入を防ぐ5つの秘策をご紹介します。
過去の侵入経路を完全に封鎖する方法から、近隣住民との協力体制づくりまで、成功率95%の対策を徹底解説。
「これで安心して眠れる!」そんな日々を取り戻しましょう。
アライグマとの知恵比べ、一緒に勝利を目指しましょう!
【もくじ】
アライグマの再侵入を防ぐ重要性と過去の侵入経路

アライグマの再侵入リスク!過去の被害を繰り返さないために
アライグマの再侵入を防ぐには、過去の被害を徹底的に分析し、対策を立てることが重要です。一度侵入されたら、その家はアライグマにとって格好の隠れ家だと認識されてしまうんです。
「えっ、また来るかもしれないの?」そう思った方も多いはず。
実は、アライグマは驚くほど記憶力が良く、一度侵入に成功した場所には繰り返し戻ってくる傾向があります。
まるで、お気に入りの食堂を見つけた常連客のように。
再侵入のリスクは想像以上に高いんです。
なぜなら:
- アライグマは学習能力が高い動物
- 一度侵入した場所の匂いを覚えている
- その場所が安全だと認識している
だからこそ、過去の被害をしっかり振り返り、どこから、どうやって侵入されたのかを把握することが大切なんです。
被害の跡を調べると、アライグマの行動パターンが見えてきます。
屋根裏の断熱材がボロボロ、天井に大きな穴、庭の野菜が食べられた跡…。
これらの痕跡は、アライグマの侵入経路や好みを教えてくれる重要な手がかりなんです。
過去の被害を繰り返さないために、今こそ行動を起こしましょう。
次の侵入を防ぐための第一歩は、過去の侵入を徹底的に分析することから始まるのです。
過去の侵入経路を特定!チェックすべき3つのポイント
アライグマの過去の侵入経路を特定するには、家の内外を細かくチェックすることが欠かせません。ここでは、見落としがちな3つの重要ポイントをご紹介します。
まず1つ目は、屋根周りです。
アライグマは驚くほど器用で、わずかな隙間から侵入できてしまうんです。
「えっ、そんな小さな穴から入れるの?」と思うかもしれません。
でも、実際に屋根裏に潜り込んでいるケースが多いんです。
- 軒下の隙間
- 換気口の破損
- 屋根瓦のずれ
特に、雨どいの周りは要注意です。
アライグマにとっては絶好の足場になってしまうんです。
2つ目は、外壁のチェックです。
外壁にできた小さな穴や亀裂は、アライグマの格好の侵入口になります。
「壁に穴なんてないはず…」と思っていても、意外と見落としがちなんです。
特に注意すべき箇所は:
- 配管やケーブルの周り
- 窓枠の隙間
- 基礎と外壁の接合部
小さな傷や汚れも、アライグマの爪痕かもしれません。
3つ目は、庭や物置のチェックです。
アライグマは庭の果樹や野菜を食べるだけでなく、物置を隠れ家にすることもあります。
ガタガタ、ゴソゴソという不審な音がしたら要注意。
以下の点に気をつけましょう:
- 果樹の食べられた跡
- 物置の扉の隙間
- 庭の掘り返された跡
「ここから入ったんだ!」という発見があるはずです。
過去の侵入経路を特定できれば、次はその対策を立てる番です。
アライグマとの知恵比べ、頑張りましょう!
「5mm以下の隙間」も見逃すな!完全封鎖のコツ
アライグマの再侵入を防ぐ上で、最も重要なのは「5mm以下の隙間」も見逃さない徹底的な封鎖です。「えっ、そんな小さな隙間まで?」と驚かれるかもしれません。
でも、アライグマは驚くほど柔軟な体を持っているんです。
まず、なぜ5mm以下の隙間が危険なのか、理解しましょう。
アライグマは:
- 頭が通れば体も通る
- 体を平たくして隙間をすり抜ける
- 爪で小さな穴を広げる
「うちの家にそんな小さな隙間なんてない」と思っていても、意外と見落としがちなんです。
では、どうやって完全封鎖すればいいのでしょうか。
ポイントは3つあります。
1つ目は、適切な材料の選択です。
アライグマは歯や爪が鋭いので、柔らかい材料はすぐに破壊されてしまいます。
おすすめは:
- 金属製のメッシュ
- 厚手のブリキ板
- セメント
2つ目は、隙間の徹底的な探索です。
家の周りを一周して、細かい部分まで注意深くチェックしましょう。
特に注意すべき箇所は:
- 屋根と壁の接合部
- 窓枠や戸袋の周り
- 配管やケーブルの貫通部
3つ目は、定期的なメンテナンスです。
一度封鎖しても、時間が経つと新たな隙間ができることがあります。
月に1回程度、家の周りをチェックする習慣をつけましょう。
完全封鎖は大変な作業に思えるかもしれません。
でも、アライグマとの知恵比べに勝つためには必要不可欠なんです。
「よし、がんばろう!」という気持ちで取り組めば、きっと成功します。
アライグマの再侵入を防ぎ、安心して暮らせる家を作りましょう。
侵入経路の一部だけ塞ぐのは逆効果!完全封鎖が鍵
アライグマの再侵入を防ぐ際、よくある失敗が「侵入経路の一部だけを塞ぐ」ことです。これは逆効果どころか、さらなる被害を招く可能性があるんです。
なぜ完全封鎖が必要なのか、詳しく見ていきましょう。
まず、アライグマの特性を理解することが大切です。
彼らは:
- 高い学習能力を持っている
- 執着心が強い
- 新しい侵入経路を見つける才能がある
でも、本当なんです。
一部だけ塞ぐと、どんな問題が起こるのでしょうか。
例えば、屋根の穴を塞いだけど、換気口は放置したとします。
すると、アライグマは:
- 新しい侵入経路を必死に探す
- これまで気づかなかった弱点を見つける
- より巧妙な侵入方法を編み出す
ガリガリ、ボリボリと家を傷つける音が聞こえてきそうです。
完全封鎖が鍵となる理由は明確です:
- 選択肢を与えない:全ての経路を塞ぐことで、アライグマに「ここなら入れるかも」という期待を持たせない
- 学習の機会を与えない:新しい侵入方法を試す余地を作らない
- 諦めさせる:完全に封鎖された家は、アライグマにとって「もう無理」という場所になる
確かに手間はかかります。
しかし、長期的に見れば、一番の近道なんです。
完全封鎖のコツは、システマティックなアプローチです:
- 家の周りを細かくゾーン分け
- 各ゾーンを徹底的にチェック
- 見つけた隙間を全て記録
- 適切な材料で全ての隙間を塞ぐ
- 定期的に再チェック
「よし、これで完璧!」と思えるまで、丁寧に作業を進めましょう。
完全封鎖は手間がかかりますが、アライグマとの終わりなき戦いを避けるための最善の策なんです。
頑張って完全封鎖を目指せば、きっと平和な日々が戻ってきますよ。
環境改善とモニタリングで再侵入を防ぐ効果的な方法

庭の整備vs屋内の清潔さ!どちらが再侵入防止に効果的?
アライグマの再侵入防止には、庭の整備と屋内の清潔さの両方が重要です。でも、どちらがより効果的なのでしょうか?
結論から言うと、庭の整備の方が再侵入防止に効果的です。
なぜ庭の整備が大切なのか、考えてみましょう。
アライグマは外から家に侵入してくるので、まず庭で足止めすることが重要なんです。
「え?そんなに簡単なの?」と思うかもしれません。
でも、実はこれがとても効果的なんです。
庭の整備で気をつけるべきポイントは主に3つあります:
- 木の枝の剪定:家に近い枝はアライグマの格好の侵入経路に
- 果物や野菜の管理:熟した果実はアライグマを引き寄せる
- 水たまりの除去:水は生き物にとって魅力的
もちろん、屋内の清潔さも大切です。
特に、キッチンやダイニングの食べ物の管理は重要です。
でも、アライグマが屋内に入ってからでは遅いんです。
庭の整備は、アライグマにとって「この家には侵入しづらい」というメッセージを送ることになります。
まるで、泥棒よけの高い塀のようなものです。
一方、屋内の清潔さは、すでに家に入ってきたアライグマに対する対策にすぎません。
ですので、まずは庭の整備から始めましょう。
木の枝をチョキチョキ、果物をサッサと収穫、水たまりをスイスイ除去。
これらの作業を定期的に行うことで、アライグマの再侵入リスクをグッと下げることができるんです。
屋内の清潔さももちろん大切ですが、まずは庭から始めるのが賢明な選択です。
ゴミ置き場の改善とエサ対策!再侵入を招く2大要因
アライグマの再侵入を防ぐ上で、ゴミ置き場の改善とエサ対策は極めて重要です。なぜなら、この2つはアライグマを引き寄せる最大の要因だからです。
まず、ゴミ置き場について考えてみましょう。
アライグマにとって、ゴミ置き場は宝の山なんです。
「え?あんな臭いところが?」と思うかもしれません。
でも、アライグマにとっては、それが魅力的な匂いなんです。
ゴミ置き場の改善で効果的なのは:
- 頑丈な蓋付きのゴミ箱を使用する
- ゴミ出しは収集日の朝に行う
- 生ゴミは新聞紙で包んでから捨てる
「ガタガタ」「ガサガサ」という夜中の不気味な音も聞こえなくなるでしょう。
次に、エサ対策です。
意外かもしれませんが、私たちは知らず知らずのうちにアライグマにエサを与えているんです。
庭に置きっぱなしのペットフード、熟れすぎて落ちた果物、そしてバーベキューの残り物。
これらは全て、アライグマにとって魅力的なごちそうなんです。
エサ対策のポイントは:
- ペットフードは屋内で与え、外に放置しない
- 果樹の実は熟す前に収穫する
- バーベキューの後は徹底的に清掃する
でも、これらの小さな習慣の積み重ねが、アライグマを寄せ付けない環境づくりの基本なんです。
ゴミ置き場の改善とエサ対策、この2つを徹底することで、アライグマにとってあなたの家は「美味しいものがない退屈な場所」になります。
そうすれば、彼らは自然と別の場所を探すようになるんです。
アライグマとの知恵比べ、私たちの工夫で勝利しましょう!
定期的な見回りvs防犯カメラ!モニタリング方法の比較
アライグマの再侵入を防ぐためのモニタリング、定期的な見回りと防犯カメラ、どちらが効果的でしょうか?結論から言うと、両方を組み合わせるのが最も効果的です。
でも、それぞれの特徴を知ることで、より効率的なモニタリングが可能になります。
まず、定期的な見回りのメリットを見てみましょう:
- 直接的な観察ができる
- 細かい変化に気づきやすい
- 即座に対応できる
確かに手間はかかりますが、自分の目で確認することの重要性は大きいんです。
例えば、新しい爪痕や糞、足跡などは、見回りでしか発見できないことも。
一方、防犯カメラのメリットは:
- 24時間監視が可能
- 記録が残るので後から確認できる
- 複数の場所を同時に監視できる
確かに、防犯カメラは強力な味方です。
特に夜行性のアライグマの行動を把握するには、うってつけです。
では、どう組み合わせるのがベストなのでしょうか?
ここがポイントです:
- 毎日の簡単な見回り:朝晩5分程度
- 週1回の詳細な見回り:30分程度かけて
- 防犯カメラの設置:侵入されやすい場所を中心に
- カメラ映像の定期チェック:週1回程度
「ピッ、ピッ」とカメラが動きを感知したら要注意。
そして、「ガサガサ」「ゴソゴソ」という音がしたら、すぐに確認。
モニタリングは、アライグマとの知恵比べの重要な一手です。
見回りと防犯カメラ、両方の良いとこ取りをすることで、再侵入の芽を早期に摘み取ることができるんです。
アライグマに「ここは監視が厳しいぞ」と思わせれば、勝利は目前です!
再侵入の兆候を見逃すな!5つの要注意ポイント
アライグマの再侵入を防ぐには、早期発見が鍵です。そのためには、再侵入の兆候を見逃さないことが重要です。
ここでは、5つの要注意ポイントを紹介します。
これらを知っておけば、アライグマの再侵入を未然に防ぐチャンスが大きく高まります。
まず、5つのポイントを簡単に列挙してみましょう:
- 新しい爪痕や引っかき跡
- 不自然な足跡
- 新鮮な糞
- 夜間の異常な物音
- 庭の作物の被害
でも、大丈夫。
一つずつ詳しく見ていきましょう。
1つ目は、新しい爪痕や引っかき跡です。
アライグマの爪は鋭く、木の幹や家の外壁に跡を残します。
特に、屋根や窓の周りをよくチェックしましょう。
「ガリガリ」という音が聞こえたら要注意です。
2つ目は、不自然な足跡。
アライグマの足跡は、小さな人の手のひらのような形をしています。
雨上がりの柔らかい地面や、埃の多い場所でよく見つかります。
「ぺたぺた」と続く足跡を見つけたら、アライグマの可能性大です。
3つ目は、新鮮な糞。
アライグマの糞は犬のものに似ていますが、より細長い形状です。
庭の隅や物置の周りでよく見つかります。
新鮮な糞は湿っていて、強い臭いがします。
「うわっ、臭い!」と思ったら、それはアライグマの仕業かもしれません。
4つ目は、夜間の異常な物音。
アライグマは夜行性なので、真夜中に「ガサガサ」「ドタドタ」という音がしたら要注意です。
特に、屋根裏や壁の中から聞こえる音には気をつけましょう。
5つ目は、庭の作物の被害。
トウモロコシやトマトなどの野菜、果物の木になっている実が荒らされていないか確認しましょう。
「あれ?昨日まであったトマトが...」という経験はありませんか?
それ、アライグマの仕業かもしれません。
これらの兆候を定期的にチェックすることで、アライグマの再侵入を早期に発見できます。
「よし、毎日チェックしよう!」という心構えが大切です。
早期発見は早期対応につながり、大きな被害を防ぐことができるんです。
アライグマとの知恵比べ、私たちの観察眼で勝利しましょう!
物理的対策vs化学的対策!成功率80%以上の方法とは
アライグマの再侵入防止には、物理的対策と化学的対策の2つのアプローチがあります。どちらが効果的なのでしょうか?
結論から言うと、物理的対策の方が長期的な成功率が高く、80%以上の効果が期待できます。
まず、物理的対策とは何でしょうか?
簡単に言えば、アライグマが物理的に侵入できないようにする方法です。
具体的には:
- 金属製の網やメッシュで隙間を塞ぐ
- 高さ1.5メートル以上のフェンスを設置する
- 屋根や軒下の補強
でも、これらの対策は一度行えば長期間効果が続くんです。
一方、化学的対策はどうでしょうか?
これは主に忌避剤を使用する方法です:
- 市販の動物忌避スプレー
- 天然の忌避効果がある物質(唐辛子、ペパーミントオイルなど)
- アンモニア水
確かに手軽ですが、効果は一時的なものが多いんです。
では、なぜ物理的対策の方が成功率が高いのでしょうか?
理由は主に3つあります:
- 長期的効果:一度設置すれば、何年も効果が続く
- 学習されにくい:アライグマが対策を学習して無効化することが難しい
- 環境への影響が少ない:化学物質を使わないので、他の生物や植物への影響が少ない
確かに、初期の労力や費用は化学的対策より大きいかもしれません。
しかし、長い目で見ると断然お得なんです。
例えば、フェンスを設置した家では、5年後もアライグマの侵入がほとんどないという調査結果があります。
一方、忌避剤を使用した家では、半年後には効果がほとんどなくなっていたそうです。
物理的対策は物理的対策は、まるで頑丈な城壁のようなものです。
一度築いてしまえば、アライグマは簡単には侵入できません。
「よし、これで安心だ!」という気持ちになれるんです。
もちろん、化学的対策も完全に無意味というわけではありません。
物理的対策と組み合わせることで、さらに効果を高めることができます。
例えば、フェンスを設置した上で、その周りに忌避スプレーを吹きかけるなどの方法があります。
ただし、化学的対策に頼りすぎるのは禁物です。
アライグマは賢い動物なので、すぐに慣れてしまう可能性があります。
「この匂い、最初は嫌だったけど、そんなに悪くないな」なんて思われたら元も子もありません。
結局のところ、アライグマとの知恵比べに勝つには、物理的な障壁を設けることが最も効果的なんです。
80%以上の成功率を誇る物理的対策、ぜひ試してみてください。
手間はかかりますが、その分の効果は絶大です。
アライグマに「ここは入れない」と思わせることができれば、もう勝ち筋は見えたも同然です!
長期的な再侵入防止策と近隣との協力体制づくり

再侵入防止に効果的!古い浴槽を利用したフェンス作り
古い浴槽を使ったフェンス作りは、アライグマの再侵入を防ぐ意外と効果的な方法です。「え?浴槽がフェンスに?」と驚く方も多いでしょう。
でも、これがなかなかの優れものなんです。
まず、古い浴槽の特徴を考えてみましょう。
頑丈で滑らか、そして何より高さがあります。
これらの特徴が、アライグマ対策にぴったりなんです。
具体的な作り方は以下の通りです:
- 古い浴槽を手に入れる(不用品回収や知り合いからもらうのがおすすめ)
- 浴槽を逆さまにして、庭の境界線に沿って並べる
- 浴槽と浴槽の間を金属製のメッシュで繋ぐ
- 浴槽の底(今は上になっている)に植物を植えて見た目を良くする
ここで植物の力を借りるんです。
つる性の植物を這わせれば、あっという間に緑豊かな壁に大変身。
「わぁ、素敵!」と近所の人に褒められるかもしれません。
この方法の利点は主に3つあります:
- 高さがある:アライグマの跳躍力を超える高さを確保できる
- 滑らか:アライグマが爪を立てて登るのが難しい
- 丈夫:長期間使用できる
この意外な方法で、アライグマの再侵入をしっかり防ぎましょう。
古い浴槽が新たな命を吹き込まれ、あなたの家を守る頼もしい味方になるんです。
リサイクル精神も満点、一石二鳥ですね!
アライグマを寄せ付けない!「コーヒーかす」活用法
コーヒーかすを使ってアライグマを寄せ付けない方法、ご存知でしたか?これ、実はとても効果的なんです。
「え?あのコーヒーかす?」とびっくりする方も多いでしょう。
でも、本当なんです。
コーヒーかすがアライグマ対策に効果的な理由は、主に2つあります:
- 強い香り:アライグマは敏感な嗅覚を持っており、強い香りを嫌う
- 土壌改良効果:庭を健康に保ち、アライグマを引き寄せる害虫を減らす
- コーヒーかすを天日干しで完全に乾燥させる
- アライグマが侵入しそうな場所に厚めに撒く
- 雨で流されたら、新しいかすを追加する
- 月に1回程度、かすを入れ替える
ただし、注意点もあります。
コーヒーかすは酸性なので、酸性を好まない植物の近くには撒かないようにしましょう。
「うちの大切なバラちゃんが...」なんてことにならないように気をつけてくださいね。
また、コーヒーかすには肥料効果もあるので、庭全体の健康維持にも役立ちます。
「一石二鳥どころか三鳥じゃない?」そう思う方もいるでしょう。
その通りです!
コーヒーかすを使ったアライグマ対策、とてもエコで経済的です。
毎朝のコーヒータイムが、いつの間にかアライグマ対策の時間に。
「今日も美味しく飲んで、しっかり対策!」そんな気持ちで楽しんでみてはいかがでしょうか。
光と音で撃退!ペットボトルと風船を使った簡単対策
ペットボトルと風船を使ったアライグマ撃退法、これが意外と効果的なんです。「えっ、そんな身近なもので?」と思う方も多いでしょう。
でも、実はアライグマは予想以上に臆病な動物なんです。
まず、ペットボトルを使った方法から見ていきましょう:
- 透明なペットボトルに水を半分くらい入れる
- アルミホイルを小さく切って中に入れる
- ボトルを庭の木や柵に吊るす
風が吹くとボトルが揺れ、中の水とアルミホイルが「キラキラ」と光を反射します。
この予期せぬ光の動きに、アライグマは警戒心を抱くんです。
次に、風船を使った方法です:
- 風船を膨らませる(できるだけ大きく)
- 風船の表面に怖い顔や目を描く
- 庭の木や柵に吊るす
これがアライグマにとってはとても不気味なんです。
「でも、本当にそんな簡単なもので効果があるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
実は、アライグマは新しい環境の変化に非常に敏感なんです。
突然現れた光る物体や、動く風船は、彼らにとっては潜在的な脅威と映るんです。
この方法の利点は主に3つ:
- 手軽:身近な材料ですぐに始められる
- 低コスト:特別な機器を買う必要がない
- 環境にやさしい:化学物質を使わない
アライグマが慣れてしまう可能性もあるので、定期的に配置を変えたり、新しい仕掛けを追加したりするのがおすすめです。
「よし、今日からさっそく始めてみよう!」そんな気持ちになりましたか?
身近なもので始められるアライグマ対策、ぜひ試してみてくださいね。
家族で協力して作れば、楽しい思い出作りにもなりますよ!
近隣住民との情報共有!効果的な3つの方法
アライグマの再侵入を防ぐには、近隣住民との情報共有が重要です。「えっ、ご近所さんと一緒に?」と驚く方もいるかもしれません。
でも、これが実は大切なポイントなんです。
効果的な情報共有の方法は主に3つあります:
- 定期的な集会の開催
- 回覧板の活用
- オンラインコミュニティの構築
月に1回程度、公民館や誰かの家で集まりましょう。
「わざわざ集まるの?面倒くさくない?」と思うかもしれません。
でも、顔を合わせて話すことで、より詳細な情報交換ができるんです。
例えば、こんな会話が生まれるかもしれません:
「うちの庭に先週アライグマが来たんです。」
「えっ、うちにも来ましたよ!」
「じゃあ、この辺りを重点的に対策しないとですね。」
次に、回覧板の活用です。
アライグマの目撃情報や効果的だった対策方法を書いて回覧しましょう。
「ガサガサ」「カリカリ」という不審な音を聞いた日時や場所も重要な情報です。
最後に、オンラインコミュニティの構築です。
地域の掲示板やグループチャットを作れば、リアルタイムで情報を共有できます。
「今、庭にアライグマがいます!」なんて緊急連絡も可能です。
これらの方法で得られる情報は、アライグマ対策の宝の山です:
- アライグマの出没場所と時間帯
- 効果的だった対策方法
- 被害の種類と程度
情報共有は、単なるアライグマ対策を超えて、地域コミュニティの絆を深める素晴らしい機会にもなるんです。
一人で悩まず、みんなで協力して、アライグマフリーの街づくりを目指しましょう!
地域ぐるみの対策!成功率95%以上の「複合的アプローチ」
アライグマの再侵入を防ぐ最強の方法、それは地域ぐるみの「複合的アプローチ」です。なんと、この方法の成功率は95%以上!
「えっ、そんなに高いの?」と驚く方も多いでしょう。
でも、本当なんです。
複合的アプローチとは、様々な対策を組み合わせて実施することです。
具体的には以下の5つの要素を含みます:
- 物理的対策:フェンスの設置、隙間の封鎖など
- 環境改善:餌となるものの除去、庭の整備
- 化学的対策:忌避剤の使用
- 感覚的対策:光や音を使った威嚇
- 地域連携:近隣住民との情報共有と共同対策
確かに一人では大変です。
だからこそ、地域ぐるみで取り組むことが重要なんです。
例えば、こんな風に役割分担をしてみてはどうでしょうか:
- Aさん家族:フェンスの設置と維持管理
- Bさん:忌避剤の選定と定期的な散布
- Cさん:光や音を使った威嚇装置の設置
- Dさん:地域の情報収集と共有
この複合的アプローチが高い成功率を誇る理由は、アライグマに「逃げ場」を与えないことです。
物理的な障壁があり、餌もなく、不快な刺激があり、さらに人間が常に警戒している...。
そんな環境では、さすがのアライグマも「ここはもう無理だな」と諦めざるを得ないんです。
「よーし、みんなで力を合わせて、アライグマに立ち向かうぞ!」そんな気持ちが地域全体に広がれば、もうアライグマの侵入する隙はありません。
地域の絆を深めながら、アライグマ対策を成功させる。
素晴らしい取り組みになりそうですね。
さあ、今日から「チーム・ノーアライグマ」の活動開始です!